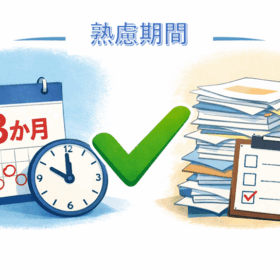Last Updated on 2025年10月10日 by 渋田貴正
日本に住んでいる方でも、ハワイの銀行に預金口座を持っていたり、現地に自動車や貴重品などの動産を保有しているケースは少なくありません。こうした海外資産は、日本の民法の適用範囲外になるケースも多く、日本の民法に基づいて作成した遺産分割協議書などの国内相続手続きだけでは処理できないため、現地法に基づいた別途の手続きが必要になります。
ここでは、ハワイ州に預金や動産を残して亡くなった場合の相続手続きについて、税務・登記の観点を交えながら解説します。
ハワイの「Affidavit for Collection」による簡易手続き
ハワイ州では、遺産の総額(自動車を除く)が10万ドル以下であれば、遺産管理人(Personal Representative)の選任を経ずに「Affidavit for Collection of Personal Property of the Decedent(宣誓供述書)」を提出することで、銀行預金や動産を相続人が直接受け取ることができます
この宣誓供述書には、次のような内容を記載します。
- 被相続人の死亡証明書の写し
- 遺産総額が10万ドル以下である旨
- 相続人であることを示す続柄や権利関係
- 対象となる銀行口座や動産の明細
提出先は、銀行や金融機関など財産の保有者です。提出後、金融機関は宣誓供述書に基づいて資産を引き渡す義務を負い、通常の遺産管理手続きと同等の効果が認められます(HRS §560:3-1202)。日本のような家庭裁判所への遺言検認や遺産分割協議書の提出は不要で、比較的迅速に預金を引き出せるのが特徴です。
例えば、日本に住むAさんがハワイの銀行に預金8万ドルを残して亡くなった場合、相続人である長女Bさんは、Affidavit for Collectionを作成し、死亡証明書と戸籍を添付して銀行に提出することで、遺産管理人を選任せずに預金を受け取ることができます。
ただし、日本の相続税申告では、この8万ドルを日本円に換算して申告しなければなりません。また、複数の相続人がいる場合は、誰がこの預金を取得するのかを日本で合意しておく必要があります。
Affidavit for Collection を使用する場合の実務上の手続きの流れ
ハワイでの預金や動産の相続手続きは、概ね以下の流れで進みます。
| 手続き段階 | 内容 | ポイント |
| ① 死亡証明書・戸籍の準備 | 日本で死亡証明書や戸籍謄本を取得 | 英訳+公証・アポスティーユが必要になる場合あり |
| ② 宣誓供述書の作成 | 相続人がAffidavitを作成 | ハワイ州法に基づいた様式(3C-E-210)を使用 |
| ③ 公証・提出 | 日本またはハワイで宣誓・署名し、銀行へ提出 | ハワイ州のNotary(公証人)による認証が必須 |
| ④ 預金の引渡し | 銀行が相続人へ預金や動産を引き渡す | 通常の遺産管理人による手続き不要 |
ポイントはハワイ州の公証人の認証が必要になる点です。日本の公証人ではありません。英訳・認証手続きは専門性が高く、現地の銀行とのやりとりも英語で行う必要があるため、実務上は日本とハワイの両方に明るい専門家に依頼することが多いです。
簡易な手続きが使えない場合のハワイでの検認手続き(プロベート)
ハワイ州では、遺産総額が10万ドルを超える場合や、相続人間で争いがある場合などには、先ほどご紹介したAffidavit for Collectionによる簡易な手続きは利用できません。その場合、裁判所で「検認手続き(Probate)」を行うことになります。
検認手続きとは、被相続人の遺言の有効性や相続人の確定を行い、裁判所の監督のもとで遺産を分配する手続きです。ハワイ州では、遺言がある場合を「Testate(テステート)」、遺言がない場合を「Intestate(インテステート)」と呼び、分配方法が異なります。
遺言がある場合は、その内容に従って遺産が分配されます。
一方で遺言がない場合は、ハワイ州の相続法(Intestate Succession)に従って、配偶者や子、親などの順位に基づいて分配されます。主な分配の概要は次のとおりです。
| 相続人の構成 | 生存配偶者の取得分 | 残余遺産の配分 |
| 直系卑属・親がいない | 全額 | - |
| 親のみがいる | 最初の20万ドル+残余の3/4 | 親が1/4 |
| 生存配偶者と連れ子がいる | 最初の15万ドル+残余の1/2 | 連れ子が1/2 |
| 被相続人の子がいる | 最初の10万ドル+残余の1/2 | 子が1/2 |
| 配偶者がいない場合 | - | 子→親→兄弟姉妹→祖父母の順 |
このように、ハワイの法定相続では配偶者の取得分が細かく定められており、日本の法定相続分とは計算方法や優先順位が異なります。日本での遺産分割協議と同様に、複数の相続人がいる場合は、事前に合意形成をしておくことが非常に重要です。
検認手続きの期間と費用
ハワイ州の検認手続きは、相続財産の内容や相続人の人数、紛争の有無によって大きく異なりますが、数か月から1年以上かかることも珍しくありません。複雑な案件では数年単位になることもあり、その間、相続財産は凍結されるため、遺族が自由に預金を引き出したり処分したりすることはできません。
また、裁判所費用や現地弁護士費用も発生します。時間と費用の負担が大きくなるため、ハワイでは検認手続を避けるために生前からの対策を行う方も多く見られます。
検認手続きの回避策
ハワイでは、以下のような手段によって検認手続きを回避し、相続時の手続きを簡略化することが可能です。
- 共同名義(Joint Property Ownership)
夫婦などで口座や不動産を共同名義にしておくことで、一方が亡くなった際に自動的に残存名義人に移転します。 - 死亡時受益者(Death Beneficiaries)
口座に死亡時の受取人を指定しておく制度で、日本の「死亡保険金受取人」に近い仕組みです。 - 撤回可能生前信託(Revocable Living Trust)
生前に財産を信託に移しておくことで、死亡時に検認を経ずに受益者へ資産を承継できます。 - 贈与(Gifts)
生前に贈与を行い、相続財産を減らすことで、検認を経る資産を減らす方法です。
こうした手法は、ハワイでは広く知られた相続対策であり、Affidavit for Collectionを使えない場合や高額な資産を有する場合には特に有効です。日本とは制度や文書の形式が異なるため、現地の法律専門家との連携が不可欠です。
ハワイにある資産についての日本での税務上の申告義務
ハワイの預金や動産も、日本の相続税法上は「海外資産」として課税対象になります。被相続人や相続人が日本の居住者である場合、世界中の財産が相続税の課税対象になるため、ハワイの資産も評価して相続税申告書に記載する必要があります。
預金については、死亡日時点の残高を為替レートで円換算して申告します。動産(自動車や貴金属など)は、現地での時価評価が必要となる場合があります。評価資料として、銀行の残高証明書や車両査定書などを取得しておくとよいでしょう。
また、日本では相続税の申告期限は「死亡を知った日の翌日から10か月以内」です。ハワイ側の手続きが遅れると評価資料が整わず、申告が難航するケースもあるため、早めの着手が重要です。
登記・名義変更との関係
ハワイの預金や動産には日本の不動産登記のような「登記」はありませんが、銀行口座や車両登録など、現地機関への名義変更手続きが必要になります。宣誓供述書で受領した後は、速やかに名義変更を完了させないと、現地での課税やトラブルの原因になることがあります。
例えば、複数の相続人がいる場合は、日本側で遺産分割協議を行い、誰がどの資産を取得するかを明確にしたうえでハワイ側に提出する必要があります。日本の協議書を英訳・認証して提出することも多いです。
ハワイに預金や動産がある場合、現地の法律・英語書類・日本の税務申告が複雑に絡みます。単なる翻訳やフォーム記入だけでは対応しきれない場面も多いため、税務と登記の両面を理解した専門家への依頼が安心です。
当事務所では、ハワイをはじめとする海外資産の相続手続きにも多数の実績があります。現地書類の作成から日本の税務申告まで一貫してサポート可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。合わせて、複数の資格を活かして会社設立や税理士サービスなどで多方面からクライアント様に寄り添うサポートを行っている。