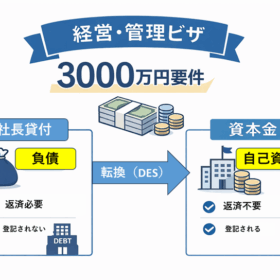Last Updated on 2025年7月27日 by 渋田貴正
相続放棄は、民法に基づいて行う法的手続きで、被相続人が死亡したことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。相続放棄をする理由は相続人によってさまざまですが、相続人が海外に住んでいる場合の相続放棄の手続きはどうなるのでしょうか。
実は、海外居住者でも相続放棄は郵送での手続きが可能です。来日して家庭裁判所に直接出向く必要はなく、必要書類を整えて郵送すれば申述は受理されます。ただし、裁判所から送られる照会書や通知書を確実に受け取ることが前提となります。
そこで重要になるのが「送達場所等届出書」という書類の活用です。
相続放棄の提出先と基本手順
相続放棄の申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。たとえば、被相続人が最後の住所地として東京都渋谷区に住んでいた場合は「東京家庭裁判所」が管轄となります。
申述は原則として郵送で可能で、必要書類は以下の通りです。
- 相続放棄申述書
- 被相続人の戸籍(出生から死亡まで)
- 相続人の戸籍謄本
- 送達場所等届出書(必要に応じて)
- 収入印紙(800円)
- 戸籍等の還付を受けたい場合には返信用のレターパックなど
海外在住者が日本国内を送付先にできる「送達場所等届出書」
海外に住んでいる相続人が相続放棄をする際、家庭裁判所からの照会書や受理通知などの重要書類を確実に受け取るためには、「送達場所等届出書」の提出が非常に重要です。この書類をあらかじめ提出することで、相続放棄に関する裁判所からのすべての書類を、日本国内の特定の住所へ送ってもらうことができます。
たとえば、次のような送達先を指定することが可能です。
| 送達場所指定先 | 特徴・メリット | 注意点 |
|---|---|---|
| 兄弟姉妹・子・配偶者など | 内容確認や返信作業を家族に任せられるため安心 | 連絡が確実に取れる相手を選ぶこと |
| 同じ相続に関与する兄弟や親族 | 手続きを一緒に進めやすく連携が取りやすい | 利害関係があるため信頼関係が必要 |
| 勤務先(会社) | 郵便物の受取体制が整っていることが多い | 会社の承諾を得ておくことが必須 |
| 司法書士・弁護士事務所など | 書類管理や裁判所対応も任せられ安心 | 有償でのサポートとなる場合が多い |
実際には、送達先として指定する相手にあらかじめ承諾を得ておくことが重要です。送達場所等届出書には、その人物の住所・氏名を正確に記載し、裁判所が書類を間違いなく送付できるように準備します。
この届出書は、相続放棄申述書と一緒に提出するのが原則ですが、提出後に送達先を変更したくなった場合は、改めて新しい届出書を提出することで対応できます。
送達先を適切に設定することは、海外からの相続放棄手続きを円滑に進めるうえで欠かせないステップです。送付先の選定に迷った場合や、書類作成に不安がある場合には、専門家に相談することをおすすめします。
郵送による相続放棄の申述の注意点
郵送で相続放棄申述を行う場合、以下の点に注意が必要です。
- 書類不備を防ぐ:必要書類はすべて漏れなく揃える
- 返信用封筒:切手を貼って同封(送達先が日本国内の場合)
- 署名・押印:本人による署名と、印鑑または署名の明確な記載が必要
また、海外から郵送する場合には郵便事情の遅延や紛失のリスクもあるため、国際書留や追跡可能な手段で発送するのが安心です。
相続放棄と税金・登記との関係
相続放棄をすると、その人は初めから相続人でなかったものとみなされます。したがって、相続税の申告義務も原則として発生しません。ただし、他の相続人が相続税の申告をする際には、相続放棄をした相続人も基礎控除の算定上1人分としてカウントできます。
また、相続放棄をすることにより、他の相続人の取得分が増えるため、結果として相続税の負担割合が変わることがあります。
不動産の相続登記を行う際には、放棄した人の「相続放棄申述受理証明書」が必要になります。登記実務においても、証明書の取得および書類の整備を事前に確認しておくことが重要です。
海外に住んでいても、日本国内の裁判所への相続放棄申述は可能です。「送達場所等届出書」を活用すれば、信頼できる日本国内の住所を送付先に指定することで、照会書などのやり取りもスムーズになります。
相続放棄に必要な書類の収集、裁判所とのやり取り、送付先の設定などに不安がある方は、専門家のサポートを受けることで、スムーズに手続きを進めることができます。当事務所では、海外在住者の相続放棄手続きにも多数の実績があります。どうぞお気軽にご相談ください。

司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。合わせて、複数の資格を活かして会社設立や税理士サービスなどで多方面からクライアント様に寄り添うサポートを行っている。