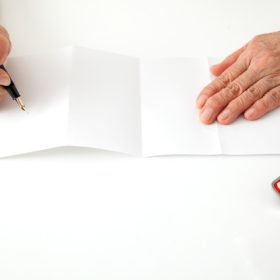Last Updated on 2025年6月26日 by 渋田貴正
相続人の中に外国籍の方がいる場合や、被相続人が外国籍の場合「日本の法律で相続分を譲渡することができるのか」と不安になる方も少なくありません。結論からいうと、外国籍であっても日本の法律に従い、相続分の譲渡は可能です。
ただし、被相続人(亡くなった方)が外国籍である場合には、そもそも日本の民法が適用されるかどうかという問題があります。
相続に適用される法律とは?外国籍の被相続人の場合
国際的な相続では、「どこの国の法律が適用されるのか」という点が非常に重要です。
原則として、相続に関する準拠法は被相続人の本国法によります。つまり、被相続人が外国籍であれば、その国の法律が相続全体に適用されるのが原則です。ただし、次のような「反致(はんち)」の考え方が働く場合、日本の民法が適用されることがあります。
例:被相続人がA国籍だが、A国の法律では「相続は被相続人の本国法でなく、住所地法(=日本)に従う」としている場合
→結果的に日本法(民法)が適用される
このように、日本の民法が適用される前提が整っていれば、外国籍の相続人による相続分の譲渡も、日本の民法に基づいて行うことができます。
| 法の適用に関する通則法 (相続)
|
相続分の譲渡とは?
「相続分の譲渡」とは、相続人が自己の持つ法定相続分または遺産分割前の相続における持分を、他の相続人または第三者に譲り渡すことをいいます。
| 民法 (相続分の取戻権)
|
相続分の譲渡を前提としてこの条文がありますので、「相続分の譲渡」そのものについての条文はありませんが、この条文を通して間接的にそういった概念が存在していることを表しています。
相続分の譲渡は、いわば相続人から他者(別の相続人や第三者)に対しての相続割合の包括贈与のようなものです。被相続人が遺言で包括遺贈する感じと似ているかもしれません。
外国籍の相続人が譲渡する場合の注意点
1.本人確認と身分証明に特有の対応が必要
譲渡契約書の作成や登記申請にあたっては、相続人であることを証明する資料と本人確認書類の提出が必要です。
外国籍かつ海外に居住している方は、以下のような書類が求められることがあります:
| 日本人の相続人 | 運転免許証、マイナンバーカード、印鑑証明書 |
| 外国籍・海外居住の相続人 | パスポート(コピー)、現地の住所証明書、公証役場または在外公館でのサイン証明書(署名証明)など |
また、日本語以外で書かれている場合は、法務局や金融機関にて翻訳文(和訳)が求められるため、早めの準備が大切です。
2.譲受人が第三者の場合の確認事項
譲渡の相手方が第三者(相続人以外)であっても、譲渡契約が有効であれば、譲受人は登記上も「その相続分を持つ者」として扱われます。
ただし、相続登記の際には、譲受人にも署名や押印を求められることがあるため、関係書類の整備が重要です。
登記の手続き
相続分の譲渡があった場合で、相続財産に不動産が含まれている場合、以下のような手続きが必要になります:
| 手続き | 内容 |
| 相続分譲渡証明書の作成 | 譲渡人・譲受人双方が合意した書面 |
| 登記申請 | 譲受人名義での登記変更または相続登記 |
| 添付書類 | 戸籍・住民票または署名証明書、相続関係説明図、譲渡証明書など |
相続分の譲渡の税務上の取扱い
譲渡の形態によっては、贈与税や譲渡所得税が発生する可能性があります。ただし、相続人間での相続分の譲渡の場合は、基本的には遺産分割協議と同様に扱われますので、相続税の枠内で計算となります。
| 相続人以外の第三者への譲渡 | 課税の可能性 |
| 無償で譲渡 | 贈与税(日本での贈与税課税の場合、基礎控除110万円超で課税) |
| 有償で譲渡 | 譲渡所得として所得税の課税可能性 |
税務上のリスクがあるため、対価の設定や契約書の記載は慎重に行う必要があります。また、贈与税が課税されると判断した場合、どこの国が課税権を持つのかということも重要な判断ポイントになります。
外国籍の相続人や被相続人が関与する相続分の譲渡では、「どの国の法律が適用されるのか」「印鑑証明書が使えないがどうするか」など、登記・税務の両面で複雑な判断が必要になります。
当事務所では、司法書士・税理士のダブルライセンスを活かし、ワンストップで対応可能です。国際的なケースも多数経験しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。合わせて、複数の資格を活かして会社設立や税理士サービスなどで多方面からクライアント様に寄り添うサポートを行っている。