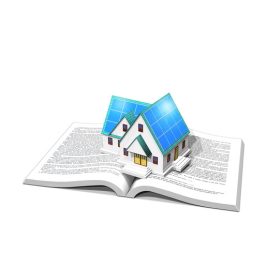Last Updated on 2025年1月19日 by 渋田貴正
相続分の譲渡とは?
相続分の譲渡とは、相続人が別の相続人や、相続人ではない第三者に、自分が相続財産を取得できる権利を譲渡することです。
相続分の譲渡を行うことで、譲渡をした相続人は遺産分割協議への参加が不要になります。相続放棄との違いは、相続放棄は最初から相続人がなかったものとして相続分が決まるのに対して、相続分の譲渡では、自分が選んだ人に自分の取り分を上乗せできる点です。
例)相続人A,B,Cがそれぞれ1/3ずつ相続できる場合
Aが相続放棄するケース→B,Cが1/2ずつ相続
AがBに相続分を譲渡するケース→Bが2/3、Cが1/3ずつ相続
このように、たとえば、3人の相続人A・B・Cがいる場合に、AがBに自分の相続分を譲渡すると、Bが2/3、Cが1/3を相続する形になります。このように、自分の相続分を特定の相手に譲ることが可能で、遺産分割協議を円滑に進めるための選択肢となります。
例えば、以下のようなケースで相続分の譲渡が活用されます。
- 配偶者への集中相続
子がいない夫婦で片方が先立った場合、亡くなった配偶者の兄弟が自分の相続分を残された配偶者に譲渡するケースがあります。これにより、残された配偶者が安心して生活を続けられるようになります。 - 特定の相続人への配慮
例えば、家業を継ぐ子どもに財産を集中させたい場合、他の兄弟姉妹が自分の相続分をその子どもに譲渡する形で協力することがあります。
相続分の譲渡は、財産の一部ではなく相続人の地位そのものの譲渡として扱われます。相続分の半分だけ譲渡して、残り半分は自分に残すといった場合は、相続分の譲渡ではなく遺産分割協議の中で行うことになります。
相続分の譲渡と相続放棄との違い
相続分の譲渡と相続放棄の違いをまとめると以下のようになります。
| 項目 | 相続分の譲渡 | 相続放棄 |
|---|---|---|
| 定義 | 相続人が自分の相続分を他の相続人や第三者に譲渡すること。 | 相続人が法律上「相続人ではなかった」とみなされる手続き。 |
| 目的 | 特定の人(相続人に限らない)に自分の相続分を渡すため。 | 相続による負担(負債や面倒な手続きなど)を免れるため。 |
| 効果 | 譲受人が譲渡された相続分を取得し、遺産分割協議に参加する。 | 放棄者の相続分は他の相続人に均等に再配分される(相続人が減る)。 |
| 手続きの管轄 | 家庭裁判所の関与は不要。譲渡証明書を作成し、実印や印鑑証明を添付して手続き。 | 家庭裁判所に対して放棄申述書を提出し、裁判所の許可が必要。 |
| 遡及効果 | 遡及効果はなく、譲渡契約成立時点から効力を持つ。 | 被相続人の死亡時点に遡り、「初めから相続人でなかったもの」とされる。 |
| 譲渡・放棄の相手 | 他の相続人または第三者(相続人以外の者)に対して譲渡可能。 | 放棄の相手は存在しない(法的に「相続権を放棄する」行為)。 |
| 遺産分割協議への影響 | 譲渡した相続人は協議に参加せず、譲受人が協議に参加する。 | 放棄した相続人は協議に参加せず、他の相続人で協議が行われる。 |
| 有償性 | 有償譲渡も可能。譲渡代価を自由に決定できるが、贈与税のリスクがある。 | 無償のみ(放棄自体に代価の授受は発生しない)。 |
| 特徴 | 自分の相続分を特定の人に渡せる柔軟性がある。 相続放棄より手続きが簡単。 |
債務を含む相続全体から免れることができる。 財産の負担を完全に放棄できる。 他の相続人とのやり取りが不要。 |
相続分の譲渡の方法
相続分の譲渡を行うには、その旨の証明書を作成して、譲渡する相続人に渡します。これは相続登記や相続預金の解約でも使用する書類となります。相続分譲渡証明書には、実印を押印して、譲渡する相続人の印鑑証明書を添付します。相続放棄のように、家庭裁判所で手続きするという必要はなく、事実上の相続放棄といえます。
| 相続分譲渡証明書
被相続人 山田 太郎 令和xx年xx月xx日 相続人 住所 東京都~~ |
上記の例は「無償」となっていますが、相続分の譲渡を有償で行うことも問題ありません。その場合は、他の相続人は関係なく、譲渡する相続人と譲渡を受ける者で金額を決めて、やり取りすれば問題ありません。有償譲渡の場合、その代価が市場価格に比して著しく低いと、贈与税の課税対象となる可能性がありますので、その点は注意しましょう。
相続分の譲渡は、遺産分割協議をする手前で、遺産分割協議に関係する相続人を減らすことができるほか、譲渡する相続人にとっても、相続放棄よりも単純で、かつ自分の相続分の行方を自分で決められます。状況に応じて、相続分の譲渡を活用しましょう。
相続分の譲渡を受けた者は、相続人であろうと第三者であろうと遺産分割協議の当事者として遺産分割協議に参加することになります。相続分の譲渡は、相続人が自由に財産の行方を決めることができる制度です。しかし、法的な手続きや税務上のリスクもあるため、慎重に判断することが求められます。特に相続放棄との違いを理解し、家庭内の事情や希望に応じて適切な選択を行うことが重要です。専門家と相談しながら、最適な方法を選びましょう。

司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。合わせて、複数の資格を活かして会社設立や税理士サービスなどで多方面からクライアント様に寄り添うサポートを行っている。