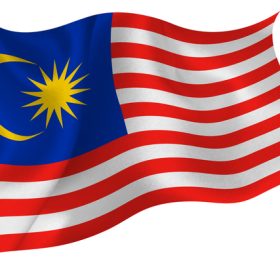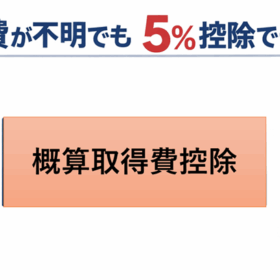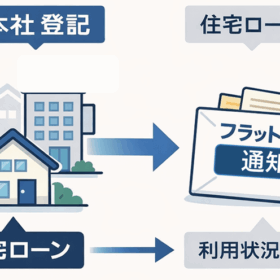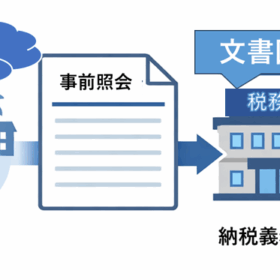Last Updated on 2025年12月12日 by 渋田貴正
インド国籍のご家族が日本で亡くなった場合、相続の準拠法がインド法と日本法のどちらになるのか、不動産や預貯金の手続をどの国のルールで進めるのかなど、一般の相続とは大きく異なる判断が必要になります。特にインドは宗教別に複数の相続法が存在し、書類の氏名表記にも揺れが出やすいため、専門家でなければ手続が進まないことも多いです。
相続法の基本構造とインドへの当てはめ
国際相続では「どこの国の法律で相続人や分割方法を判断するか」が最初の重要ポイントです。各国は必ずしも同じ法体系を採用しておらず、相続の準拠法が国によって大きく異なります。特にインドのように宗教別に相続ルールが異なる国の場合、前提を押さえておかないと誤った判断につながるおそれがあります。理解の助けとして、まず代表的な分類を表にまとめます。
| 分類 | インド | |
|---|---|---|
| 相続統一主義か相続分割主義か | 相続統一主義:相続全体を一つの国の法律で判断する方式 相続分割主義:動産と不動産など、財産ごとに準拠法が変わる方式 |
相続分割主義(動産=ドミサイル、不動産=所在地) |
| 人的不統一法国かどうか | 宗教・慣習などで相続法が複数存在する国 | 該当する(ヒンドゥー・ムスリム等) |
| 場所的不統一法国かどうか | 不動産は所在地法、動産は別基準など複数の基準を併用 | 該当する |
インドは複雑な法体系を採用しているため、日本人の相続よりも準拠法の判定に専門性が求められます。
具体例として、インド国籍の被相続人Aの相続準拠法の判断を考えてみます。
本件の被相続人Aはインド国籍で、日本に永住し、日本人配偶者B・日本国籍の子C・Dがいます。まず、日本の通則法36条では「相続は被相続人の本国法による」と規定されているため、原則としてインド法が出発点になります。
しかしインド相続法5条は、不動産と動産で準拠法を切り分ける「相続分割主義」を採用しています。不動産については、その不動産が所在する国の法律が準拠法となり、動産については被相続人のドミサイル、つまり生活の本拠がどこにあるかによって適用される法律が決まります。本件のAは、日本で婚姻し、子が出生し、永住資格を取得して日本で死亡しているため、死亡時点のドミサイルは日本にあったと判断されます。
そのため、日本にある不動産については、インド法の定めにより「不動産所在地の法」に従うことになり、結果として日本法が適用されます。また、預貯金や株式などの動産についても、Aのドミサイルが日本である以上、所在地が日本であってもインドであっても日本法を適用することになります。結果として、インド国内の不動産を除いた大部分の財産は、日本民法を基準に相続人の範囲や相続分を判断することになる、という整理が適切です。
国際相続では「本国法→相手国の国際私法→反致の有無」という手順を踏む必要があるため、専門家でなければ判断が難しい領域です。
インド国籍の被相続人が所有していた日本にある不動産の相続登記
インドの法律上、不動産は「不動産所在地法」が基本ですから、日本にある不動産の相続については日本民法と不動産登記法に完全に従うことになります。この点は国籍に関係なく、インド人であっても手続方法は日本人の相続と同じです。
ただし問題は「相続人が誰かを日本の資料だけで証明できるか」という点です。
Aが日本の戸籍制度の対象外である以上、A自身の戸籍は存在せず、日本側で取得できる情報は限定的です。具体的に証明できる事実は次の三つです。
・Aの死亡 → 住民票の除票(死亡日・住所地)
・配偶者Bとの婚姻の有効性 → Bの戸籍(婚姻事項記載)
・子C・DがAの実子であること → Bの戸籍にAが父として記載
一方で、Aにインド国内に他の子がいるかどうかまでは公的資料で確認できないため、「Aの相続人はB・C・Dであり、他にいない」という証明書類は原則存在しません。このため、実務では相続人全員の上申書などで補完する運用が多く見られます。
特にインド出身者には書類ごとにローマ字表記が異なるケースも多く、「同一人物であることの証明」が追加で求められる場合があります。
遺産分割協議書を作成する場合は、署名のローマ字についても実務的に注意が必要です。Aの名前が「RAJ KUMAR」と「RAJ KUMAR SHARMA」で異なる書類が混在しているときは、その旨を説明した上申書を作っておくと後のトラブル防止になります。
インド国籍の被相続人が所有していた日本にある預貯金・株式・動産の相続手続
預貯金や株式・投資信託・車両などの動産は、Aのドミサイルが日本にあるため「すべて日本民法が準拠法」とされます。相続人の範囲や法定相続分も日本民法に基づいて判断されるため、手続の基本的な流れは日本人の相続と変わりません。
しかし、金融機関ごとに必要書類の考え方に差があり、特に外国籍の被相続人の場合は次の書類が追加で求められるケースがあります。
・氏名の綴りの違いを説明する上申書
・旧パスポートや在留カードの写し
・(必要に応じて)宣誓供述書の公証
インド人の相続では、英文名の揺れが実務上の最大の課題となります。
「KUMAR」「KUMAR S」「K. RAJ」など同一人物であっても別人と判断されるリスクがあり、金融機関によっては厳格な照合を求める場合があります。
基本的には、不動産登記で使用した相続関係書類一式をそのまま流用できますので、まずは登記用の書類を整えておくと全体の効率が良くなります。
インド国内にある不動産・預貯金の相続手続
インド国内の財産については、インド法に基づき現地で相続手続きを行う必要があります。
特にインドでは宗教別相続法制(ヒンドゥー法・ムスリム法・キリスト教徒法など)が存在するため、Aがどの法体系に属するかを確認するところから始まります。
また、インド国内の相続手続には以下のような特徴があります。
・出生証明や婚姻証明の提出が求められる
・日本の資料は翻訳およびアポスティーユが必要
・各州ごとに運用が異なり、管轄庁の判断もまちまち
・固定資産の相続登録には現地の弁護士または会計士の関与が一般的
インド国内の財産が一定規模の場合、日本側で遺産分割が完了していても、インド側で別途相続人の確認手続(Succession Certificateなど)が必要になることがあります。そのため、日本とインドで手続の順番を誤ると「日本では終わったがインドで進まない」という状態になりかねません。
この点はインド現地の専門家との連携が必須になってきます。
インド国籍の相続は、準拠法の判断、反致、氏名同一性、インドと日本の書類収集、各金融機関との実務調整など、専門性の高い分野です。当事務所では、税理士と司法書士の資格を兼ね備えた専門家が、日本側の相続登記と税務申告を一体でサポートいたします。また、必要に応じてインド現地の専門家と連携してインド国内の相続手続きもサポートいたします。国際相続でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。合わせて、複数の資格を活かして会社設立や税理士サービスなどで多方面からクライアント様に寄り添うサポートを行っている。