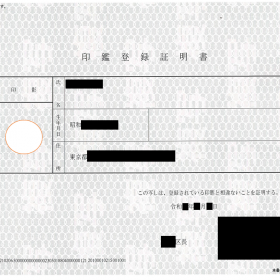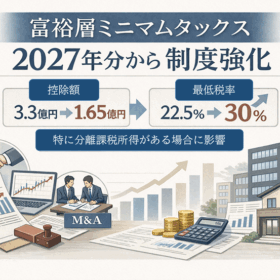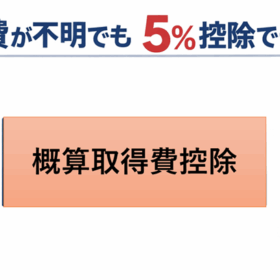Last Updated on 2025年7月11日 by 渋田貴正
不動産を共有している人の中には、ごくまれに一方の共有者に相続人がいない方がいらっしゃいます。たとえば「遠い親戚同士で土地を共有していたが、その親戚が亡くなり、結婚歴も子どももいない」というようなケースです。自分自身はその親戚の相続人には該当しないため、相続登記はできない、といった状況になります。
このような場合、「自分が自動的に持分を取得するのでは?」「長年放置されているから時効取得できるのでは?」と考える方も少なくありません。
しかし実際には、相続人がいない場合でも、すぐに他の共有者に持分が帰属するわけではなく、一定の法的手続きが必要です。
相続人がいない場合でも、いきなり共有持分は移らない
民法255条では「共有者が死亡し相続人がいない場合、その共有持分は他の共有者に帰属する」と定められています。
ただし、これはあくまで最終的な帰属先の話であって、相続人がいないことが確定したからといって、即座に他の共有者に移転されるわけではありません。
まずは、遺言による受遺者や相続債権者、特別縁故者に対する配慮が必要です。それでもなお残った財産について、はじめて他の共有者に帰属されるというのが原則です。
相続人がいない場合の共有持分の帰属先の優先順位
| 優先順位 | 帰属先 | 解説 |
| 第1位 | 遺言による受遺者 | 遺言により財産を譲り受けた人 |
| 第2位 | 相続債権者 | 被相続人に貸金等の請求権がある者 |
| 第3位 | 特別縁故者 | 被相続人と特別な関係にあった人(同居、介護など) |
| 第4位 | 他の共有者 | 上記がいないときに初めて適用(民法255条) |
| 最終的 | 国庫 | 区分所有建物など、例外的に国へ帰属する場合あり |
区分所有建物(マンション)の敷地持分は国に帰属
注意が必要なのは、マンションのような区分所有建物の敷地持分です。民法とは異なり、「区分所有法」により、敷地と建物の分離処分が禁止されているため、たとえ他の共有者がいたとしても、共有持分は国庫に帰属します。
| (分離処分の禁止) 区分所有法 第22条 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。 (民法第二百五十五条の適用除外) 区分所有法 第24条 第22条第1項本文の場合には、民法第255条(中略)の規定は、敷地利用権には適用しない。 (持分の放棄及び共有者の死亡) |
共有持分の帰属までに必要な手続きと期間
相続人がいない場合、次のような流れで手続きが進みます。帰属までには最低でも9か月以上かかるのが通常です。
共有持分が帰属するまでの流れ
- 相続財産清算人の選任申立て(民法952条)
- 清算人による公告(6か月)(民法952条)
- 相続債権者・受遺者の申出(2か月以上)(民法957条)
- 特別縁故者による分与申立て(3か月以内)(民法958の2)
- 家庭裁判所の審判
- 残余財産の他の共有者への帰属(民法255条)または国庫帰属
不動産の共有持分を時効取得できるのでは?
よくある誤解として、「持分が長年使われていないから、時効取得できるのでは?」という考えがあります。
しかし結論から言うと、共有持分の時効取得は極めて困難です。理由は以下のとおりです。
- 共有物は他人の権利が明確に存在するため、単独で「所有の意思」による占有を主張しにくい
- 登記簿上で他人名義が明示されており、「善意の占有」ではない
- 他の共有者が自由に利用していれば、自分だけが単独所有しているとはいえない
また、今回のように法定相続人がいない場合には、相続財産清算人の制度や特別縁故者への分与など、法律で帰属のルールが整備されています。時効取得を主張するまでもなく、正規の手続きを踏めば共有持分を取得できるのです。
他の共有者の所在・生死が不明な場合の対応
共有者が複数いる場合、他の共有者について「死亡しているかもしれない」「相続人が分からない」「どこに住んでいるのか不明」といったケースもあります。
このようなときは、以下の制度を活用して対応を検討します。
| 手続き | 内容 |
| 民法262条の2 | 所在不明共有者の持分を他の共有者に帰属させる裁判 |
| 民法262条の3 | 所在不明共有者の持分を第三者に譲渡させる裁判 |
| 民法25条 | 不在者財産管理人の選任申立て |
相続税の課税関係に注意
他の共有者が持分を取得した場合、その取得は「遺贈」とみなされ、相続税の課税対象となります(相続税基本通達9-12)。
また、取得者が被相続人の法定相続人でない場合には、相続税額に2割加算されます(相続税法18条)。
相続税の申告期限
| ケース | 申告期限 |
| 特別縁故者がいない | 分与申立期限の翌日から10か月以内 |
| 特別縁故者がいた | 分与審判確定を知った日の翌日から10か月以内 |
以下のような関係のある方は、家庭裁判所に申立てをすることで特別縁故者として財産を受け取れる可能性があります。
- 被相続人と長年同居していた内縁の配偶者
- 無償で介護・看護をしていた人
- 被相続人に仕送りを続けていた親族
- 任意後見人や身元保証人になっていた人
相続人がいない不動産の持分問題は、法律と税務の両面から対処が必要です。家庭裁判所への手続きから相続税の申告、登記の整備まで、一人で対応するのは非常に困難です。
当事務所では、税理士と司法書士の資格を活かし、ワンストップで相続財産の処理や不動産の整理をサポートしております。
まずはお気軽にご相談ください。初回のご相談は無料です。

司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。合わせて、複数の資格を活かして会社設立や税理士サービスなどで多方面からクライアント様に寄り添うサポートを行っている。