Last Updated on 2025年5月5日 by 渋田貴正
「親から子へ」「知人から友人へ」。不動産や高額なモノ(車・骨董品など)を個人間で時価よりも安い価格で譲り渡すケースは珍しくありません。しかし、単純に安く売るだけでは済まないのが日本の税制と登記制度。知らずに行うと、思わぬ贈与税や譲渡所得税、登録免許税が発生することもあります。
時価より安く譲渡すると「贈与」とみなされる
たとえば、市場価格3,000万円の土地を1,000万円で息子に売却したとします。この場合、「売買」と言いつつ、差額2,000万円については贈与と見なされます。
| (贈与又は遺贈により取得したものとみなす場合) 相続税法 第7条著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合においては、当該財産の譲渡があつた時において、当該財産の譲渡を受けた者が、当該対価と当該譲渡があつた時における当該財産の時価(中略)との差額に相当する金額を当該財産を譲渡した者から贈与(当該財産の譲渡が遺言によりなされた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。 (後略) |
【事例】安価譲渡の贈与税判定(イメージ表)
| 時価 | 譲渡価格 | 差額 |
| 3,000万円 | 1,000万円 | 2,000万円が贈与税の課税対象 |
ここで気になるのが、「著しく低い価額」がいくらかという点です。この点について明確に法律で定められた基準はありませんが、一つの指標としては以下の目安が用いられています。
| 判定基準 | 内容 |
| 概ね時価の70%未満 | 一般的に「著しく低い」と判断されやすい。 |
| 時価の50%以下 | ほぼ確実に贈与とみなされる(否認リスクが高い)。 |
この70%や50%といった基準は、個人の棚卸資産の低額譲渡(70%)や個人から法人への低額譲渡(50%)に関する考え方を参考にしており、不動産の低額譲渡でも目安として活用されています。ただし、あくまで参考基準であり、具体的事案ごとに総合的に判断されます。
贈与税だけじゃない!元の持ち主には譲渡所得税が課税される
不動産の売却には譲渡所得税も関係します。安く売っても、売主が取得費より高く売った場合、利益に対して所得税・住民税がかかります。
【譲渡所得の計算式】
譲渡価格 -(取得費+譲渡費用)= 譲渡所得
たとえば、取得費500万円の土地を1,000万円で譲った場合、500万円が譲渡所得となります。
※所有期間が5年超なら長期譲渡所得(税率20%程度)、5年以下なら短期譲渡所得(税率39%程度)になります(所得税法第31条)。
登録免許税と不動産取得税も発生する
不動産の名義変更には登録免許税と不動産取得税がかかります。
【登録免許税の概要】
売買:固定資産税評価額 × 2%(租税特別措置法第72条) 贈与:固定資産税評価額 × 2%
なお、売買価格が安くても登録免許税の基礎は「固定資産税評価額」なので注意が必要です。
また、不動産取得税も固定資産税評価額×3%(または4%)を基準に算出されます。
【登記に必要な書類】
- 売買契約書または贈与契約書
- 固定資産税評価証明書
- 登記識別情報(権利証)
- 印鑑証明書
贈与が成立した場合は贈与税申告書、譲渡所得が出た場合は確定申告書も必要です。
さらに、贈与税については基礎控除110万円を超える部分に課税されます。
【税金のまとめ表】
- 時価:3,000万円
- 譲渡価格:1,000万円
- 取得費:500万円
| 税金の種類 | 課税される人 | 課税対象額 | 備考 |
| 贈与税 | 買主(譲受人) | 2,000万円(時価3,000万円 - 譲渡価格1,000万円) | 相続税法第7条により「時価との差額」が贈与とみなされる |
| 譲渡所得税 | 売主(譲渡人) | 500万円(譲渡価格1,000万円 - 取得費500万円) | 所得税法第31条に基づき課税。所有期間により税率が異なる |
| 登録免許税 | 買主(譲受人) | 固定資産税評価額×2% | 租税特別措置法第72条 |
| 不動産取得税 | 買主(譲受人) | 固定資産税評価額×3%(または4%) | 地方税法第73条の2 |
不動産や高額資産を安く譲り渡す行為は、単なる売買では済まない税務・法務上のリスクが多く潜んでいます。特に親族間や知人間の取引は、税務署に目をつけられやすいため、事前の計画と正確な申告・登記が必要です。
「税金も登記も両方対応できる専門家」に依頼することが、安心・安全な資産移転のカギと言えるでしょう。
不動産や高額資産の譲渡でお悩みの方は、ぜひ税理士・司法書士の両資格を持つ当事務所へご相談ください。税務と登記のワンストップ対応で、最適な解決策をご提案いたします。

司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。合わせて、複数の資格を活かして会社設立や税理士サービスなどで多方面からクライアント様に寄り添うサポートを行っている。







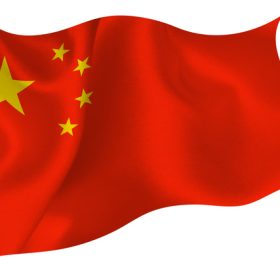




時課税-280x280.png)

