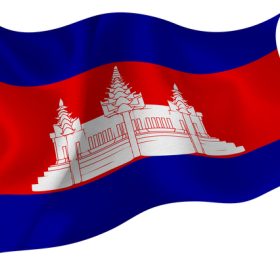Last Updated on 2025年10月30日 by 渋田貴正
相続人の中に、すでに日本を離れて海外に居住している方がいる場合、遺産分割協議書の作成にあたって注意が必要です。日本では、相続人が実印を押して印鑑証明書を添付するのが一般的ですが、海外に移住した非居住者には日本の住民票がなく、印鑑証明書を取得できません。
そのため、代替となる「署名証明書(サイン証明書)」の用意が不可欠です。海外からの相続手続きでは、この署名証明書が遺産分割協議書の信頼性を確保する重要な書類となります。現地での本人確認を経て発行されるため、法務局や金融機関でも正式な本人確認書類として扱われます。
大使館や総領事館で取得する署名証明書の仕組みと注意点
署名証明書で証明されるのは「署名した事実」に限られます。遺産分割協議書の内容が正確か、法的に有効かまでは証明しません。そのため、署名証明書付きの協議書であっても、内容面の確認は別途日本側で慎重に行う必要があります。
また、署名証明書は、あくまで本人が自らサインを行ったことを証明するためのものです。領事館で本人確認が行われる点が最大の特徴であり、他人の代筆や郵送による取得は認められません。発行までには予約や手数料が必要な国もあるため、早めの準備をおすすめします。
署名証明書の種類
日本の各在外公館では、署名証明書には次の2種類があります。
- 単独形式
領事館備え付けの用紙に署名し、その署名自体を証明してもらうものです。一般的な契約書など、提出先が指定様式を求めない場合に利用されます。 - 貼付形式
署名する側であらかじめ書類(例:遺産分割協議書)を用意し、領事館の窓口で署名を行い、その書類に署名証明書を貼り付けてもらうものです。
遺産分割協議書では、必ず「貼付形式」を使用します。未署名の協議書を持参し、領事館で署名し、その場で署名証明書を貼付してもらうことで、本人の署名が真正であることを証明できます。貼付形式で発行された証明書は、法務局や銀行でも広く受理される形式です。
| 貼付(貼り付け)形式 | 単独形式 | |
|---|---|---|
| 概要 | 申請者が用意した書類(例:遺産分割協議書)に、領事館で署名し、その書類に署名証明書を貼り付けてもらう形式。 | 領事館備え付けの用紙にその場で署名し、署名そのものを証明してもらう形式。 |
| 主な使用目的 | 相続手続・登記申請・契約書提出など、具体的な書類に署名が必要な場合。 | 一般的な本人署名証明や会社設立時の本人確認など、特定の書類に添付しない場合。 |
| 発行対象書類 | 遺産分割協議書、不動産売買契約書、委任状など実際に提出する文書。 | 領事館指定の証明用紙(汎用的に利用可能)。 |
| 署名方法 | 未署名の書類を領事館に持参し、窓口で署名して貼付証明を受ける。 | 領事館のカウンターで備え付けの用紙に署名するだけ。 |
| 提出先での利用可否 | 法務局・金融機関・裁判所など、印鑑証明書の代替として正式に利用可能。 | 書類との関連性が薄いため、相続手続などでは通常使用不可。 |
| 利便性・手間 | 持参書類が必要なため準備はやや手間がかかるが、正式な証明として通用。 | 手軽に取得できるが、提出先によっては受理されないことがある。 |
| 実務での使用頻度 | 相続や登記関係ではほぼすべてこの形式。 | 日常的な署名確認や軽微な手続で使用されることが多い。 |
署名証明書を取得する際には、いくつかの実務的な注意点があります。まず、署名証明書は本人が日本大使館または総領事館の窓口で署名しなければならず、郵送での発行や代理申請はできません。領事官が本人の署名を目の前で確認することによってのみ、証明が成立する仕組みだからです。
また、証明書自体には法的な有効期限は定められていませんが、提出先の法務局や金融機関によっては「発行から3か月以内のもの」を求められることがあります。実際には、登記や口座解約などの手続が長期化するケースも多いため、相続全体のスケジュールを見越して発行時期を調整することが重要です。
海外在住の相続人が複数いる場合、それぞれの相続人が自らの居住国にある日本大使館や総領事館で署名証明書を取得する必要があります。例えば、アメリカでは州ごとに管轄領事館が異なり、事前予約制で本人確認書類のコピー提出を求めるところもあります。オーストラリアやカナダなどでも、郵送予約やオンラインフォームの事前提出が必須のケースがあります。
このように、国や地域によって受付方法や発行日数が大きく異なるため、早めの情報収集が不可欠です。特に、2024年4月に施行された不動産登記法の改正により、相続登記の申請が義務化された今では、署名証明書の遅れが全体の手続きに影響する可能性もあります。海外在住の相続人がいる場合には、国内の相続人と連携し、書類準備から発送、提出までを一体的に進めることが円滑な相続の鍵となります。
署名証明書は、海外在住の相続人が日本国内の相続手続きを行ううえで欠かせない書類です。領事館が遠方にあることも多く、必要書類を漏れなく揃えて一度で手続きを完了させることが大切です。
また、国によっては書類の翻訳が求められる場合や、外国人配偶者が含まれるケースなどもあり、専門的な判断が必要になることがあります。
大使館や総領事館で署名証明書を取得する際に必要な書類
署名証明書を取得する際には、次の書類が一般的に必要です。
- 未署名の遺産分割協議書(日本語で可)
- 有効な日本のパスポート
- 現地での在留資格を示す公的書類(滞在許可証や運転免許証など)
領事館では、申請時に「使用目的」や「提出先」を記入します。目的欄には「相続手続のため」、提出先欄には「法務局」または「金融機関」と記載しておくとスムーズです。
国によっては、滞在証明や住所証明の提示が求められる場合もあります。また、領事館によって受付日や発行までの期間が異なるため、事前にウェブサイトで必要書類や手数料を確認しておくことが重要です。
署名証明書といっしょに在留証明書も併せて取得しておくと安心
署名証明書には現地住所の記載がないため、別途「在留証明書」も取得しておくことをおすすめします。在留証明書は、現地の住所を日本語で証明する書類で、金融機関の相続手続や登記申請で住所確認を求められた際に役立ちます。
特に、不動産の登記や預金口座の名義変更など、本人確認が厳格な手続きでは、署名証明書と在留証明書をセットで提出するケースが一般的です。どちらも同じ領事館で申請できるため、署名証明書と同時に取得しておくと効率的です。証明書の発行日が同一であれば、書類の整合性が取りやすく、後日の確認もスムーズになります。
当事務所では、海外在住の相続人がいる場合の遺産分割協議書作成、署名証明書・在留証明書の取得サポート、登記申請まで一貫して対応しております。ご家族が海外にお住まいの方は、ぜひ一度ご相談ください。

司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。合わせて、複数の資格を活かして会社設立や税理士サービスなどで多方面からクライアント様に寄り添うサポートを行っている。