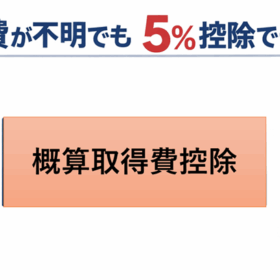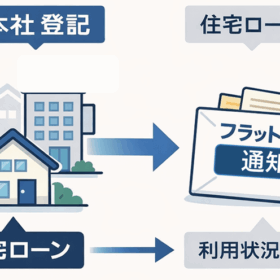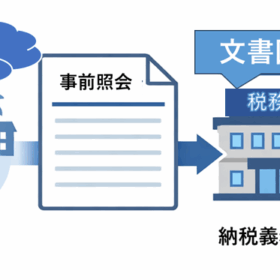Last Updated on 2025年11月20日 by 渋田貴正
不動産の所有者が住所や氏名を変更した場合、従来は所有者自身が登記の変更申請を行う必要がありました。しかし2026年4月1日からは、氏名・住所の変更日から原則 2年以内に変更登記を申請する義務が課されます。
さらに、この手続負担を軽減するために、法務局側で住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)を検索し、最新の情報に基づいて職権で変更登記を行う 「スマート変更登記」 が導入されます。このスマート変更登記を実効性あるものにするために不可欠なのが、2024年4月から始まった 「検索用情報の申出制度」 です。
不動産登記の検索用情報とは何か
検索用情報とは、登記官が「登記簿上の所有者」と「住基ネットに記録された人物」を照合するために必要となる情報です。具体的な内容は次のとおりです。
・氏名
・フリガナ(外国籍の人については、氏名の表音をローマ字で表示したもの)
・生年月日
・住所(住民票上の住所)
・通知用メールアドレス(任意)
氏名、生年月日、住所が一致することで、登記官は本人を特定でき、住所変更があった際に自動で職権登記(スマート変更登記)を行えるようになります。もともと氏名と住所は登記される情報なのでフリガナと生年月日があらたに追加された情報になります。
特に生年月日は、同姓同名の人物が多い場合でも確実に本人を識別できるため、検索用情報の中でも重要な要素です。
検索用情報の申出を行っておくことで、所有者自身が住所の変更登記を忘れてしまった場合でも、自動的に最新の状態に保たれる可能性が高まり、不動産の管理が格段に楽になります。
メールアドレスは必須ではありませんが、届け出ておくことで、スマート変更登記が行われた際に「登記が更新された」という通知を受け取れる ようになります。実際に職権で変更されたタイミングは登記簿を見ないと分かりにくいため、メール通知を設定しておくと、住所変更が反映された時期を確実に把握でき、名義管理がより安心になります。
また、法務局からの補正連絡などがメールで届くわけではありませんので、「手続通知が全部メールになる」という趣旨ではありません。
あくまで「スマート変更登記が完了したことを知らせるための通知先」という位置づけです。メールアドレスを入力し忘れても制度の利用自体には支障がありません。あくまで通知先を付加するオプションであり、スマート変更登記の有無そのものには影響しません。
不動産登記の検索用情報の申出方法
検索用情報の申出方法は「登記と同時に申出する方法」と「後日に単独で申出する方法」の二つに分かれます。
登記申請と同時に申出する方法
売買、相続、贈与、新築による保存登記など、何らかの登記手続きを行うタイミングで、検索用情報の申出を併せて行う方法です。
この方法では、
・申出書類をまとめて作成できる
・本人確認の手続も登記申請と一体で行える
・不動産の個数が多い場合でも効率的
といったメリットがあります。
たとえば相続登記では、相続人が複数いる場合、将来的にそれぞれの住所変更登記が必要になりますが、この段階で検索用情報を申出しておくことで、将来の手間を減らせます。
なお、検索用情報の申出ができるのは 登記申請人に限られる という制度上の制約があります。
たとえば相続登記で、法定相続分どおりに共有名義にする場合でも、実務では複数の相続人のうち一部の法定相続人のみが申請人となることも可能です。この場合、申請人とならない相続人は検索用情報を申出することができません。
そのため、
・相続人全員が将来のスマート変更登記の対象になりたい
・住所変更手続を極力自動化したい
といった希望がある場合には、
相続登記の申請方式(代表者申請にするか、全員申請にするか)自体を検討する必要があります。
この点は制度を正確に理解していないと見落とされやすく、司法書士が事前にアドバイスすべき重要ポイントです。
後日、検索用情報のみを申出する方法
すでに登記済みの不動産について、後から検索用情報を申出する方法です。
この場合は所有者本人が法務局に直接出向き、本人確認書類(マイナンバーカードや住民票など)を提示する必要がある場合があります。
不動産を複数所有している場合には、不動産番号の一覧を整理して提出する必要があります。漏れがあると「一部の物件だけスマート変更登記が作動しない」という事態も起きるため、司法書士に依頼したうえで整理・申出するケースが増えています。
不動産登記の検索用情報の申出とスマート変更登記との関係
検索用情報とスマート変更登記は、密接に連動する仕組みになっています。
- 検索用情報の申出あり
→登記官が住基ネットを検索し、住所・氏名の変更を自動反映。
→2年以内の申請義務は残るが、実際には職権で変更される可能性が高い。 - 検索用情報の申出なし
→所有者が自ら申請しなければ住所変更はされない。
→義務違反となれば過料の可能性も。
このため、現在新しく登記する方や相続登記を行う方は、検索用情報の申出を併せて行うことが実務上の標準になりつつあります。
また、検索用情報が申出済みであっても、職権登記が行われるタイミングは住基ネットの情報更新状況に依存します。目安としては、住民票の異動後すぐ職権登記が行われるわけではなく、一定の処理期間を経たうえで登記簿に反映されます。このタイムラグも、制度を理解するうえでは重要なポイントです。
スマート変更登記の導入と司法書士のお仕事
スマート変更登記が始まることで、司法書士の実務も変化します。
特に「住所変更登記の減少」が直接的な影響ですが、その一方で新しい業務も生まれています。
減少する可能性のある業務
・引っ越し等による単純な住所変更登記
→従来は頻繁に依頼されていたが、スマート変更登記により自動化される部分が増える。
ただし「氏名の変更(婚姻・離婚)」については住基ネットと登記上の名義の一致確認が特に重要で、依然として専門家によるサポート需要は大きいです。
一方で増加する業務
・検索用情報の申出書作成
・対象不動産の整理、登記簿の洗い出し
・住基ネットに登録されていない人(例:法人、住民票を除いた人)への個別アドバイス
・相続登記時の検索用情報に関するアドバイス
特に、複数の不動産を所有する方、共有名義の物件が多い方、法人の場合などは、検索用情報の制度ではカバーしきれない部分が多いため、司法書士に相談される場面が確実に増えています。
検索用情報の制度は新しく、誤解されやすい部分も多くあります。
「申出したほうがよいのか」「自動で変更されるのか」「相続が絡む場合はどうなるのか」など、状況に応じた判断が必要です。
当事務所では、税理士と司法書士の資格を併せ持つ専門家が一体で対応し、登記・税務の両方の観点から最適なご提案をいたします。
不動産の名義管理に不安がある方は、どうぞお気軽にご相談ください。

司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。合わせて、複数の資格を活かして会社設立や税理士サービスなどで多方面からクライアント様に寄り添うサポートを行っている。