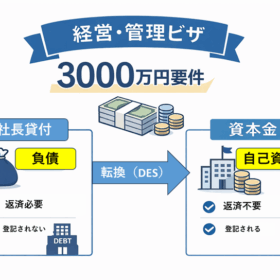Last Updated on 2025年10月24日 by 渋田貴正
日本で暮らす外国人や、海外に資産を持つ日本人が遺言を残す場合、どの国の法律に従うべきか――。この疑問に関係するのが、「遺言の方式に関する法律の抵触に関する条約(1961年10月5日採択、通称ハーグ条約)」です。
この条約は、遺言の「形式(方式)」に関する国際的なルールを定めたものです。遺言がどの国の形式要件を満たしていれば有効とみなされるかを明確にし、国をまたぐ相続手続きでも安心して遺言を作成できるようにすることを目的としています。
遺言の方式に関する法律の抵触に関する条約の基本的な仕組み
この条約では、遺言の形式が次のいずれかの法律に合致していれば有効とされています。
- 遺言を作成した国の法律(行為地法)
- 遺言者の国籍国の法律(作成時または死亡時)
- 遺言者の住所地または常居所地の法律(作成時または死亡時)
- 不動産に関する遺言の場合は、その不動産の所在地の法律
つまり、どれか一つでも条件を満たせば方式上「有効」と認められるという、柔軟な制度になっています。この複線的な基準があることで、国をまたぐ遺言でも無効となるリスクを大幅に下げることができます。
日本はこの条約の締約国であり、この条約に批准する流れで国内法として「遺言の方式の準拠法に関する法律」が制定されています。この法律により、外国人が日本で遺言を残す場合や、日本人が海外で遺言を作成する場合でも、上記のいずれかの法に適合していれば、日本でも方式上有効と扱われる可能性があります。
遺言の方式に関する法律の抵触に関する条約の批准国と非締約国の違い
遺言の方式に関する法律の抵触に関する条約に批准している国と、していない国では、遺言の方式上の扱いが異なります。以下に整理します。
| 観点 | 批准国(条約の締約国) | 非締約国 |
| 方式の有効性 | 条約第1条により、作成地・国籍国・住所地・常居所地・不動産所在地のいずれかに合致すれば有効。どれか一つでも満たせばOK。 | 条約の適用なし。自国法に従い、外国方式を認めるかどうかはその国の国内法次第。 |
| 日本で作成した遺言の他国での扱い | 他国が批准国であれば、上記のいずれかの法律に適合していれば方式上有効と扱われやすい。 | 批准していない国では、外国方式の遺言が有効かどうかはその国の裁判所の判断に委ねられる。 |
| 内容の適法性 | 条約は「形式(方式)」のみを対象。遺留分や公序良俗など、内容面は各国法に従う。 | 同様に内容面は各国法による。 |
| 不動産を含む場合 | 不動産所在地国の法律で作成していれば有効(条約で明確に認められている)。 | 所在地国の法律に従うことが原則。 |
| 実務上の予見可能性 | 高い。複数の準拠法が選べるため、無効リスクが小さい。 | 低い。外国方式が受け入れられるか不明確な場合が多い。 |
| 推奨される対応 | 日本法の方式で作成しつつ、資産所在地国の方式にも合致させる。 | 各国の国内法を個別に確認し、必要ならその国でも遺言を作成。 |
このように、批准国では「どれか一つでも方式が合えば有効」というセーフティネットが働きますが、非締約国では国内法次第のため、事前確認が不可欠です。
日本国籍・外国国籍、資産の所在による4パターン比較
国籍と資産の所在を掛け合わせた4パターンで、どの国の方式で遺言を残すべきかを整理します。
| ケース | 国籍 | 資産の所在 | 推奨される遺言方式 |
| ① | 日本国籍 | 日本国内資産 | 日本法方式で作成すれば十分。国内登記・税務にも適合。 |
| ② | 日本国籍 | 海外資産 | 日本法方式に加え、資産所在地国の方式でも作成しておくと確実。 |
| ③ | 外国国籍 | 日本国内資産 | 日本法方式を採用するのが安全。不動産の場合は所在地法(日本)で有効。 |
| ④ | 外国国籍 | 海外資産 | 国籍国または資産所在地国の方式を優先。日本で作成する場合は、その方式も整合させておくのが理想。 |
※不動産については、条約上「所在地国法」によって作成していれば方式的に有効です。したがって、どの国の国籍であっても、不動産がある国での方式を整えておくことが最も確実です。
条約で定められているのは、あくまで「方式」面
「批准国であれば、日本で作った遺言はその国でも有効になる」と理解されていますが、厳密には次のように整理されます。
批准国同士の間では、日本で作成した遺言であっても、条約で定められた方式のいずれか、たとえば作成地の法律や遺言者の本国法などの要件を満たしていれば、他国でも形式的に有効と認められます。
ただし、この条約はあくまで「形式」の有効性を保証するものであり、遺言の「内容」そのものまで有効とするわけではありません。たとえば、その国の強行法規――遺留分制度や公序良俗に関する規定――に反する内容を含んでいる場合には、たとえ条約に基づく形式を満たしていても無効と判断されることがあります。
また、条約の締約国でない国に対しては、このような形式の相互承認は及びません。したがって、非締約国においては、その国の国内法が外国方式の遺言をどの範囲まで認めるかにより、有効性が左右されます。
そのため、海外に資産を持っている場合や外国籍の関係者がいる場合には、関係する国が条約を批准しているかどうかをまず確認し、必要に応じて現地の法律に従った遺言を別途整えておくことが安全です。
税務・登記の実務上の影響
条約は「遺言の方式」を扱うものですが、実務上は税務や登記の流れにも関わります。
- 税務面:日本国内に資産を持つ外国人の遺言に基づく相続では、日本の相続税法が適用される可能性があります。方式が整っていれば、相続税申告を円滑に行うことができます。
- 登記面:日本の不動産登記では、遺言の方式が明確であれば名義変更(相続登記)をスムーズに行えます。逆に、方式の不備があると、登記官が受理を保留するケースもあります。
国際的な遺言は、単に書面を整えるだけでなく、税務申告・登記・金融機関対応など多面的な実務を見据えておく必要があります。
国際的な遺言では、形式上の有効性に加えて、各国の相続税や登記制度との整合も求められます。条約を理解していても、実際の手続きには細かな要件や証明書類が関わるため、専門家による事前確認が不可欠です。
当事務所では、税理士・司法書士の双方の立場から、
- 国際的な遺言書の作成支援
- 各国法との整合性チェック
- 相続税・登記の一体的対応
をワンストップでサポートしています。
海外資産や外国籍をお持ちの方、またはご家族に外国籍の方がいる場合は、ぜひ一度ご相談ください。方式・税務・登記をすべて見据えた最適なアドバイスをご提供いたします。
補足 締約国(批准国)一覧
以下は、1961年「遺言の方式に関する法律の抵触に関する条約(HCCH 1961 Form of Wills)」の全42か国の締約国リストを、日本語訳付きでわかりやすく整理した表です。(2025年10月現在)
| No. | 国名(英語) | 国名(日本語) | 型式 | 効力発生日(EIF) |
| 1 | Albania | アルバニア | A(加入) | 2013-12-24 |
| 2 | Antigua and Barbuda | アンティグア・バーブーダ | Su(継承) | 1985-05-01 |
| 3 | Armenia | アルメニア | A(加入) | 2007-04-30 |
| 4 | Australia | オーストラリア | A(加入) | 1986-11-21 |
| 5 | Austria | オーストリア | R(批准) | 1964-01-05 |
| 6 | Belgium | ベルギー | R(批准) | 1971-12-19 |
| 7 | Bosnia and Herzegovina | ボスニア・ヘルツェゴビナ | Su(継承) | 1992-03-06 |
| 8 | Botswana | ボツワナ | A(加入) | 1969-01-17 |
| 9 | Brunei Darussalam | ブルネイ・ダルサラーム | A(加入) | 1988-07-09 |
| 10 | Denmark | デンマーク | R(批准) | 1976-09-19 |
| 11 | Estonia | エストニア | A(加入) | 1998-07-12 |
| 12 | Eswatini | エスワティニ(旧スワジランド) | A(加入) | 1971-01-22 |
| 13 | Fiji | フィジー | Su(継承) | 1970-10-10 |
| 14 | Finland | フィンランド | R(批准) | 1976-08-23 |
| 15 | France | フランス | R(批准) | 1967-11-19 |
| 16 | Germany | ドイツ | R(批准) | 1966-01-01 |
| 17 | Greece | ギリシャ | R(批准) | 1983-08-02 |
| 18 | Grenada | グレナダ | Su(継承) | 1974-02-07 |
| 19 | Ireland | アイルランド | A(加入) | 1967-10-02 |
| 20 | Israel | イスラエル | A(加入) | 1978-01-10 |
| 21 | Italy | イタリア | R(批准) | (表記なし) |
| 22 | Japan | 日本 | R(批准) | 1964-08-02 |
| 23 | Lesotho | レソト | Su(継承) | 1966-10-04 |
| 24 | Luxembourg | ルクセンブルク | R(批准) | 1979-02-05 |
| 25 | Mauritius | モーリシャス | Su(継承) | 1968-03-12 |
| 26 | Montenegro | モンテネグロ | Su(継承) | 2006-06-03 |
| 27 | Netherlands | オランダ | R(批准) | 1982-08-01 |
| 28 | North Macedonia | 北マケドニア | Su(継承) | 1991-11-17 |
| 29 | Norway | ノルウェー | R(批准) | 1973-01-01 |
| 30 | Poland | ポーランド | A(加入) | 1969-11-02 |
| 31 | Portugal | ポルトガル | R(批准) | (表記なし) |
| 32 | Republic of Moldova | モルドバ共和国 | A(加入) | 2011-10-10 |
| 33 | Serbia | セルビア | Su(継承) | 1992-04-27 |
| 34 | Slovenia | スロベニア | Su(継承) | 1991-06-25 |
| 35 | South Africa | 南アフリカ共和国 | A(加入) | 1970-12-04 |
| 36 | Spain | スペイン | R(批准) | 1988-06-10 |
| 37 | Sweden | スウェーデン | R(批准) | 1976-09-07 |
| 38 | Switzerland | スイス | R(批准) | 1971-10-17 |
| 39 | Tonga | トンガ | Su(継承) | 1970-06-04 |
| 40 | Türkiye | トルコ | A(加入) | 1983-10-22 |
| 41 | Ukraine | ウクライナ | A(加入) | 2011-05-14 |
| 42 | United Kingdom | イギリス(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国) | R(批准) | 1964-01-05 |
この表の見方
- R(批准):条約を正式に批准した国。
- A(加入):締約国ではなかったが、後から参加した国。
- Su(継承):旧宗主国等からの独立時に条約効力を引き継いだ国。
- EIF(効力発生日):その国において条約が発効した日付。
補足:
- 日本は1964年8月2日に発効しており、アジアでは比較的早期に加入した国のひとつです。
- 欧州諸国を中心に批准国が多く、北欧・中欧・地中海沿岸諸国が広く加盟しています。
- 一方で、アメリカ合衆国、中国、韓国、カナダなどは現時点で締約国ではありません。
この条約は「形式(方式)」のみを対象としており、内容(遺留分、公序良俗など)は各国の国内法に委ねられています。
国際相続や外国人の遺言作成を検討する際には、関係国がこの条約の締約国か否かをまず確認することが重要です。

司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。合わせて、複数の資格を活かして会社設立や税理士サービスなどで多方面からクライアント様に寄り添うサポートを行っている。