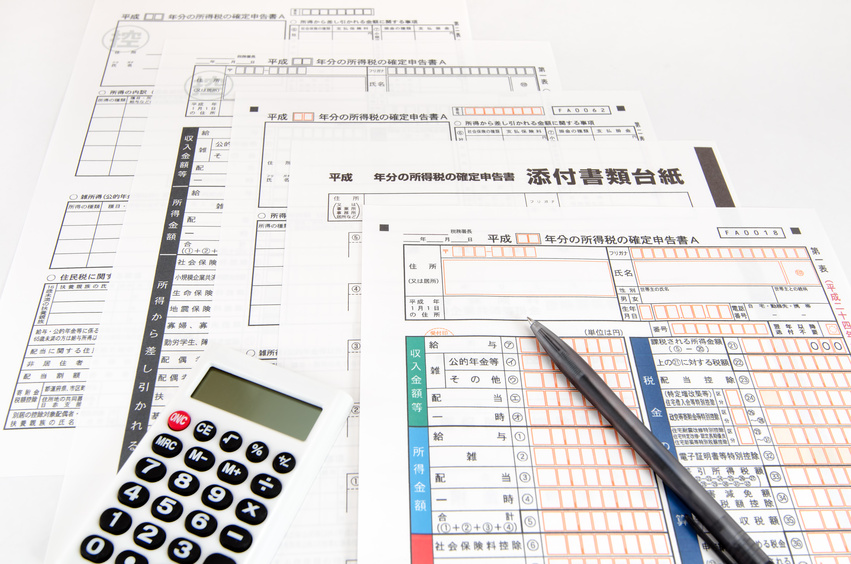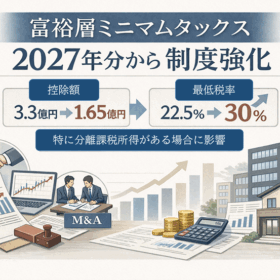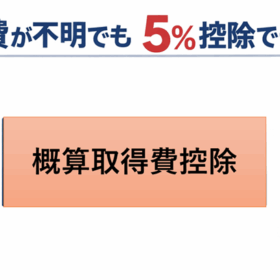Last Updated on 2025年10月15日 by 渋田貴正
同族会社や一人会社では、代表者や役員が個人資金を会社に貸し付けるケースは非常によくあります。とくに創業初期や資金繰りが不安定な時期には、社長が自分の財布から会社を支えることは珍しくありません。こうした貸付は、元々の動機が資金繰りの改善ということもあり、無利息で行われることも多く、実務では「とりあえず会社にお金を入れておく」という感覚で処理されていることも少なくありません。
しかし、貸付金に利息を設定し、その利息を役員個人が受け取るようにすると、所得税・法人税の課税関係や相続時の評価など、複数の税務論点が発生します。正しく処理を行わないと、後から税務調査で否認される可能性もあるため注意が必要です。以下では、実務上押さえておきたい基本的なポイントをわかりやすく解説します。
役員貸付と利息支払いの基本
会社の資金が不足した際、代表取締役や役員が会社にお金を貸すことを「役員貸付」といいます。会社から見れば借入金(負債)です。これは、会社と個人の間で交わされる通常の金銭消費貸借契約と同じ扱いになります。会社は借りたお金を返済する義務があり、利息を設定して支払うことも可能です。
中小企業では、こうした貸付は無利息で行われるのがむしろ一般的です。会社が軌道に乗るまでは、利息を設定せずに資金を融通するケースが多く見られます。一方で、会社の資金繰りが安定してきた段階で、「役員報酬をこれ以上増やすと所得税や社会保険料の負担が大きくなる」「給与以外の形で資金を回収したい」といった理由から、利息を設定して会社から支払いを受けるケースもあります。
しかし、役員報酬にしても役員への利息にしても役員が会社から利益を移転してもらっていることには変わりなく、そこには役員本人への課税が発生することをしっかりと認識しておく必要があります。
会社から利息を受け取ったときの役員個人の課税関係と確定申告義務
会社から役員に支払われる利息は、所得税法上は「利子所得」ではなく「雑所得」に区分されます。銀行預金の利息のように20.42%が源泉徴収され、申告不要となる「利子所得」とは異なる扱いです。そのため、会社が利息を支払う際に源泉徴収を行う必要はありません。
一方で、役員個人は、受け取った利息を雑所得として翌年の確定申告で申告する必要があります。ここで注意したいのが、同族会社の役員が会社から受け取る利息については、たとえ少額であっても申告義務が生じるとされている点です。一般的な雑所得では「年間20万円以下であれば申告不要」というルールがありますが、同族会社との取引の場合は、この特例の適用対象外となります。こうした利息や同族会社からの賃料収入などは金額に関わらず申告が必要になるという点は、実務上とても重要な注意点です。
また、雑所得として計上する際には必要経費の控除も可能ですが、役員貸付の場合は特別な経費が発生しないことが多く、そのまま全額が課税対象になるのが通常です。
役員に利息を払ったときの会社側の税務上の処理と注意点
会社が役員に利息を支払った場合、その利息は法人税法上「支払利息」として損金(経費)に算入することができます。これにより、会社の課税所得を減らす効果が得られます。ただし、損金算入が認められるためには、利率が適正であることが必要です。
国税庁は、役員に対する貸付や借入について「認定利息」の考え方を示しています。会社が支払っている利率が市場水準を大きく上回っている場合には、超過部分が損金不算入とされ、役員賞与とみなされるリスクがあります。逆に、無利息や極端な低利で貸付を行っていると、役員側に経済的利益が生じたとみなされ、給与課税の対象になることもあります。いわば、損金には入れられないけど所得税は課税されるというダブルパンチ状態です。
たとえば、社長に対してまったく利息を付さずに貸付を行っていた場合、税務署が「会社から役員に利益が移転した」と判断し、給与として課税されることがあるのです。実務上は、市場金利や金融機関の短期貸出金利などを参考に、適正な利率を設定することが重要です。
会社から利息を受け取ったときの相続の注意点
役員貸付金は、役員が亡くなった際には「貸付金債権」として相続財産に含まれる点にも注意が必要です。たとえば、社長が会社に1,000万円を貸し付けたまま亡くなった場合、その1,000万円は相続税の計算上、相続財産として評価され、相続税の課税対象となります。
また、利息が未収のままになっている場合には、その未収利息部分も相続財産に含まれる可能性があります。相続人が相続放棄をした場合は、その債権は相続財産から外れますが、誰も相続しなければ会社側では貸倒れ処理を行う必要が生じる場合があります。
一方、将来的な相続を見据えて、役員貸付金を株式に振り替える(いわゆる「債権→株式」=DES)など、相続税対策を検討するケースもあります。ただし、この場合は会社法上の手続や税務上の留意点が多く、慎重な検討が必要です。
役員貸付と利息支払いを適正に処理するためには、以下のような点をチェックしておくと安心です。
| チェック項目 | 内容 |
| 契約書の作成 | 貸付契約書(利率・返済条件・期日など)を明確に定める |
| 利率の設定 | 市場金利を参考に、過大・過少にならないよう注意 |
| 帳簿処理 | 利息支払・受取を正しく会計処理し、証憑を残す |
| 申告義務 | 役員側は雑所得として金額にかかわらず申告する必要あり |
| 認定利息 | 税務署が認定利率を適用して課税するリスクに注意 |
| 相続対策 | 将来の相続税評価や貸倒れリスクも踏まえた対応を検討する |
同族会社・一人会社での役員貸付と利息の支払いは、単なる資金移動に見えて、所得税・法人税・相続税といった複数の税務分野が絡み合うテーマです。金額が小さいからといって油断すると、確定申告漏れや認定課税、相続時のトラブルなど、思わぬリスクにつながることがあります。
弊所では、税務と登記の両面から、役員貸付や利息設定に関する適正な手続きをサポートしています。契約書の整備や税務処理、将来の相続を見据えた対策まで、一貫したサポートが可能です。ご不安のある方は、ぜひ一度ご相談ください。

司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。合わせて、複数の資格を活かして会社設立や税理士サービスなどで多方面からクライアント様に寄り添うサポートを行っている。