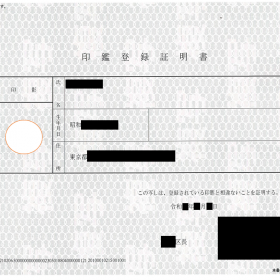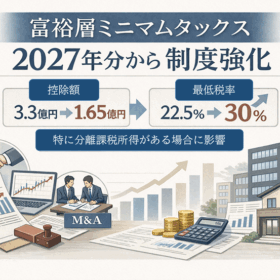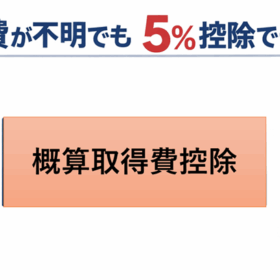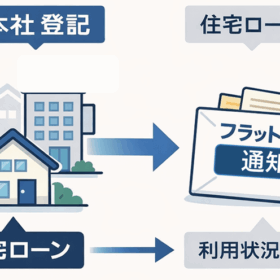Last Updated on 2025年8月28日 by 渋田貴正
法人に遺贈できるのか?基礎知識
「遺贈」という言葉は、遺言によって財産を特定の人や団体に譲ることを指します。相続は相続人が対象となりますが、遺贈は相続人以外の者にも財産を渡すことができます。
ここで気になるのが「法人への遺贈はできるのか」という点です。
結論からいうと、法人への遺贈は可能です。民法965条では、受遺者(遺贈を受ける者)は「権利能力を有する者」であれば足りるとされています。権利能力を持つのは自然人だけでなく法人も含まれるため、株式会社や合同会社、一般社団法人、公益法人などにも遺贈は認められます。さらに、法人格を持たない社団・財団であっても一定の要件を満たせば有効とされています。
以下の表に、遺贈の対象となる代表的なパターンをまとめました。
| 遺贈の対象 | 遺贈の可否 | 備考 |
| 個人(相続人以外の友人など) | 可能 | 一般的な遺贈 |
| 株式会社・合同会社 | 可能 | 贈与による登記手続きが必要 |
| 一般社団法人・公益法人 | 可能 | 事業目的に合致するか確認 |
| 法人格のない社団・財団 | 可能 | 権利能力なき社団でも有効 |
| 胎児 | 可能 | 相続の場合と同様、すでに生まれたものとみなされる |
法人への遺贈手続きの流れ
法人に遺贈する場合、相続人に遺産が自動的に承継される「相続」とは異なる手続きが必要となります。具体的な流れを見てみましょう。
遺言の作成
法人に財産を遺贈するには、遺言書を作成して明確に記載する必要があります。たとえば「私の所有する不動産をA株式会社に遺贈する」と具体的に記しておきます。公正証書遺言にしておくことで後日の争いを防ぎやすくなります。
遺言執行者の選任
遺贈の実行には「遺言執行者」が重要な役割を果たします。遺言執行者は遺贈義務者として、不動産の登記や財産の引渡しを行います。遺言書に指定しておけばスムーズです。
不動産の場合は遺贈による登記
遺贈の対象が不動産である場合には、不動産登記簿の名義変更が必要です。遺贈義務者は、相続開始時点の状態で受遺者(法人)に財産を移転する義務があります(民法998条)。司法書士が代理して登記を行うのが一般的です。
法人税申告
法人が遺贈を受けた場合、相続税は課されません。その代わり法人税の課税対象となり、受け取った財産は「受贈益」として法人の益金に算入されますので、法人税申告の時に反映が必要です。
法人が遺贈を受けた場合の税務上の扱い
ここで注意すべきは、税務上の取扱いです。個人が遺贈を受けた場合には相続税の対象となりますが、法人が遺贈を受けた場合には相続税法ではなく法人税法の規定が適用されます。
法人に帰属した財産は「受贈益」として益金に算入され、法人税が課税されます。つまり、法人にとっては遺贈財産は「収益」として扱われるのです。
たとえば、不動産評価額3,000万円の土地を法人が遺贈により取得した場合、その3,000万円は法人の利益に計上され、法人税の課税対象となります。これにより、実際に遺贈によって法人が得られる経済的メリットは、相続人が個人で受けて相続税で申告する場合と比べて税負担が重くなるケースがあります。
(借方)土地 30,000,000 /(貸方)受贈益 30,000,000
法人への遺贈のメリットと注意点
法人に遺贈するメリットは、遺言者が「自分の築いた財産を会社や団体に役立ててほしい」という意思を明確に実現できる点です。特に自分が設立した会社に財産を遺贈すれば、会社の安定的な経営に資することができます。公益法人やNPO法人に遺贈することで、社会貢献にもつながります。
一方で注意点もあります。
- 法人税の課税:法人は受け取った財産について受贈益として課税される。
- 登記費用・登録免許税:不動産を法人に遺贈する場合には、相続登記に比べて多くの登録免許税が課されます。
| メリット | 注意点 |
| 財産を法人に役立てられる | 法人税が課税される |
| 社会貢献につながる | 登記費用や登録免許税の負担 |
| 経営の安定化に貢献 | 定款や目的に合致しているか要確認 |
法人への遺贈にかかる費用と期間
登記費用
不動産を法人に遺贈する場合、登録免許税は固定資産評価額の2%となります。たとえば評価額3,000万円の土地を遺贈する場合、登録免許税だけで60万円の負担が発生します。司法書士報酬も加わりますので、事前に見積りを取っておくことが大切です。
遺贈の手続きのための期間
遺贈の登記は相続開始から速やかに行うのが望ましいですが、実務上は数週間から数か月程度を要することが一般的です。遺言の内容確認、遺言執行者の就任、登記申請書類の準備など複数の手続きが必要だからです。
具体的な事例
事例1:自分の会社に土地を遺贈するケース
Aさんは、生前に自分が設立した会社(A株式会社)の経営を支えてきました。亡くなった後も会社の発展に役立ててほしいとの思いから、所有していた土地(固定資産評価額5,000万円)をA株式会社に遺贈する旨の遺言を残しました。
この場合、会社は遺言に基づいて土地を取得します。
仕訳は次のようになります。
(借方)土地 50,000,000 /(貸方)受贈益 50,000,000
税務上は、受贈益として5,000万円が益金に算入され、法人税の対象となります。さらに、不動産登記の名義変更には登録免許税(評価額の2%=100万円)が必要になります。
司法書士が名義変更登記を行い、会社は税理士を通じて法人税申告に反映させる流れとなります。
事例2:公益法人に寄付の趣旨で遺贈するケース
Bさんは社会貢献を望み、遺言で「私の金融資産2,000万円を公益財団法人Cに遺贈する」と記載しました。
公益法人が遺贈を受けた場合も、法人税法上は「受贈益」として課税対象となります。ただし、公益法人等の場合には、事業目的に沿った活動に充てられる寄附金について法人税が非課税となる特例があります。この場合、C財団は非課税措置の適用を受けられる可能性があります。
仕訳の例は次のとおりです。
(借方)現金預金 20,000,000 /(貸方)受贈益 20,000,000
その後、非課税対象として処理されるかどうかは、公益法人の活動内容や寄附金の使途により判断されます。
法人への遺贈は法律的にも認められており、実際に行うことができます。しかし、税務上は法人税の課税対象となる点や、登記・費用の負担などに注意が必要です。当事務所では、遺言書作成から登記、法人の税務申告まで一貫してサポートしております。法人への遺贈を検討されている方は、ぜひお気軽にご相談ください。

司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。合わせて、複数の資格を活かして会社設立や税理士サービスなどで多方面からクライアント様に寄り添うサポートを行っている。