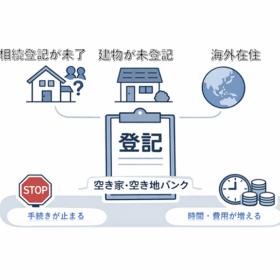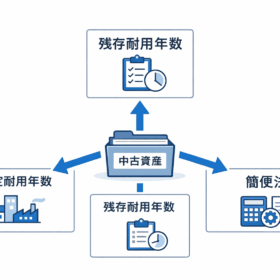Last Updated on 2025年7月20日 by 渋田貴正
国際相続では、海外にある不動産や預金口座などの財産を整理する必要があり、そのために現地の弁護士と連携を取る場面が少なくありません。しかし、異なる言語・法制度・報酬体系のもとで手続きを進めるのは容易ではなく、想定外のトラブルや費用が発生することもあります。
そこで本記事では、国際相続において海外の弁護士に依頼する際の注意点や、依頼先の選び方、費用対効果の見極め方について、実務経験に基づいた視点でわかりやすく解説します。
現地弁護士とやり取りする際の心構え
外国の専門家に相続手続を依頼する場合は、事前に質問の内容を整理し、できるだけ明確かつ具体的に伝えることが重要です。たとえば、「この書類で手続できますか?」といった曖昧な聞き方ではなく、「この戸籍謄本とその英訳に、アポスティーユを付したもので、裁判所の認定が得られますか?」といった、YesかNoで答えられるような聞き方が理想です。
また、質問に先立って、相続の背景や日本の法制度についても簡潔に説明する必要があります。同じ法律用語であっても、国によって意味や運用が異なるため、前提を共有せずに話を進めてしまうと、誤解や手続ミスを招く恐れがあります。
もちろん現地の言葉(または対応していれば英語など)でやり取りできることも必要です。
相続に関する法制度の違いに注意
相続に関する制度は国ごとに大きく異なります。たとえば、日本では民法上「遺留分」や「特別縁故者」などの制度がありますが、これらが存在しない国もあります。また、誰が相続人となるか、配偶者や兄弟姉妹の権利がどう扱われるかといった点も、各国の法律によって異なります。
これらの違いを理解せずに「日本ではこうだから」と進めてしまうと、手続が滞ったり、現地で無効とされるリスクもあります。国際相続では、常に「その国では何が通用し、何が通用しないのか」を冷静に見極める必要があります。
海外の弁護士費用とタイムチャージ制
日本では、相続に関する報酬体系として、着手金+成功報酬制や、遺産総額に応じた定額報酬制が一般的です。しかし、海外の弁護士の多くは「タイムチャージ制」を採用しています。これは「1時間〇〇ドル」といった形で、作業時間に応じて料金が発生する仕組みです。
このため、漠然とした質問や、頻繁なやり取りを続けてしまうと、想定以上の費用が発生するおそれがあります。実際に、簡単な手続に見えても、法制度の確認や裁判所との調整、書類の翻訳などで多くの時間がかかるケースも少なくありません。
費用対効果を考え、どこまでの手続きを行うのか、あらかじめ方向性を定めておくことが肝要です。
日本の専門家を通じて依頼すべき理由
国際相続が発生して、海外の弁護士などに依頼が必要となった場合、海外の弁護士に直接依頼するのではなく、日本の専門家を通じて手続きを進めることで、以下のようなメリットがあります。
| 比較項目 | 海外弁護士に直接依頼 | 日本の専門家を通じて依頼 |
| 言語対応 | 通訳が必要 | 日本語で対応可能 |
| 制度理解 | 依頼者が調査必要 | 日本法と現地法を比較説明 |
| 質問の整理 | 自力で行う必要あり | 専門家が要点を抽出 |
| コスト管理 | 費用が不透明 | 必要な範囲で調整可能 |
日本の専門家に依頼することで、制度の違いや文化的な背景を踏まえたうえで適切な進め方を提案してもらえます。また、重要でない手続に過剰なコストをかけるリスクも避けられます。
手続の取捨選択も時には必要
国際相続では、「すべての財産を相続することが得かどうか」を冷静に判断する必要があります。仮に相続財産が少額であっても、現地の裁判所手続や翻訳費用、弁護士費用がかさむと、費用倒れになる可能性もあります。
たとえば、相続する財産が10万円程度であっても、翻訳や書類認証、弁護士とのやり取りで30万円以上かかってしまうこともあります。このような場合には、あえて相続を断念する判断も、依頼者の利益を守るためには必要です。
当事務所では、海外に財産を有する方の相続手続を、法務・税務の両面からサポートしております。現地弁護士との連携や費用対効果を含めたご提案が可能です。国際相続でお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。

司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。合わせて、複数の資格を活かして会社設立や税理士サービスなどで多方面からクライアント様に寄り添うサポートを行っている。