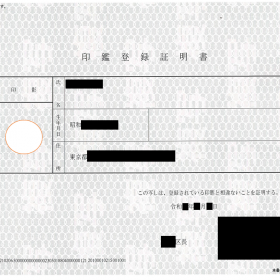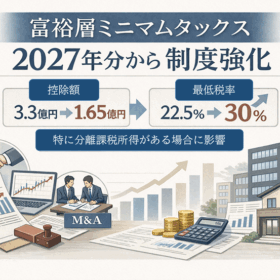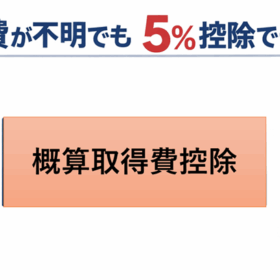Last Updated on 2025年10月12日 by 渋田貴正
中国の土地使用権の相続
中国籍の人だけでなく、日本人が中国にある不動産を相続する場合、日本国内での相続税の申告対象になります。その際に重要となるのが、中国特有の「土地使用権」という制度の理解と、相続税の評価方法です。
中国の土地制度は日本と大きく異なり、土地自体を所有することはできません。そのため、中国の不動産相続については、土地使用権の理解が必要です。日本の相続税評価の実務上の取扱いについて解説します。
中国の土地使用権とは
中国の土地使用権の相続
中国では土地は国家所有とされ、個人や企業は土地そのものを所有することはできません。代わりに、土地を一定期間利用する権利として「土地使用権」が設定されています。土地使用権は売買・相続の対象となり、建物の所有権と一体で扱われます。
主な特徴は次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
| 所有者 | 国家(個人の土地所有は不可) |
| 権利の内容 | 土地を一定期間使用する権利 |
| 使用期間 | 用途により異なる(住宅用70年、工業用50年など) |
| 建物との関係 | 土地使用権と建物は常に一体で扱われる |
| 相続の可否 | 外国人による相続も可能(現地で名義変更手続が必要) |
このように、日本の所有権とは根本的に異なる制度であるため、相続税評価でも「土地使用権+建物」という複合的な資産として捉える必要があります。
これだけ聞くと、なんだか日本の敷地権付きのマンションに似ている気がしますが、以下のような違いがあります。
| 日本(マンション+敷地権) | 中国(土地使用権+建物) | |
|---|---|---|
| 土地の権利形態 | 所有権または借地権を敷地権として取得 | 国家所有で、個人は土地使用権を一定期間保有 |
| 建物 | 区分所有法に基づき個人所有 | 個人・法人が所有可能 |
| 土地と建物の関係 | 一体不可分(敷地権と専有部分は分離処分不可) | 制度上不可分(売買・相続・譲渡も一括) |
| 権利の期間 | 所有権は永久/借地権は契約による | 使用期間に上限あり(住宅用70年など) |
| 評価の前提 | 路線価・借地権割合など国内制度に基づく | 資産評価師の評価や公示価格など現地制度に基づく |
| 相続税評価 | 日本の評価通達に基づき、土地・建物それぞれ評価 | 土地使用権と建物を一体の資産として精通者意見価額で評価 |
中国の土地使用権は日本の相続税の対象になるか
中国に所在する土地使用権と建物は、被相続人が日本の居住者であれば、相続税の課税対象に含まれます。
相続税法上、日本の居住者が死亡した場合には、国内・国外を問わずすべての財産が課税対象になるためです(いわゆる「無制限納税義務者」)。
また、相続人が居住者である場合も、国外財産は申告対象となります。つまり、中国の土地使用権を相続した場合、日本国内での相続税申告にあたり、当該土地使用権と建物の評価額を日本円に換算して申告書に記載する必要があります。
中国の土地使用権の評価の基本的な考え方
日本の相続税法に基づく財産評価は、国内不動産であれば路線価方式や固定資産税評価額をもとに行いますが、国外不動産には路線価制度がありません。そのため、財産評価基本通達では、国外財産の評価について「精通者意見価額」を用いる方法が認められています。
精通者意見価額とは、その国の不動産事情に精通した専門家が評価した金額をもとにする方法です。中国の場合、この評価を行えるのが「資産評価師(Asset Appraiser)」という国家資格者です。
資産評価師は、中国で不動産や企業などの資産評価を行うことが認められた国家資格者で、日本の不動産鑑定士に近い存在です。
土地使用権と建物について資産評価師に依頼すると、評価調書や評価証明書を発行してもらうことができます。この証明書は、日本の税務上も「精通者意見価額」として利用できるため、相続税評価額として採用するのが最も実務的で確実な方法です。
評価を依頼する際は、不動産の登記情報、位置図、建物の資料などが必要になります。また、評価証明書は中国語で作成されるため、日本の税務署に提出する際には日本語訳を添付します。
一部の地域では、地方政府が土地の売買実例価格や公示価格を公表しています。この価格情報をもとに評価額を算定する方法もあります。特に都市部では取引事例が豊富なため、資産評価師による評価証明書の代替または補完として活用できるケースがあります。
ただし、日本の税務上は算定根拠の明示が求められるため、出典や計算方法を明確に記載した資料を残すことが重要です。例えば、現地政府の公式サイトから公示価格の資料を取得し、それを基に合理的に評価額を算定するという手順が考えられます。
| 評価方法 | 内容 | メリット | デメリット |
| 資産評価師による評価 | 国家資格者が評価証明書を発行 | 税務上の信頼性が高く、実務で最も有効 | 評価費用・依頼手続が必要 |
| 公示価格・売買実例 | 地方政府の価格情報を参考に評価 | コストを抑えられる/簡便 | 対応地域が限られる/根拠資料が不可欠 |
換評価額が算定できたら、日本円に換算して相続税申告書に記載します。換算には、被相続人の死亡日または相続開始日における為替相場(TTM)を用いるのが一般的です。
また、国外財産の場合、日本の税務署に対して評価の根拠資料を求められることがあります。資産評価師の証明書、公示価格の出典、計算過程の明示など、評価の裏付けとなる資料をしっかり整えておくことが大切です。
中国の土地使用権と建物の評価は、日本の相続税制度にそのまま当てはめることができないため、現地制度と日本の評価通達の両方に精通した対応が必要です。当事務所では、中国を含む海外不動産の相続税評価や申告にも対応しております。現地専門家との連携も可能ですので、日本にお住まいで中国の不動産を相続された方は、ぜひご相談ください。

司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。合わせて、複数の資格を活かして会社設立や税理士サービスなどで多方面からクライアント様に寄り添うサポートを行っている。