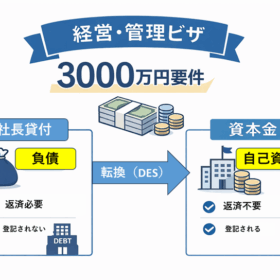Last Updated on 2025年11月18日 by 渋田貴正
インド国籍の方が日本に不動産や預金などの資産を持っていた場合、その相続手続きは非常に複雑になります。なぜなら、インドは「人的不統一法国」と呼ばれ、被相続人の宗教ごとに異なる相続法が存在するからです。日本で相続登記や相続税申告を進める際にも、どのインド法を根拠に相続人を確定すべきかを明らかにしなければなりません。
ここでは、日本に資産を持つインド国籍者の相続に焦点を当て、準拠法、登記、税務の観点からわかりやすく解説します。
インド相続の準拠法と日本法の関係
通則法による準拠法の決定
日本の国際私法では、相続の準拠法は「被相続人の本国法」とされています。
| 法の適用に関する通則法 (相続) 第36条 相続は、被相続人の本国法による。 |
つまり、インド国籍の方が亡くなった場合は、インドの相続法が適用されるのが原則です。
ところがインドなど人の属性によって適用される法律が異なる国、いわゆる「人的不統一法国」では話はそう単純ではありません。インドでは宗教ごとに異なる法律があるため、まず被相続人がヒンドゥー教徒なのか、イスラム教徒なのか、あるいは別の宗教なのかを確認する必要があります。
宗教ごとの相続法の概要
日本での実務に直結するよう、宗教別の相続法を整理します。
| 被相続人の宗教 | 適用される法律 | 主な特徴 |
| ヒンドゥー教徒 | ヒンドゥー相続法(Hindu Succession Act, 1956/2005改正) | 娘も息子と同等の相続権。改正前は父系優先だったが大きく是正。 |
| イスラム教徒 | イスラム法(シャリーア)に基づく相続規定 | 男女で相続分が異なる。遺言は全財産の1/3まで有効。 |
| キリスト教徒・ゾロアスター教徒など | インド相続法1925年(Indian Succession Act) | 不動産は所在地法、動産は住所地法に従う。非ヒンドゥー・非イスラムに広く適用。 |
このように宗教によって相続分や遺言の効力が大きく変わるため、日本の相続登記や税務に進む前提として「どのインド法が適用されるか」を確認することが最優先となります。
外務省のページによれば、ヒンドゥー教徒79.8%、イスラム教徒14.2%、キリスト教徒2.3%、シク教徒1.7%、仏教徒0.7%、ジャイナ教徒0.4%(2011年国勢調査)となっていますので、ほとんどのケースではヒンドゥー相続法が適用されると考えられます。
インド国籍の被相続人について日本での登記手続きへの影響
相続登記の基本
日本に不動産を持つインド国籍者が亡くなった場合、相続人は日本の法務局で相続登記を行う必要があります。
その際に問題となるのが「相続人を誰とするか」の証明です。
必要となる書類
これらの書類をインドから取り寄せ、日本語に翻訳して提出する必要があります。現地の公証制度や認証の違いから、準備に数か月を要することも珍しくありません。
ただし、法律上で不動産の相続については不動産の所在地の国の法律に従うとなっていれば、相続人の範囲も日本の民法に従います。
インド国籍の被相続人について日本の相続税への影響
課税対象
被相続人が日本に不動産を所有していた場合、その財産は日本の相続税の課税対象になります。たとえ被相続人や相続人がインドに居住していても、日本国内財産については課税されます。
二重課税のリスク
インドでも相続に関する税務上の規定がありますが、日本とインドの間には相続税に関する租税条約が存在しないため、二重課税のリスクがあります。この場合、外国税額控除を利用して調整を図る必要があります。
実務で想定される流れ
日本に不動産を持つインド国籍者の相続では、以下のような流れになります。
- 被相続人の宗教を確認し、適用されるインド法を特定
- インド国内で相続人を確定する証明書類を取得
- 日本語翻訳と認証を受け、登記書類として法務局に提出
- 日本での相続税申告を行い、必要に応じて外国税額控除を検討
このプロセスには法律と税務の両面からの調整が不可欠です。
インドの相続法体系は宗教によって異なるため、日本で相続登記や相続税の手続きを行うには高度な専門知識が必要です。相続人自身で全てを進めるのは非常に難しく、現地専門家との連携、日本での登記・税務手続きを同時に進める体制が求められます。
当事務所では、インド籍の方が関係する国際相続案件についても、登記と税務をワンストップで対応しております。日本に資産をお持ちのご家族の相続でお困りの際は、ぜひご相談ください。

司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。合わせて、複数の資格を活かして会社設立や税理士サービスなどで多方面からクライアント様に寄り添うサポートを行っている。