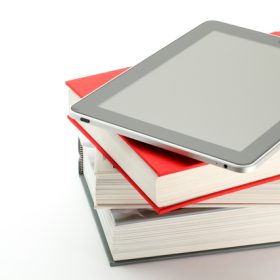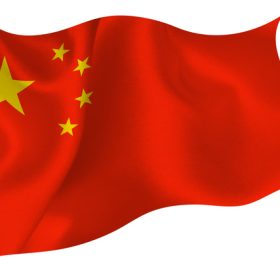Last Updated on 2025年7月9日 by 渋田貴正
外国会社が日本で事業を行っている場合、法務局に「外国会社」の登記を行い、その際に「日本における代表者」を定めておく必要があります。特にこの代表者が日本に住所を有している場合、その人物は外国会社にとって日本国内での窓口となる重要な存在です。では、この日本における代表者が退任する場合、どのような手続きが必要なのでしょうか?単に登記を抹消するだけでは済まないという点に注意が必要です。
日本に住所を有する代表者が退任する場合の法的手続
外国会社の日本における代表者が全員退任しようとする場合には、以下のような「債権者異議手続」を踏む必要があります。
| 手続き | 内容 |
| 官報公告 | 「代表者が退任するので、債権者は1か月以上の期間内に異議があれば申し出てください」との内容を官報に公告します(会社法820条1項)。 |
| 個別催告 | 公告とは別に、外国会社が「知れている債権者」には個別に催告を行う必要があります。 |
| 異議が出た場合 | 債権者に対し、①弁済、②担保の提供、③信託会社への信託などの対応が求められます(同条2項)。 |
| 登記 | 上記手続きを完了した後でなければ、退任の登記はできず、法的効力も発生しません(同条3項)。 |
「知れている債権者」とは?
実務上問題となるのが、「知れている債権者」の範囲です。これは、単に債権者であるというだけでなく、その債権の存在や内容を会社側が具体的に把握している債権者を指します。請求書のやりとりがあった取引先や、未払金がある業者などが典型です。
一方で、少額で取引履歴も古く、現在では連絡先も不明という場合でも、催告が漏れていたと後で争いになるリスクがあるため、事前に取引履歴を洗い出す作業が重要です。
債権者異議手続が不要なケースとは?
会社法820条では、一定のケースに限り、債権者異議手続きを省略することが可能です。それは「債権者を害するおそれがないとき」です。
たとえば、次のような場合が考えられます。
- 代表者の退任と同時に新たな代表者(日本に住所を有する者)が選任されている
- 当該外国会社が信用力のある世界的な企業であり、弁済能力が明らかである
- 債権に対して既に担保が提供されている
こうした場合には、債権者の保護に実質的な影響がないと認められるため、公告や催告を行わなくても退任登記が可能とされます。
「全員退任」の意味と実務上の注意点
この手続きが必要となるのは、「日本に住所を有する日本における代表者が全員退任する場合」に限られます。代表者が複数いる場合に一部のみが退任するケースでは、債権者異議手続は不要です。
また、退任ではなく「国外転居」によって日本に住所を有しなくなった場合でも、実質的には「退任」と同様の扱いになるため注意が必要です。
法的には、手続を踏まずに退任登記をすることはできませんし、勝手に代表者を退任した場合には、最大で100万円の過料(会社法976条26号)が科される可能性があります。
また、未登記のまま外国会社が日本から撤退した場合には、債権者は訴訟や強制執行を行うために外国での手続きを強いられるなど、大きな不利益を受けることになります。
外国会社の日本支店の営業譲渡と税務上の論点
外国会社が日本支店を閉鎖する一環として、支店の資産(建物・備品・営業権など)を第三者に譲渡するケースもあります。この場合、課税関係についても整理が必要です。
| 資産の種類 | 課税関係(売主側) |
| 土地 | 非課税売上 |
| 建物・備品 | 課税売上 |
| 営業権(営業譲渡) | 非課税(国外取引) |
特に重要なのは「営業権」です。外国法人の本社所在地が国外であれば、外国会社の日本支店であっても国外取引と判断され、消費税の課税対象外となります。
| ステップ | 内容 |
| 1 | 日本に住所を有する代表者の全員退任の意向を確認 |
| 2 | 知れている債権者を洗い出し、個別に催告 |
| 3 | 官報に公告(期間は1か月以上) |
| 4 | 債権者から異議が出た場合、弁済・担保・信託等の対応 |
| 5 | 全手続完了後に法務局で退任登記 |
外国会社の代表者退任に関する手続きは、登記だけでなく、債権者への配慮や税務処理も絡むため、慎重に進める必要があります。特に支店の閉鎖や資産譲渡を伴う場合は、税務と登記の両面で専門的な対応が求められます。
当事務所では、外国会社の登記、代表者変更、支店譲渡に伴う税務処理などについて、司法書士・税理士の立場から一貫したサポートをご提供しております。外国法人としてのスムーズな日本撤退や再編成をお考えの場合は、ぜひお気軽にご相談ください。

司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。合わせて、複数の資格を活かして会社設立や税理士サービスなどで多方面からクライアント様に寄り添うサポートを行っている。