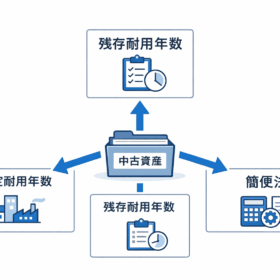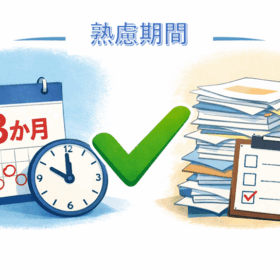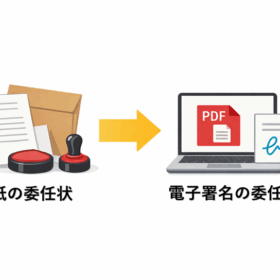Last Updated on 2025年7月6日 by 渋田貴正
近年、日本で不動産を所有する中国国籍の方が亡くなり、相続人もすべて中国籍というケースが増えています。このような場合でも、日本の不動産については相続登記を行う必要があり、2024年4月からは義務化されているため、放置しておくことはできません。これは中国籍であっても同じです。
被相続人・相続人が全員中国籍の場合の日本の相続登記について、必要書類や注意点、税金の扱いなどを解説します。
外国籍の被相続人のケースでも相続登記の義務はある?
まず重要なポイントとして、相続登記は2024年4月から義務化されています(不動産登記法第76条の2)。
不動産を相続した相続人は、相続を知った日から3年以内に登記申請をしなければならず、正当な理由がなく怠った場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。
この義務は、国籍に関係なく、日本にある不動産を相続したすべての人が対象です。つまり、被相続人・相続人が中国籍であっても、相続登記を行う必要があります。
日本と中国、適用される法律は?
不動産に関する登記や管理は、日本国内にある以上、日本の法律(民法や不動産登記法)によって処理されます。
一方で、「誰が相続人なのか」「相続分は何%なのか」といった相続権に関するルールについては、原則としては「被相続人の本国法」(中国籍の被相続人であれば中国の法律)が適用されるのが原則です。
|
(相続)
法の適用に関する通則法 第三十六条 相続は、被相続人の本国法による。
|
ただし、中国法では「不動産の相続はその所在地の法律を適用する」と定めており(中国民法典 第34編第2章第3節)、この規定により、最終的に日本法が適用されます(反致)。実務上も日本の民法に従った登記を行うことになります。
| 項目 | 適用される法律 |
| 登記手続・不動産管理 | 日本法(民法・不動産登記法) |
| 相続人の範囲・割合 | 原則:中国法(ただし不動産は反致により日本の民法が適用される) |
相続登記に必要な中国側の書類と翻訳
いくら不動産の相続に日本の民法が適用されるとはいっても、相続人の範囲を証明するのに日本側で書類を発行することはできません。身分関係は本国側の書類で証明する必要があります。
中国その他多くの国では日本のような戸籍制度がないため、親族関係や死亡の事実を証明するためには、以下のような中国の公証書類を取得する必要があります。
| 書類名 | 内容・備考 |
| 死亡公証書 | 被相続人が亡くなった事実の証明 |
| 親族関係公証書 | 被相続人と相続人の続柄を証明 |
| 遺産分割協議書 | 相続分の合意を記載(遺産分割協議書に相当。反致がある場合は日本と同じ要領で作成すればよい) |
| 相続人のパスポートの写し | 本人確認として必要 |
| サイン証明書(署名証明書) または 中国の公証処発行の印鑑証明書 |
相続人の署名を証明するもの(登記申請時に必要) |
これらの書類はすべて中国語で発行されるため、日本語訳(翻訳者の署名付き)を添付する必要があります。ただし、中国の公証書で日本語訳がいっしょに綴られている場合は不要です。
翻訳者は相続人本人でも構いませんが、正確性を求められるため、専門家に依頼するのが安心です。
署名証明書には注意
また、署名証明書については注意が必要です。登記申請書に署名する相続人が中国に住んでいる場合、署名が本人によるものであることを証明する「サイン証明書(署名証明)」が必要です。以前は在日中国大使館でこの証明を取得することが一般的でしたが、近年は大使館が署名証明を取り扱っていないケースも増えています。
その場合は、中国本国の公証処(Notary Office)でサイン証明を取得する必要があります。取得後は日本語訳を添付します。
署名証明は非常に重要な書類の一つなので、事前に取得可能かどうか確認することが不可欠です。
婚姻証明書は「結婚証」で代替できる場合も
配偶者が相続人に含まれる場合、婚姻関係を証明するための書類が必要になります。原則としては婚姻証明書の公証書(婚姻関係公証書)を取得しますが、実務では中国の「結婚証(赤い冊子)」を使用できるケースもあります。
ただし、結婚証での証明は次の条件を満たす必要があります。
- 結婚証に発行日・発行機関・夫婦の情報が明記されている
- 日本語訳を添付して内容が明確に確認できる
- 登記官が証明力を認めるかどうかはケースバイケース
確実に登記を進めたい場合は、婚姻関係の公証書を取得しておくのが望ましいです。
相続税はかかる?非居住者でも要注意
不動産を相続した場合、相続税が課される可能性があります。中国籍であっても、日本にある不動産の取得であれば、日本の相続税法が適用されます。
| 居住地の状況 | 相続税の対象財産 |
| 被相続人・相続人とも非居住者 | 日本国内の財産(不動産など)のみ対象 |
| 相続人が日本に住所あり | 日本国外を含むすべての財産が課税対象に |
さらに、相続人が日本国外に住んでいる場合は、**納税管理人の選任届出(相続税法第70条)**を行う必要があります。これを提出しないと、税務署から通知が届かず、申告期限(10か月以内)を過ぎてしまう可能性があるため注意が必要です。
2024年から相続登記が義務化され、外国籍の方も例外ではなくなりました。
中国と日本、それぞれの制度の違いを理解し、翻訳や書類の整備、登記や税務の申告を進めるには、多くの手間と正確性が求められます。
当事務所では、中国籍の相続人による日本の不動産の相続登記・税務申告に豊富な実績があります。
中国語の書類整備から登記完了まで、ワンストップで丁寧にサポートいたします。
「中国籍だけど、日本の不動産を相続した。どうすればよいか分からない」そんなときは、まずは当事務所までお気軽にご相談ください。

司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。合わせて、複数の資格を活かして会社設立や税理士サービスなどで多方面からクライアント様に寄り添うサポートを行っている。