Last Updated on 2025年5月14日 by 渋田貴正
相続登記や贈与登記を行う際、「評価証明書」と「評価通知書」という二つの書類が関係します。名称が似ているため混同されがちですが、取得方法や使い道、法的な性質は全く異なります。特に「評価通知書」は、地方税法に基づいて発行される特殊な文書であり、納税通知書や評価明細とは別物です。
評価証明書と評価通知書の違い
評価証明書と評価通知書は似て非なる分書です。その主な違いについては以下の通りです。
| 項目 | 評価証明書 | 評価通知書(地方税法第422条の3) |
| 根拠法令 | 地方税法第382条 | 地方税法第422条の3 |
| 発行主体 | 市区町村の固定資産税担当課 | 同左(登記目的で必要時に交付) |
| 交付対象 | 所有者・相続人・登記申請人等(利害関係人) | 登記申請人・法務局 |
| 取得方法 | 窓口で申請、手数料必要(1通300円程度) | 窓口で登記目的として請求、無料 |
| 登記での扱い | 登記申請書類に添付し原本還付可能 | 登記申請時に添付、原本還付不可 |
| 記載内容 | 評価額・所在地・地目・地積など詳細情報 | 評価額等の最低限の情報(登記目的) |
| 他の用途 | 税務署への提出、不動産取得税申告など | 登記専用(他用途での使用不可) |
| 取得可能な時期 | 年間を通じて取得可能 | 登記の必要があるときに限り取得可 |
評価証明書とは?税務・登記に広く使える公的書類
評価証明書とは、不動産の固定資産税評価額を証明するための公的な書類です。市区町村が発行し、相続・贈与登記、不動産取得税や相続税・贈与税の申告にも使われる汎用性の高い文書です。
主な用途
取得方法
不動産の所在する市区町村の窓口(資産税課など)で、地番を指定して申請します。本人だけでなく、相続人や登記申請者、委任を受けた代理人など利害関係人も取得可能です。
手数料は多くの自治体で1通あたり300円前後。土地・建物ごとに発行されるため、複数ある場合は通数に応じた費用がかかります。
評価通知書とは?登記専用の無料文書
一方、「評価通知書」は、登記手続に限定して交付される特殊な書類です。地方税法第422条の3に基づき、市町村が法務局に対して通知する書類の一部を、登記申請人の請求に応じて写しとして交付する制度です。
地方税法第422条の3(抜粋)
「市町村長は、毎年、当該市町村の区域内にある土地及び家屋に係る固定資産税の価格その他政令で定める事項を登記所に通知しなければならない。」
この評価通知書は、元々は法務局(登記官)が登録免許税を審査するために必要な情報を提供するものであり、登記のためにだけ使える、いわば裏方の証明書です。
取得できる場面
- 不動産の登記(相続・贈与・財産分与など)を申請する際
- 評価証明書の取得が難しい場合(例:所有者が非協力的)
特徴
- 無料で交付される(自治体によって若干異なるが通常手数料不要)
- 登記目的に限って交付される
- 原本還付ができない(登記申請後に戻ってこない)
- 記載情報は登記に必要な最小限にとどまり、税務等には使用不可
実務での使い分けのポイント
| 利用シーン | おすすめの書類 | 備考 |
| 相続登記 | 評価証明書(推奨) | 原本還付可能・他の税務にも使える |
| 贈与登記 | 評価証明書または評価通知書 | 評価通知書を使うと費用削減可能 |
| 不動産取得税申告 | 評価証明書 | 通知書は使用不可 |
評価通知書は以下のようなケースで特に有効です。
- 所有者が海外にいる、または非協力的で評価証明書の取得が難しい
- 相続人が多数おり、利害関係人としての証明に時間がかかる
- 登記費用を少しでも抑えたい
ただし、評価通知書は登記以外には一切使用できず、使い回しも不可です。そのため、今後の相続税や取得税申告の予定がある場合は、評価証明書を取得しておくのが無難です。
| 書類名 | 用途 | 取得方法 | 原本還付 |
| 評価証明書 | 登記・税務等全般 | 市区町村窓口 | 可能 |
| 評価通知書 | 登記専用 | 市区町村窓口(登記目的) | 不可 |
評価通知書は、原本が登記後に還付されない点や、他の用途に使えない点に注意が必要です。
その一方で、無料で取得でき、一定の場面では非常に有用な手段でもあります。
評価証明書・評価通知書の取得から登記までトータルでサポート
当事務所では、評価証明書の取得や、必要に応じた評価通知書の取得支援、さらに登記申請まで一貫して対応可能です。
相続登記や贈与登記などでお困りの方は、初回相談無料ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。合わせて、複数の資格を活かして会社設立や税理士サービスなどで多方面からクライアント様に寄り添うサポートを行っている。





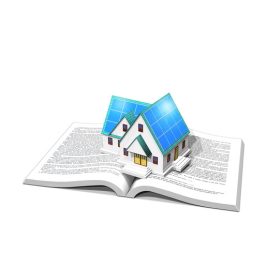





時課税-280x280.png)

