Last Updated on 2025年7月3日 by 渋田貴正
相続が発生した際、相続人の間で相続分の譲渡が行われることがあります。特に、法定相続による登記や遺産分割協議を行う前に相続分が譲渡された場合には、どのように不動産の相続登記を進めればよいのか、判断に迷うケースも少なくありません。今回は、そんな「相続登記前に相続分の譲渡があった場合」について、登記の方法や必要な書類、実際に活用される場面などを解説します。
相続分の譲渡とは?
相続分の譲渡とは、相続人が自己の持つ「相続財産全体に対する割合的な持分(=相続分)」を、他の相続人や第三者に譲渡する行為です。
これは、不動産の一部や特定の財産を売却したり贈与したりするのではなく、「相続人としての立場の一部を他者に引き継ぐ」ようなイメージに近いものです。
譲受人(譲り受けた人)は、元々の相続分がある場合には、これと譲り受けた分を合算した割合で相続人として登記されます。
どんな場面で相続分の譲渡が行われるのか?
相続分の譲渡が活用される背景には、家庭や相続人同士の事情があります。実際に多く見られるのは、以下のようなケースです。
ケース1:遺産分割協議が成立しないと見込まれるとき
たとえば3人兄弟で、長男と次男は協力的であるものの、三男が他の兄弟と対立していて協議に応じないような場合です。このようなとき、三男が長男に相続分を譲渡することで、遺産分割協議を経ずに少なくとも三男の持分は長男に相続させる登記が可能になり、手続きを前に進めることができます。
ケース2:特定の相続人が不動産を取得したいと希望しているとき
たとえば実家を相続したい兄が、他の兄弟から相続分を買い取るケースです。このような場面では、相続分の譲渡契約書を作成しておけば、法定相続登記を経ることなく、最終的な所有割合で登記を行うことができます。遺産分割協議でも対応可能ですが、次男は代償が欲しいが、三男はいらないといった個別に対応が分かれるケースでは相続分の譲渡が有効な場合もあります。
ケース3:相続に関わりたくない人がいるとき
高齢や病気、関心のなさなどの理由で、相続に関わること自体を避けたい相続人が、自分の相続分を他の相続人に譲渡してしまうケースもあります。相続放棄とは異なり、登記にはこの相続分譲渡が活用されます。
法定相続登記を経なくても直接相続分の譲渡を受けた相続人に登記できる
相続人間で相続分の譲渡があった場合には、いったん法定相続分で登記してから持分移転登記をする必要はなく、変更後の割合で直接相続登記を行うことが可能です。
たとえば甲・乙・丙が各3分の1ずつの法定相続分を有する中で、丙が甲に自己の相続分を譲渡した場合、甲が3分の2、乙が3分の1という割合で、直接登記申請することができます。
登記申請に必要な書類
実際に相続登記を申請するには、以下の書類を準備する必要があります。
| 書類名 | 内容 |
| 戸籍一式(被相続人の出生~死亡) | 相続関係を証明 |
| 法定相続情報一覧図(任意) | 上記戸籍の代替資料として利用可能 |
| 相続分譲渡証書 | 譲渡内容の記載(譲渡人の実印+印鑑証明書添付) |
| 登記申請書 | 相続人の持分に応じた登記内容を記載 |
譲渡証書は双方の相続人で締結した契約書形式でも、譲渡する相続人単独が作成した意思を確認した書面でも構いませんが、いずれにしても印鑑証明書の添付が必要です。
実務上の先例に基づく登記の具体例
登記実務では、以下のような先例により、相続分の譲渡を反映した登記が認められています。
- 先例1:5人の相続人のうち3人が相続分を1人に譲渡 → 受け取った人の登記持分を増加
- 先例2:A・B・Cの3人がDに譲渡 → D単独名義で相続登記可能
- 先例3:譲渡人が死亡していた場合 → 相続人全員の証明書を添付すれば、譲受人のみで登記可能
特定不動産だけを譲渡した場合と相続分の譲渡の違いに注意
ここで注意が必要なのは、「相続分の譲渡」と「特定不動産の持分だけの譲渡」はまったく異なる扱いになる点です。
たとえば、兄弟3人のうち、乙と丙が甲に特定の不動産の共有持分だけを譲渡して預貯金は別途協議したといった場合には、まず法定相続分による共同相続登記を行い、その後に持分移転登記(売買・贈与など)を別途行う必要があります。
| 譲渡の対象 | 登記の流れ |
| 相続分(全財産に対する割合) | → 直接、変更後の割合で相続登記可能 |
| 特定不動産のみの持分 | → 法定相続登記 → 持分移転登記(売買・贈与など) |
相続分の譲渡は一見シンプルに見えますが、「どこまでが譲渡か」「誰が登記申請人になるか」「遺産分割との関係」など、細かい判断が必要になる場面も少なくありません。
当事務所では、司法書士・税理士のダブルライセンスにより、登記手続と相続税の両面からサポートを行っております。相続人間のトラブルや協議の難航が予想される場合にも、相続分の譲渡を活用して柔軟に対応できます。
相続の進め方でお困りの方は、ぜひ当事務所へお気軽にご相談ください。

司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。合わせて、複数の資格を活かして会社設立や税理士サービスなどで多方面からクライアント様に寄り添うサポートを行っている。










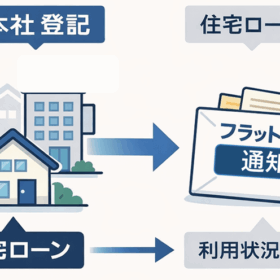

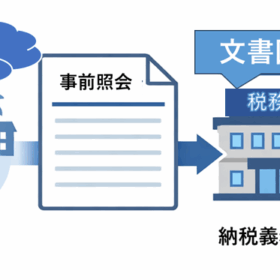

時課税-280x280.png)
