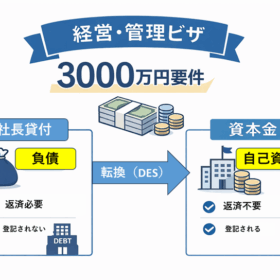Last Updated on 2025年5月27日 by 渋田貴正
遺言によって、特定の人が多くの財産を受け取ったり、生前に一部の人だけが贈与を受けたりすることがあります。こうした場合、他の法定相続人の最低限の取り分である「遺留分」が侵害されている可能性があります。
そのようなときに行うのが遺留分侵害額請求です。
多くのケースでは遺留分侵害額請求は相続人に対して行うので「遺留分侵害額請求は相続人に対してしかできない」されていますが、それは正しくありません。相続人以外であっても、遺言や契約によって財産を得た人に対しても請求が可能です。
以下で、具体的な請求対象とその順番、請求可能な金額の範囲などを詳しく見ていきましょう。
遺留分侵害額請求できる相手とは?
遺留分侵害額請求の対象は、以下のように相続人に限られず、財産を得た全ての人が対象となり得ます。
(遺留分侵害額の請求)
|
| 法定相続人以外の請求対象者 | |
| 包括受遺者 | 遺言により、財産の全部または一定割合を受け取った人(相続人でない場合もある) |
| 特定受遺者 | 遺言により、特定の財産(例:土地や株式)を受け取った人 |
| 死因贈与の受贈者 | 死因贈与契約に基づき、死亡によって財産を取得した人 |
| 生前贈与の受贈者 | 相続開始前に、被相続人から財産を贈与された人(例:不動産、生前贈与信託など) |
これらの人々は、相続人であるか否かにかかわらず、財産を受け取った事実がある限り、遺留分侵害額請求の対象となります。
遺留分侵害額請求を行う順番
誰から順番に遺留分侵害額の請求できるかは、民法で細かく規定されています。
| 組み合わせ | 優先される相手 |
| 遺贈 vs 贈与 | 遺贈が先 |
| 同順位の遺贈または贈与 | 財産の価額割合に応じて分担 |
| 異時の贈与(例:2015年と2020年) | より新しい贈与(例でいえば2020年)から請求 |
この「順番ルール」は強行規定とされており、遺留分権利者の意思で変更することはできません。また、贈与の時期については、契約日・履行日・条件成就日などを基準とする複数の学説が存在し、実務上も判断が分かれる部分です。
多少迷うのが死因贈与の場合です。「死因贈与」とは、贈与契約でありながら、被相続人の死亡によって効力を生じる契約です。その性質から、遺留分請求においては以下のような中間的扱いを受けます。
| 請求順位 | 対象 |
| 第1順位 | 遺贈(包括・特定)・財産承継遺言 |
| 第2順位 | 死因贈与 |
| 第3順位 | 生前贈与(新しい順) |
これは、判例(東京高判平成12年3月8日)でも認められており、学説もこの「中間説」が主流です。
無資力者(財産のない人)が対象の場合は請求を飛ばすことができる?
請求相手が実際には無資力(財産がない)で、たとえ請求しても回収できない場合、他の人に請求できるのでしょうか?
答えはNOです。
遺留分侵害額請求は、順番が法律で定められているため、先に請求すべき相手が無資力であっても、次の人に飛ばして請求することはできません(民法1047条4項)。
また、同順位に複数の対象者がいる場合も、全体の財産価額に応じて分担請求をする必要があり、一部の人にまとめて請求することはできません。
負担する金額の上限は?
遺留分侵害額請求では、相手方に請求できる金額にも上限があります。
| 請求相手の立場 | 上限額の考え方 |
| 遺留分を持つ相続人 | 受け取った額 - 本人の遺留分額 |
| 遺留分のない人(放棄含む) | 受け取った額全額 |
例えば、ある相続人が遺留分を放棄していた場合、その人には遺留分が存在しないため、受け取った額全体が請求対象となります。
【具体例】長男Aが遺留分を請求するケース
| ケース | 説明 | Aが請求する相手 |
| Bが遺留分を放棄していない | Bは1000万円受けており、ちょうど遺留分に相当する → 請求できない | 丙に1000万円請求 |
| Bが遺留分を放棄している | Bに遺留分なし → 全額が請求対象 | Bに1000万円請求 |
遺留分侵害額請求は、一見単純に見えても、法律に基づいた請求相手の選定や金額の計算、順番の判断など、非常に高度な判断を求められます。
また、遺言の文言次第で負担割合を変更できる点も、争いになりやすいポイントです。
誤った相手に請求をしてしまうと、時効が進行して回収不能になるおそれもあります。請求するかどうかの判断も含めて、専門家への早めの相談が非常に大切です。「どこに請求すればいいのかわからない」「遺言の内容が不公平で納得できない」
そんなお悩みをお持ちの方は、どうぞ税務と法務の専門家が両方揃う当事務所へご相談ください。
遺留分の請求対象者の調査から、請求書の作成、交渉対応、必要に応じた調停・訴訟まで一貫して対応可能です。初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。合わせて、複数の資格を活かして会社設立や税理士サービスなどで多方面からクライアント様に寄り添うサポートを行っている。