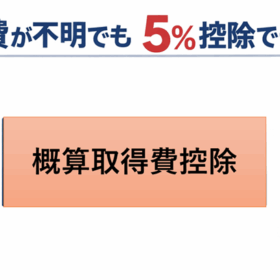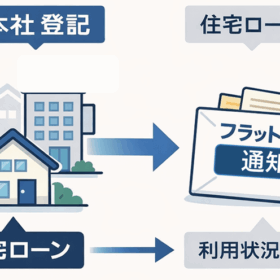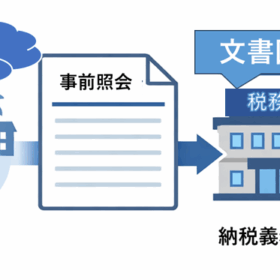Last Updated on 2025年8月21日 by 渋田貴正
2025年12月1日から、所得税に関する大きな税制改正が施行されます。今回の改正では、
- 基礎控除の拡大
- 給与所得控除の引き上げ
- 新設された特定親族特別控除
という3つの柱が導入されます。
これにより、年末調整や確定申告における控除の計算方法が大きく変わり、特に子育て世帯や低~中所得層の方に影響があります。改正の背景は政治的な面もありここでは詳しく説明せずに決まったことだけをまとめました。以下で順番に詳しく見ていきましょう。
2025年の基礎控除の見直し
基礎控除とは、一定の所得以下の納税者全員に適用される最低限の控除です。これまでは一律48万円(ただし高所得者は段階縮小)でしたが、今回の改正で2025年、2026年は一時的に特例で拡大され、2027年に新制度に移行します。
2025年、2026年の基礎控除額の比較表
| 合計所得金額 | 給与収入だけの場合 | 改正前の基礎控除 | 改正後の基礎控除 | 改正後の基礎控除への特例加算 | 改正後の基礎控除合計 |
| 132万円以下 | 200万3,999円以下 | 48万円 | 58万円 | 37万円 | 95万円 |
| 132万円超336万円以下 | 200万3,999円超475万1,999円以下 | 48万円 | 58万円 | 30万円 | 88万円 |
| 336万円超489万円以下 | 475万1,999円超665万5,556円以下 | 48万円 | 58万円 | 10万円 | 68万円 |
| 489万円超655万円以下 | 665万5,556円超850万円以下 | 48万円 | 58万円 | 5万円 | 63万円 |
| 655万円超2,350万円以下 | 850万円超2,545万円以下 | 48万円 | 58万円 | 0円 | 58万円 |
| 2,350万円超2,400万円以下 | 48万円 | 48万円 | 0円 | 48万円 | |
| 2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 | 32万円 | 0円 | 32万円 | |
| 2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 | 16万円 | 0円 | 16万円 | |
| 2,500万円超 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
2027年以降の基礎控除額の比較表
| 合計所得金額 | 給与収入だけの場合 | 改正前の基礎控除 | 改正後の基礎控除 | 改正後の基礎控除への特例加算 | 改正後の基礎控除合計 |
| 132万円以下 | 200万3,999円以下 | 48万円 | 95万円 | 37万円 | 95万円 |
| 132万円超336万円以下 | 200万3,999円超475万1,999円以下 | 48万円 | 58万円 | 0円 | 58万円 |
| 336万円超489万円以下 | 475万1,999円超665万5,556円以下 | 48万円 | 58万円 | 0円 | 58万円 |
| 489万円超655万円以下 | 665万5,556円超850万円以下 | 48万円 | 58万円 | 0円 | 58万円 |
| 655万円超2,350万円以下 | 850万円超2,545万円以下 | 48万円 | 58万円 | 0円 | 58万円 |
| 2,350万円超2,400万円以下 | 48万円 | 32万円 | 0円 | 32万円 | |
| 2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 | 32万円 | 0円 | 32万円 | |
| 2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 | 16万円 | 0円 | 16万円 | |
| 2,500万円超 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
この表から分かるとおり、2025年と2026年分は一時的に大幅拡大されますが、令和9年分以後は58万円を基本とし、2,400万円超から段階的に縮小される仕組みになります。
例えば、給与収入が180万円程度の人の場合、従来は48万円の控除でしたが、令和7年分では95万円に増えるため、課税所得が47万円分減少し、その分所得税が軽減されます。
2025年の給与所得控除の見直し
給与所得控除とは、会社員など給与所得者が経費としてみなされる控除です。改正のポイントは、最低保障額が55万円から65万円へと10万円引き上げられたことです(所得税法第28条)。
給与所得控除額の比較表
| 給与等の収入金額 | 2024年まで | 2025年から |
| 1,625,000円まで | 550,000円 | 650,000円 |
| 1,625,001円~1,800,000円 | 収入×40% – 100,000円 | 650,000円 |
| 1,800,001円~1,900,000円 | 収入×30% + 80,000円 | 650,000円 |
| 1,900,001円~3,600,000円 | 収入×30% + 80,000円 | 収入×30% + 80,000円 |
| 3,600,001円~6,600,000円 | 収入×20% + 440,000円 | 収入×20% + 440,000円 |
| 6,600,001円~8,500,000円 | 収入×10% + 1,100,000円 | 収入×10% + 1,100,000円 |
| 8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) | 1,950,000円(上限) |
最低賃金付近やパートタイムで働く方など、比較的収入が低い層に恩恵が大きい改正です。
2025年の特定親族特別控除の新設
今回の改正で新たに導入されたのが「特定親族特別控除」です。配偶者には、「配偶者特別控除」がありますが、19歳以上23歳未満で年収123万円を超えてしまった子を持つ親のためにも似たような制度ができたと思えばよいでしょう。
特定親族特別控除の対象となるのは、19歳以上23歳未満の親族で、合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入換算で123万円超188万円以下)の場合です。
特定親族特別控除額の表
| 合計所得金額 | 給与のみの場合 |
特定親族特別控除額 |
||
| 超 | 以下 | 超 | 以下 | |
| 58万円 | 85万円 | 123万円 | 150万円 | 63万円 |
| 85万円 | 90万円 | 150万円 | 155万円 | 61万円 |
| 90万円 | 95万円 | 155万円 | 160万円 | 51万円 |
| 95万円 | 100万円 | 160万円 | 165万円 | 41万円 |
| 100万円 | 105万円 | 165万円 | 170万円 | 31万円 |
| 105万円 | 110万円 | 170万円 | 175万円 | 21万円 |
| 110万円 | 115万円 | 175万円 | 180万円 | 11万円 |
| 115万円 | 120万円 | 180万円 | 185万円 | 6万円 |
| 120万円 | 123万円 | 185万円 | 188万円 | 3万円 |
例えば、大学生の子どもがアルバイトで年収150万円だった場合、従来は扶養控除の対象外でしたが、この改正により「特定親族特別控除」の63万円が適用されます。親の課税所得から大きく控除できるため、実質的な税負担軽減につながります。
扶養控除の壁の引き上げ
これまで「103万円の壁」と呼ばれていた扶養親族等の所得要件が、今回の改正により大きく見直されました。改正前は、扶養控除や配偶者控除の対象となるためには、合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合で103万円以下)である必要がありました。そのため、多くの家庭ではアルバイトやパートの収入を103万円以内に抑えるかどうかが重要な判断基準とされてきました。
しかし令和7年改正後は、基礎控除が95万円に引き上げられたことに伴い、扶養親族や同一生計配偶者、ひとり親の子については「58万円以下(給与収入のみの場合で123万円以下)」に要件が引き上げられました。これにより、いわゆる「103万円の壁」は「123万円の壁」となり、従来よりも収入の上限に余裕が生まれています。
改正によるまとめ
子どもの年齢区分ごとの比較表
今回の改正によって、従来は被扶養者の所得税非課税と扶養控除の対象となる収入のボーダーラインが103万円でイコールでしたが、今回の改正によって両者が別のボーダーラインになりました。この点が混乱しやすい部分だと思います。
| 年齢区分 | 子自身の所得税がかからないバイト年収上限 | 親が子について扶養控除を受けられる子の収入上限 |
|---|---|---|
| 16歳未満 | 160万円 | 123万円 |
| 16歳以上19歳未満 | 160万円 | 123万円 |
| 19歳以上23歳未満 | 160万円 | 123万円 |
| 23歳以上 | 160万円 | 123万円 |
当事務所では、今回の税制改正に伴う年末調整・確定申告の実務対応、さらには扶養控除や親族控除の適用判定まで幅広くサポートしています。複雑な控除の判定や書類作成も安心してお任せください。ぜひ一度ご相談ください。

司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。合わせて、複数の資格を活かして会社設立や税理士サービスなどで多方面からクライアント様に寄り添うサポートを行っている。