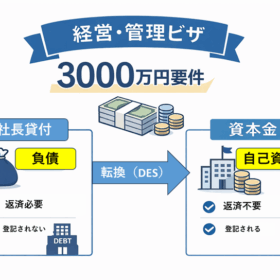Last Updated on 2025年7月30日 by 渋田貴正
被相続人が過去に無国籍だった期間がある場合、その身分関係や相続人の確定は非常に困難です。特に成人後に無国籍状態だったケースでは、その間に子どもが生まれている可能性を否定できず、相続人の範囲が不明確になるリスクが高まります。
そのため、相続登記や税務申告を進めるには、被相続人と相続人との関係を公的書類で証明するだけでなく、無国籍期間の扱いについても明確化する必要があります。
無国籍者の相続に適用される法律(準拠法)は?
日本では、相続に関する準拠法は以下の通り定められています。
■ 原則:被相続人の本国法(国籍法)
国際的な相続においては、原則として「被相続人の本国法(国籍のある国の法律)」が適用されます。
■ 例外:無国籍者の場合の準拠法
無国籍者については本国法が存在しないため、以下の条文により、常居所地の法律が適用されることになります。
| (常居所地法) 法の適用に関する通則法 第39条 当事者の常居所地法によるべき場合において、その常居所が知れないときは、その居所地法による。(後略) |
たとえば、被相続人が生前に日本に居住していた無国籍者であれば、原則として日本法(民法)が相続に適用されます。
無国籍状態が発生する例と背景
無国籍者は世界的に見ても少数ですが、以下のような経緯で無国籍になるケースが知られています。
| ケース | 内容 |
| 1 | 親の国が出生地主義、出生国が血統主義で国籍が与えられない |
| 2 | 他国への帰化のために国籍放棄したが、帰化が不許可に |
| 3 | 両親ともに無国籍であり、子も国籍を取得できなかった |
| 4 | 出生登録がなされず、存在自体が証明されない場合 |
このような背景をもつ方が日本に移住し、無国籍のまま生活・死亡した場合、その相続は日本の法律に基づいて処理されることが多いです。
被相続人が無国籍であることによる実務上の課題:相続人の確定
無国籍期間が存在することで、相続人の範囲を証明する書類が欠落する可能性があります。特に、成人後の無国籍期間は「その間に認知していない子どもが存在するかもしれない」といった可能性を排除できません。
そのため、相続登記や相続税申告、特に相続登記を行うにあたり、「相続人が他にいないこと」「相続関係に争いがないこと」を示す必要があります。
上申書の提出とその重要性
上記のような事情がある場合、登記所や税務署では、相続人全員が署名・押印した上申書を提出することで、事実関係を補完します。
■ 上申書に記載すべき内容
- 被相続人の略歴(国籍の変遷、無国籍期間、居住地)
- 無国籍となった経緯とその間の生活状況
- 無国籍期間中に配偶者・子が存在しないことの説明
- 相続人全員がその内容を認めている旨
この上申書は、登記手続きにおける補助資料として非常に重要であり、提出しない場合、登記申請が却下される可能性もあります。上申書は特に決まった内容があるわけではなく、作成には法的な知識も必要です。
| 手続き | 必要な対応 | 無国籍期間の影響 |
| 不動産の相続登記 | 相続人の確定、戸籍・翻訳書類、上申書 | 国籍不明期間の補完資料が必要 |
| 相続税申告 | 法定相続分に基づく財産評価・申告 | 相続人の範囲が不明確だと課税誤差のリスクあり |
とくに税務署に対しては、申告の正確性が求められるため、「相続人がこれだけで間違いない」という説明責任を果たす必要があります。
無国籍期間がある相続案件は、日本の戸籍制度にも外国の書類制度にも精通していないと対応が難しく、通常の日本人の相続よりも多くの専門的判断と実務的対応が必要です。
当事務所では、国籍を有しない方や外国籍の方の相続・登記・税務申告に多数の実績があります。
無国籍や国籍喪失、上申書の作成、翻訳証明など、複雑な手続きを円滑にサポートいたします。
「無国籍の期間があったが相続手続きを進めたい」といったお悩みがある方は、どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。

司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。合わせて、複数の資格を活かして会社設立や税理士サービスなどで多方面からクライアント様に寄り添うサポートを行っている。