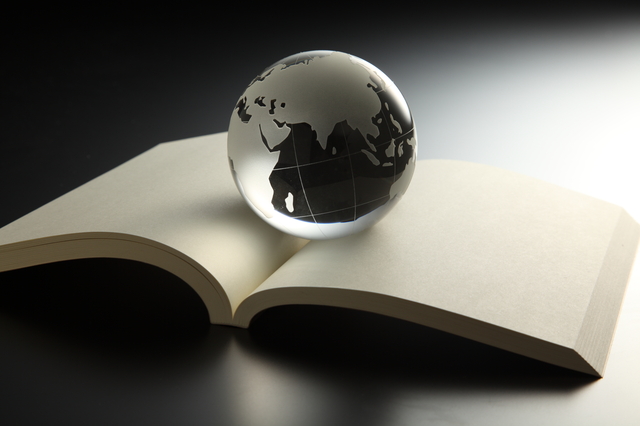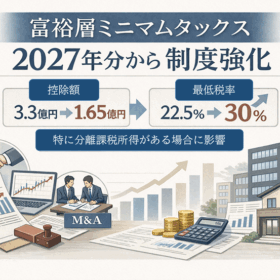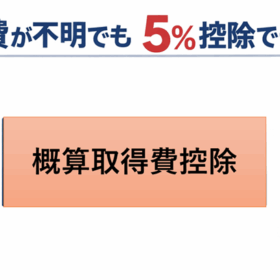Last Updated on 2025年5月19日 by 渋田貴正
被相続人が外国籍だった場合で遺留分を侵害するような遺言を残していた場合、相続人が「日本で遺留分侵害額の請求はできるのだろうか?」と悩まれるケースがあります。特に国際相続では、どこの裁判所に申し立てができるのか、どの国の法律が適用されるのか、どの財産が対象となるのかが問題となります。
外国籍の被相続人に対する遺留分侵害額請求の可否については、以下の3つのポイントが重要となります。
- 遺留分請求が認められるか(準拠法)
- どこの裁判所に請求できるか(裁判管轄)
- どの財産が請求の対象となるか(財産の範囲)
日本の家庭裁判所で遺留分侵害額請求ができるのはどんなとき?
遺留分侵害額請求はまず「家庭裁判所への調停申立て」から始めるのが一般的です。外国籍の被相続人であっても、以下のいずれかに該当すれば、日本の家庭裁判所に調停を申し立てることが可能です。
| 認められるケース | 解説 |
| 請求対象となる訴訟に日本の裁判所の管轄がある | 後述の「訴訟の国際管轄」のいずれかに該当 |
| 相手方の住所が日本国内にある | 最も多く見られる実務上の典型パターン |
| 当事者間で日本の家庭裁判所を選ぶ合意がある | 遺留分請求においては稀で、実務上ほとんど見られない |
実際のケースでは、「相手方の住所が日本国内にある」ことを理由に申し立てられることが大多数です。たとえば、被相続人が外国籍であっても、日本に住む相続人に対して遺留分の請求を行う場合には、家庭裁判所の管轄が認められやすいといえます。
| (家事調停事件の管轄権) 家事事件手続法 第3条の13 裁判所は、家事調停事件について、次の各号のいずれかに該当するときは、管轄権を有する。 一 当該調停を求める事項についての訴訟事件又は家事審判事件について日本の裁判所が管轄権を有するとき。 二 相手方の住所(住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所)が日本国内にあるとき。 三 当事者が日本の裁判所に家事調停の申立てをすることができる旨の合意をしたとき。 |
日本の地方裁判所で遺留分侵害額請求の訴訟ができる場合とは?
家庭裁判所での調停が不成立だった場合、地方裁判所に訴訟を提起することになります。この場合、以下のいずれかに該当すれば、日本の裁判所に国際裁判管轄が認められます。
| 認められるケース | 解説 |
| 被告(相続人)の住所が日本国内にある | 実務上最も典型的なパターン |
| 日本国内に差し押さえ可能な財産がある | 財産の価額が極端に少額でなければOK |
| 相続開始時に被相続人の住所が日本国内にあった | 住所・居所・滞在地などが日本国内であった場合が該当 |
ただし、外国の裁判所でも同様の訴訟が係属している場合には、日本の裁判所が「特別の事情」として、訴えを却下することもあります。たとえば、外国の裁判所で既に審理が進んでいる、証拠がすべて外国にあるといった場合は日本での管轄が認められない可能背があるので注意が必要です。
| (被告の住所等による管轄権) 民事訴訟法 第3条の2 裁判所は、人に対する訴えについて、その住所が日本国内にあるとき、住所がない場合又は住所が知れない場合にはその居所が日本国内にあるとき、居所がない場合又は居所が知れない場合には訴えの提起前に日本国内に住所を有していたとき(日本国内に最後に住所を有していた後に外国に住所を有していたときを除く。)は、管轄権を有する。(契約上の債務に関する訴え等の管轄権) 民事訴訟法 第3条の3 次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定めるときは、日本の裁判所に提起することができる。 (中略) 3 財産権上の訴え 請求の目的が日本国内にあるとき、又は当該訴えが金銭の支払を請求するものである場合には差し押さえることができる被告の財産が日本国内にあるとき(その財産の価額が著しく低いときを除く。)。 |
遺留分の準拠法は被相続人の「本国法」
遺留分の制度が適用されるかどうかは、相続の準拠法によって決まります。
| (相続) 法の適用に関する通則法 第36条 相続は、被相続人の本国法による。 |
国際相続において、最も重要といってもよいこの条文の「相続」には遺留分侵害額請求も含んでいます。つまり、原則として、相続開始時における被相続人の「本国法」が適用されます。
| ケース | 適用される準拠法 |
| 被相続人が日本国籍 | 日本法 |
| アメリカ国籍で日本在住 | アメリカの抵触法により、日本法が準拠法となる可能性(反致) |
| アメリカ国籍でアメリカ在住(ドミサイル) | 米国州法(たとえばUPCなど)が準拠法 |
アメリカなど一部の国では、不動産については「所在国法」、動産については「ドミサイル地法(最後の居住地の法)」が準拠法になることがあります。そのため、アメリカ市民で日本在住の場合は、アメリカの抵触法の適用により日本法が準拠法とされるケース(反致)も多く見られます。
遺留分算定の対象となる財産とは?
日本法が準拠法である場合(日本人・反致適用時)
日本法が準拠法となる場合、遺産の所在地にかかわらず、すべての遺産が遺留分算定の対象になります。日本法は「相続統一主義」を採用しており、たとえばアメリカにある預金や不動産も対象に含められます。
外国法が準拠法である場合
一方で、アメリカなど外国法が準拠法となる場合には、不動産はその所在地法、動産はドミサイル地法が適用されるなど、財産の種類ごとに異なる扱いがされることがあります。
| 財産の種類 | 適用法の一例(アメリカ) |
| 不動産 | 不動産の所在地の法(例:アメリカ州法) |
| 動産 | 被相続人のドミサイル地法(例:日本法など) |
したがって、日本にある財産が遺留分の対象から外れる可能性もあるため、準拠法の判断が非常に重要です。
外国籍の被相続人が関わる遺留分侵害額請求は、準拠法・裁判管轄・財産の範囲が複雑に絡み合い、一般の方が判断するのは非常に困難です。国際私法や各国の抵触法に加え、相続税や登記の観点も含めた多面的な検討が必要となります。国際相続は、日本の相続とは異なる難しさがあり、慎重な対応が必要です。当事務所では、税理士・司法書士の立場から、相続・税務・登記の各側面を総合的にサポートいたします。外国籍の被相続人に関する遺留分請求でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。

司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。合わせて、複数の資格を活かして会社設立や税理士サービスなどで多方面からクライアント様に寄り添うサポートを行っている。