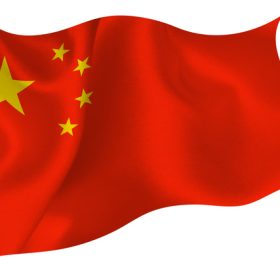Last Updated on 2025年5月9日 by 渋田貴正
会社設立をお考えの方は、役員報酬(給与)をいくらに設定するかを必ず決めることになります。
しかし、この役員給与、金額次第では税務上大きなリスクが潜んでいます。
法人税法では、不相当に高額な役員給与(過大役員給与)は会社の経費(損金)として認められず、結果として法人税が増える可能性があります。
会社設立直後は特に税務リスクを避ける役員給与設定が重要です。以下で具体的な注意点を解説します。
過大役員給与については、次の3つのケースで過大かどうかを判断する基準が設けられています。
| 類型 | 判断内容 |
|---|---|
| ①時期の外れた使用人分の賞与 | 他の社員の賞与時期と異なるタイミングで支給した賞与は全額過大扱い |
| ②過大な退職給与 | 役員の勤務期間や会社の業績に比べて不当に高額な退職金 |
| ③その他の役員給与 | 職務内容や同業他社と比べて不当に高額な通常の役員報酬 |
ケース①|支給時期がズレた使用人分賞与は「過大」に!
会社を設立し、役員が従業員(使用人)としても働くケースは珍しくありません。この場合、役員としての給与のほか、社員としての「使用人分賞与」を支給することもあります。しかし、他の社員と異なるタイミングで支給した賞与は、金額に関係なく自動的に過大給与とされ、会社の経費になりません。
たとえば、社員には6月と12月にボーナスを支給しているのに、役員の使用人分賞与だけ9月に支給した場合、金額が適切でも損金不算入です。さらに、社員と同じ時期に「未払い」として経理し、実際の支給を遅らせても税務署から否認される可能性がありますので要注意です。
もし、過去の社員としての勤務に対する賞与を役員昇格後に支給する場合でも、「相当額」であれば経費として認められます。
支給時期や計上処理には特に注意が必要です。
ただし、一人社長などの場合は、こうした従業員兼役員といった問題は生じないので、このケースは使用人兼務役員である取締役がいるようなケースで、どちらかというと従業員がある程度の人数いるような規模の会社で注意すべきポイントです。
ケース②|高すぎる退職金
設立したばかりの会社でも、将来的に役員退職金を支払う可能性があります。役員退職金の金額は、次の基準で過大かどうかが判断されます。
- 勤務期間
- 退職の事情(普通退職か、会社都合か)
- 業界・同規模企業の相場
これらに比べて不当に高額な場合、その超過部分は損金不算入とされます。
たとえば、5年しか在任していない役員に数千万円の退職金を払った場合、税務調査で否認されることがあります。特にオーナー社長が退職金を多く受け取って節税を図るケースは調査対象になりやすいです。
また、企業年金や厚生年金をすでに受給している場合は、その額も加味して「過大」と判断されることがあります。内規がなくても株主総会で合理的な退職金額を決めれば経費計上できますが、同業他社の相場や役員の職務内容を考慮して適正額を算出することが重要です。
ケース③|役員給与が高すぎる場合(実質基準・形式基準)
毎月支払う役員給与についても過大給与の判断基準があります。このケースが最も重要であり、どの規模の会社にも当てはまりますので注意が必要です。
■実質基準
次の要素をもとに、給与額が過大かどうか判断されます。
- 役員の職務内容
- 会社の収益・社員の給与状況
- 同業他社の役員給与相場
たとえば、理屈の上では、設立したばかりで売上がまだ少ないのに、役員給与を月100万円など高額に設定すると、税務署から「過大」と判断されるリスクがあるということです。ただし、会社法上は役員報酬は株主が決めるのが原則となっていますので、そうして決定された役員報酬の金額が過大だと認定するのはかなりの理論的な根拠が必要です。
実際には、役員報酬の金額が高くても、しっかりと所得税側で確定申告を行うなど対応を取っていれば過大だと認定されることは少なくとも代表者については滅多にないことです。どちらかといえば、家族を役員にしているようなケースで、家族の業務内容に比べて役員報酬の金額が高すぎるといったケースで問題になることが多いです。
■形式基準
会社の定款や株主総会で決めた報酬枠(上限)を超える給与を支払った場合、その超過額は自動的に損金不算入です。
なお、役員が社員としても働いている場合(使用人兼務役員)、社員分の給与については、他の社員との比較などにより相当額であれば経費と認められます。
役員給与の金額設定は事前にしっかり検討し、税務上の根拠を用意しておくことが大切です。
会社設立時の役員給与の設定ミスは、創業期の経営にとって致命的な税務リスクになりかねません。また、役員報酬の設定は、税金だけではなく、社会保険料や資金繰りの問題にも直結します。
当事務所では、会社設立時の役員給与設定から、税務リスクのない給与規程作成、適正額のアドバイスまでトータルでサポートしています。
まずはお気軽にご相談ください。あなたの新しいビジネスを、税務・法務の面からしっかりサポートします!

司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。合わせて、複数の資格を活かして会社設立や税理士サービスなどで多方面からクライアント様に寄り添うサポートを行っている。