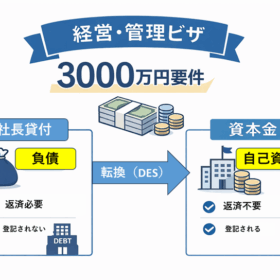Last Updated on 2025年10月28日 by 渋田貴正
個人事業主が法人化して会社設立する理由の一つに、消費税の納税義務を回避したいという点があります。
消費税の納税義務の判定で最も基本的なのが「基準期間」による判定です。基準期間とは、個人事業主の場合は前々年、たとえば2022年の判定なら2020年が基準期間になります。
そして、この基準期間中の課税売上高が1,000万円を超えた場合に消費税の納税義務が発生します。
ただし、「法人化したから必ずリセットされる」と単純に考えるのは危険です。新たに設立された法人(基準期間がない法人)は、原則として設立1期目・2期目は免税となる扱いですが、次のような例外に該当すると、設立直後から課税事業者となることがあります。
・設立時の資本金(出資金)が1,000万円以上である場合
・適格請求書発行事業者(インボイス登録事業者)として登録している場合
・「特定新規設立法人」に該当する場合
このうち「特定新規設立法人」とは、設立の日前2年以内に「関係者(個人または法人)」が事業を行っていた場合で、その関係者が新設法人の出資金または議決権の50%超を直接または間接に保有しているときに該当します。
ここでいう「関係者」とは、単に親しい人物や同業者といった日常的な意味ではなく、消費税法上の定義に基づく法律上の概念です。
設立者や株主、役員、その親族(配偶者・同居の親子など)、あるいは新法人を支配する親会社やその関連会社など、「資本的に支配しているか」「経営を実質的に動かしているか」という実質的な支配関係で判断されます。
この制度は、かつて見られた「免税制度の悪用」への対策として導入されたものです。たとえば、大企業が100%子会社を次々設立し、形式上は新設法人として消費税の免税を繰り返すといったケースが問題となりました。その防止策として、「特定新規設立法人」は、国内売上5億円超またはグループ全体(海外含む)で50億円超の場合に適用されます。
もっとも、この金額は中小企業の一般的な事業規模からはかけ離れています。個人事業主が年商数千万円から1億円程度で法人化するようなケースでは、この制度が問題となることはまずありません。実際の対象は、親会社が5億円を超える売上を持ち、その子会社として新法人を設立するようなケースです。
したがって、一般的な法人成りでは「そういう制度もあるが自分には関係ない」と考えて差し支えないでしょう。
一方で、大企業グループや関連会社が多い法人では、親会社の売上が5億円を超えている、グループ全体の収益が50億円を超えている、親会社が新法人の株式の過半数を保有している、といった場合には注意が必要です。その場合は、設立初年度から課税事業者となる可能性があります。
つまり、個人事業主の法人成りの際に注意しておくべき点は以下の2点ということになります。
・設立時の資本金(出資金)が1,000万円以上である場合
・適格請求書発行事業者(インボイス登録事業者)として登録している場合
このように、個人事業主のときの売上がいくらであろうと、必ずしも単純に「法人化で消費税がリセットされる」わけではありません。資本金、関係会社の規模、インボイス登録の有無を総合的に判断することが重要です。
固定資産を引き継ぐ際の消費税にも注意
また、法人化の際に注意すべきもう一つのポイントは、個人が保有する固定資産の引継ぎです。個人事業主が課税事業者である場合、個人から法人へ固定資産を売却したり現物出資したりすると、その取引が消費税の課税対象となることがあります(対価性のある取引=課税対象)。
具体的には次のような点に注意が必要です。
| 区分 | 消費税の課税の有無 | 課税となる理由・法的根拠 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|---|
| 売買(譲渡) | 課税対象(※土地を除く) | 建物・機械・什器などの資産を対価を得て譲渡するため。課税事業者の行う資産の譲渡 | 建物や設備の時価で譲渡すると、その金額に対して消費税が発生。土地部分は非課税。帳簿価額と譲渡価額の差額が所得税・法人税にも影響する。 |
| 現物出資 | 課税対象 | 出資として資産を譲渡し、見返りに株式等を取得するため。株式の時価が対価に相当 | 出資により取得する株式の評価額(時価)が課税標準となる。形式上の出資でも「対価性あり」とみなされ課税されるため、非課税にはならない。 |
| 贈与・無償譲渡 | 原則非課税(ただし例外あり) | 無償で資産を譲渡する場合、対価性がないため消費税の課税対象外。ただし、負担付贈与など、実質的に対価を伴う場合は課税。 | 無償で譲渡した場合は消費税はかからないが、贈与税や法人側の受贈益課税が問題になることがある。税目全体での有利・不利を検討する必要あり。 |
個人事業主が法人化して会社設立する理由の一つとして、消費税の納税義務があります。消費税の納税義務の判定として、最も基本的なものが基準期間による判定です。
基準期間とは、個人事業主の場合は2年前、例えば2022年であれば2020年を指します。そして、この基準期間中の課税売上高が1,000万円を超えた場合に消費税の納税義務が発生します。
しかし、もし個人事業主が会社を設立して法人化した場合は、この基準期間はリセットされます。
個人事業主の法人化の場合、個人事業主がそのまま社長になって同じ事業を行うことになるケースがほとんどですが、法人と個人では別人格ですので、別の人が売り上げを上げたことになるのです。
法人の場合は、基準期間は原則として2事業年度前の売上となりますが、設立して2年間は2事業年度前がないので、原則として免税事業者となります。法人化によって少なくとも2年間は消費税の納税義務を免除されることになります。
個人事業主のときの売上がいくらであろうと、法人化によって消費税の納税義務もリセットされることになります。
個人事業主の確定申告の期間は1月1日から12月31日と決まっています。そのため、法人化するのもキリよく1月からというケースも多いかもしれません。
もちろん、所得税だけを考えれば、この決め方が最もスッキリしてよいでしょう。
しかし、もし個人事業主として既に消費税の納税義務があるとしたら、別の視点から法人化の時期を考える必要があります。
それは、個人事業主が保有している固定資産を設立した会社に引き継ぐ点です。
もし、消費税の納税義務がある状態、つまり課税事業者の状態で法人化すると、固定資産を引き継ぐ場合にも、その取引に消費税がかかってしまいます。
個人事業主と設立した会社の代表者が同じだったとしても、別人格なので、固定資産も個人から法人に売却したことになるのです。そして、固定資産を売却した場合、課税事業者であれば消費税が課税されます。
特に飲食店のように固定資産を多く抱える業種ほど、この消費税問題は重要です。 それでは、売却以外の方法でなんとかならないか考えてみましょう。
まず思い浮かぶのは現物出資です。設立する会社に売却するのではなく、現物出資するということです。消費税では、現物出資で資産を会社に譲渡した場合も課税が行われる旨が規定されています。
この場合は、取得した株式の時価が対価となります。そのため、現物出資の方法を採っても、資産の譲渡として消費税が課税されることになります。
固定資産の設立した会社への譲渡において消費税を回避する方法としては、設立日をちょっと前倒しにして12月(もしくはそれ以前)にするという方法が考えられます。
キリよく1月に法人化ということも、目的が確定申告を半端な期間で行わないということであれば、12月後半などに設立したとしても、その目的は達成されます。
当事務所では、法人成りに伴う消費税・所得税・贈与税・法人税の影響をワンストップで試算し、お客様の事業実態に最も適した資産承継スキームをご提案します。まずは現状の資産一覧(土地・建物・設備の概略)と最近2年間の売上、予定資本金額をお知らせください。設立日や移転方法まで含めて、最も有利で安全な法人化プランをご提案いたします。

司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。合わせて、複数の資格を活かして会社設立や税理士サービスなどで多方面からクライアント様に寄り添うサポートを行っている。