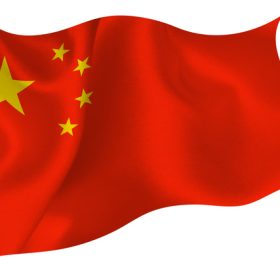Last Updated on 2025年1月28日 by 渋田貴正
不動産登記での生年月日の提供
不動産登記では、所有者の住所と氏名(共有であれば持分)が記録されています。不動産登記の際に新たな所有者の住所や氏名を申請書に記載して、その情報が登録されます。
所有者の氏名や住所といった情報は、不動産の権利関係を公に示す重要な役割を果たしていますが、生年月日の記録は行われていません。将来的には、不動産登記の際に、住所・氏名の情報に加えて生年月日の情報も登記申請時に法務局に提供することが予定されています。
生年月日については、登記事項証明書の情報としては不要なので、法務局内部で記録される情報(表には出ない情報)として、法務局にて情報が保管されます。
なぜ生年月日を法務局に提供するのか
生年月日を法務局で管理する理由は、不動産所有者の正確な特定と、登記内容の更新を円滑に行うためです。
具体的には、不動産の所有者の生年月日を法務局で管理することで、住所・氏名に加えて生年月日も使って、自治体が管理する住民基本台帳ネットワークに情報を照会することが、よりやりやすくなります。こうすることで、所有者が死亡した事実や、引っ越しによる住所の変更や、婚姻等による氏名の変更を法務局側で把握しやすくなります。
相続登記の義務化や、所有者の住所や氏名の変更登記の申請の義務化を見据えて、法務局側からも登記の働きかけを行っていくための変更といえるでしょう。
マイナンバーとの違いと慎重な運用
個人の特定といえば最も確実なのはマイナンバーかもしれません。ただ、マイナンバーは税金や社会保障のための番号なので、登記申請の際にマイナンバーを法務局に提供するということは現行法では、さすがにできないでしょう。生年月日が登記記録の裏情報として法務局で保管されることで、相続登記の未申請も法務局で把握しやすくなります。不動産を相続したら、相続登記をするか、相続放棄をするかなど、相続人間でしっかりと話し合うことがますます重要になります。
相続登記義務化と生年月日提供の関係性
2024年4月から施行された相続登記の義務化は、不動産の所有権が相続により移転した場合、相続人が3年以内に登記を申請しなければならないことを規定しています。この改正により、相続登記が怠られた不動産に対して、10万円以下の過料が科される可能性があります。
生年月日情報が法務局に提供されることで、法務局側から相続人に対する登記の促進や、相続登記の未申請物件への対応がより積極的に行われると考えられます。相続人側から見れば、相続登記が未完了の場合は、速やかに相続登記の申請や、その代替となる相続人申告登記、国庫帰属制度の活用などを検討すべきでしょう。

司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。合わせて、複数の資格を活かして会社設立や税理士サービスなどで多方面からクライアント様に寄り添うサポートを行っている。