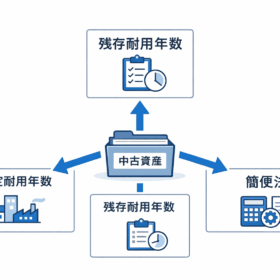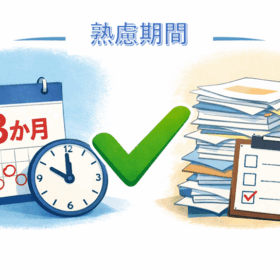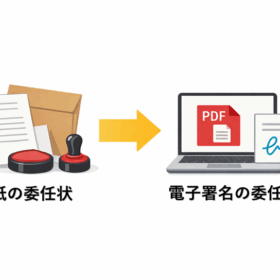Last Updated on 2025年10月18日 by 渋田貴正
2023年10月から始まったインボイス制度(適格請求書等保存方式)は、会社設立のタイミングで検討すべき重要な制度です。
インボイスとは、国税庁に登録した「インボイス発行事業者」だけが発行できる請求書で、取引先が消費税の仕入税額控除を受けるために必要になります。
設立したばかりの会社は原則として「消費税の免税事業者」となりますが、取引先の状況や信用面を考えると、設立と同時に登録しておいた方が有利な会社も多くあります。
会社設立時にインボイス登録をした方がよい会社の特徴
BtoBで取引先が課税事業者である場合
取引先が消費税を申告・納税している「課税事業者」である場合、相手は仕入税額控除を受けるためにインボイスを必要とします。
もしあなたの会社が登録していなければ、相手は控除できず、
- 取引金額を消費税分減額される
- 別のインボイス登録している取引先に変更するために契約を断られる
といった不利益が発生しかねません。
特にBtoB取引や下請け業務では、インボイス未登録は大きなマイナス要素になります。
特にBtoBで信用面で重要な場合
インボイス未登録は、単に税務上の問題だけではありません。企業経営上の信用面で不利になるリスクがあります。
BtoB取引の相手企業は、
- 「制度対応がきちんとできているか」
- 「財務体制が整っている会社か」
- 「小規模すぎて、依頼した仕事をしっかり対応できる体制があるのか」
といった点を重視します。
設立直後の会社がインボイス未登録だと、
- 「この会社、大丈夫かな?依頼した仕事を完遂できるだろうか?」
- 「依頼後にトラブルにならないだろうか」
という不安を抱かれる可能性があります。
つまり、インボイス登録は「税金のため」だけではなく、対外的な信頼を示すシグナルでもあるのです。
初年度から売上が1,000万円を超える見込みがある場合
消費税の免税基準は「前々事業年度の課税売上高が1,000万円以下」であることです。会社設立初年度は前々年度が存在しないため、原則として売上がいくらあっても免税事業者になります。
そのため、本来はインボイス登録をせずに免税事業者としてスタートすれば、初年度の消費税の納税が不要となり、資金繰り上は有利に働くことが多いです。
しかし、初年度から大口の契約や高額な取引が見込まれている会社では、取引先が課税事業者であるケースが多く、インボイス未登録だと相手側が仕入税額控除をできず、契約条件や金額面で不利になる場合があります。
また、2期目以降は課税事業者になるため、初年度だけ免税→翌期から登録という対応は、契約・請求書の切り替えなど実務面で煩雑になる点にも注意が必要です。
1年目は免税なのにあえて設立時に登録しておくことで、
- 開業直後からインボイスを発行できる
- 途中で登録が間に合わず契約上トラブルになるのを防げる
といった利点があります。
大口契約を控えているスタートアップや、フランチャイズ加盟の飲食店などは、このパターンに当てはまります。
簡単にまとめると以下のようになります。
| 登録をした方がよい会社の例 | しなくてもよさそうな会社の例 |
|---|---|
| BtoB取引が中心で、取引先が課税事業者(仕入税額控除を必要とする) | BtoC(一般消費者)向け取引が中心で、取引先が仕入控除を必要としない |
| 建設業・下請け業など、取引先から登録を求められる業種 | 小売・飲食業など、消費者相手の売上が中心で登録の要請が少ない業種 |
| 初年度から売上1,000万円超が見込まれる会社 | 売上が少なく、当面は免税事業者のメリットを活かしたい会社 |
| 大手企業・上場企業・広告代理店などとの取引を予定している会社 | 地域密着型の小規模事業で、取引先が主に個人事業主や消費者の会社 |
| 信頼・信用力を重視されるコンサル・士業・制作業など | 開業初期で資金繰りを優先し、信用面で大きな影響が出にくい業種 |
インボイス登録と会社設立の実務
設立と同時に登録を進める場合、次の流れになります。
| 手続き内容 | 提出先 | タイミング |
| 法人設立登記申請 | 法務局 | 設立日 |
| 設立届出書提出 | 税務署 | 設立直後 |
| 課税事業者選択届出書提出 | 税務署 | 設立直後 |
| インボイス登録申請書提出 | 税務署 | 設立直後 |
インボイス登録は申請からおおよそ1か月で通知が届きます。設立時にまとめて処理すれば、スムーズにスタートできます。
ケーススタディで見るインボイス登録の判断
実務では、業種や取引形態によってインボイス登録の必要性は大きく異なります。
以下では、代表的な業種・ケースごとに判断のポイントを具体的に紹介します。
建設業(下請け会社)
元請け課税事業者との取引が中心の建設業では、未登録だと請負金額から消費税分を減額されるケースが一般的です。
1,100万円(税込)の請負でも、登録していなければ1,000万円しか受け取れないといった現実があります。
さらに、元請け側から「制度対応に遅れた会社」と見られ、長期的な取引から外される可能性もあります。
→ 設立と同時の登録が実務上ほぼ必須です。ただし、古くから付き合っている会社との取引のみであれば、インボイス未登録に理解を示してくれるかもしれません。
IT・制作業(フリーランスから法人化)
制作業界やIT業界では、発注元が大手企業であることが多く、インボイス番号がないと社内処理ができないケースが増えています。
法人化直後に未登録だと、「小規模で体制が弱そう」という印象を持たれ、契約を逃すこともあります。
→ 信用・営業の両面から登録が有効です。
飲食業・小売業(BtoC中心)
主な取引先が一般消費者である場合は、インボイス未登録でも売上への影響は少ないです。
開業初期は免税事業者として消費税分を手元に残し、資金繰りに充てる戦略も有効です。
→ 将来の事業拡大を見据えて判断します。
コンサル・士業
顧問契約など長期的な関係では、相手企業が税務体制や会社の信頼性を重視します。
未登録だと「この会社に任せて大丈夫か」と不安視されることがあります。
→ 登録が信用力強化の大きな武器となります。
輸出業・越境EC
輸出免税が多い業種では、登録の要否が還付額やキャッシュフローに直結します。
→ 税額計算を踏まえた専門家への相談が不可欠です。
専門家に相談して最適な判断を
インボイス登録の要否は、税務上の損得だけでなく、信用や営業戦略にも大きく関わる経営判断です。
当事務所では、会社設立とインボイス登録をワンストップでサポートし、業種・売上・信用戦略を踏まえた最適な手続きをご提案しています。
「設立直後の信用を高めたい」「登録するか迷っている」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。

司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。合わせて、複数の資格を活かして会社設立や税理士サービスなどで多方面からクライアント様に寄り添うサポートを行っている。