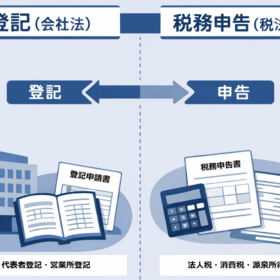Last Updated on 2025年9月20日 by 渋田貴正
相続税は、被相続人が亡くなった時点で保有していた財産全体を基に計算されます。計算方法は「総額方式」と呼ばれ、まず財産全体から相続税総額を算出し、その後に各相続人や受遺者の実際の取得額に応じて税額を按分します。
つまり「自分がもらった分だけで税額を計算する」のではなく、「全財産をもとに総額を計算し、その結果を取得分に応じて負担する」仕組みです。
居住無制限納税義務者と制限納税義務者の違い
相続税の課税範囲は、被相続人や相続人の居住地や国籍によって変わります。
| 区分 | 該当する人 | 課税対象となる財産 |
| 居住無制限納税義務者 | 日本に住所がある人、日本国籍で過去5年以内に日本に住所があった人 | 世界中の財産 |
| 非居住無制限納税義務者 | 日本国籍で過去15年以内に住所があったが現在は国外在住 | 世界中の財産 |
| 居住制限納税義務者 | 外国籍で過去15年以上日本に住所がない人 | 日本国内の財産のみ |
| 非居住制限納税義務者 | 日本に住所がなく、外国籍かつ過去15年以内に住所がない人 | 日本国内の財産のみ |
多くの場合、日本に住む一般的な相続人は「居住無制限納税義務者」にあたり、国内外の全財産が課税対象となります。
外国居住者の遺産を日本在住者が特定遺贈された場合の税対応
以下の事例で考えてみます。
- 被相続人:外国に長年居住(居住制限納税義務者)
- 相続財産:合計1億円(うち日本のマンション1,000万円、その他財産9,000万円)
- 受遺者:日本在住(居住無制限納税義務者)、遺言によりマンションを特定遺贈
この場合、被相続人が外国に住んでいたからといって「国内財産だけが課税対象」とはなりません。相続人や受遺者に居住無制限納税義務者が含まれているため、課税対象は国内外の全財産=1億円となり、その後、受遺者が実際に取得したマンション(1,000万円)の割合に応じて税額を負担します。
特定遺贈の相続税計算の流れ
特定遺贈を受けた場合も、基本的には通常の相続と同じ総額方式で税額を計算します。
- 遺産総額を確定
国内外すべての財産を評価します。 - 基礎控除の適用
3,000万円+600万円×法定相続人の数を控除。
特定受遺者は相続人でなければ控除人数に含まれません。 - 課税遺産総額を法定相続分で按分
法定相続分を基準に仮計算し、相続税総額を求めます。 - 実際の取得額に応じて分配
特定受遺者は、実際に受け取った財産額に比例した税額を負担します。
計算イメージ
- 遺産総額:1億円
- 基礎控除:3,600万円(相続人1人の場合)
- 課税遺産総額:6,400万円
- 相続税総額を計算 → 日本在住の特定受遺者は取得割合(1/10)に応じた税額を負担
ちなみに、日本の特定受遺者からすれば気になるところかもしれませんが、残り9,000万円を外国在住の相続人が取得した場合のその扱いは次のとおりです。
| 立場 | 納税義務者区分 | 日本での課税対象 |
| 日本在住の特定受遺者(マンション1,000万円) | 居住無制限納税義務者 | 全財産を基に計算 → 実際の取得額1,000万円分に応じた税負担 |
| 外国在住の相続人(9,000万円) | 居住制限納税義務者 | 日本国内の財産に限り課税。国外財産なら日本で課税されない |
つまり、日本にある財産はマンションだけで、あとは海外にある預貯金や不動産といった場合には、結局日本に住んでいる特定受遺者だけが日本での相続税の課税対象になるということです。
特定受遺者が全財産を把握できない場合はどうする?
特定遺贈を受けた人にとって、被相続人の全財産(特に国外財産)を把握することは現実的に困難です。遺産の大半を取得するのは他の相続人であり、受遺者は自分の取得分以外の情報にアクセスできない場合が多いですし、相続人に確認することも言語の壁や文化の壁などがあり、非常に困難です。
実務上の対応
- 相続人や遺言執行者に協力を依頼
財産目録の作成は相続人や遺言執行者の役割であり、受遺者単独で全体を把握する必要はありません。 - 把握できる範囲で申告し説明を付す
不明点がある場合には、その旨を申告書に記載して税務署に説明することが可能です。 - 情報交換制度の活用
CRS(金融口座情報自動交換制度)や租税条約を通じ、日本の税務当局が国外財産情報を把握するケースもあります。 - 連帯納付義務の意識
相続税には連帯納付義務があるため、受遺者が知らなかった国外財産についても、課税が発生すれば責任が及ぶ可能性があります。調査状況を記録し、専門家のサポートを受けておくことが重要です。
「被相続人は海外在住」「受遺者は日本在住」というケースでは、課税範囲が全世界財産に及ぶ一方で、特定受遺者には国外財産の把握が難しいという実務上の課題があります。相続税申告だけでなく、不動産登記、相続人との調整、二重課税リスクへの対応まで考えると、専門的なサポートが欠かせません。
当事務所は税理士・司法書士として、税金の相談から登記手続きまで対応いたします。国際相続に関するご不安も安心してご相談ください。

司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。合わせて、複数の資格を活かして会社設立や税理士サービスなどで多方面からクライアント様に寄り添うサポートを行っている。









時課税-280x280.png)