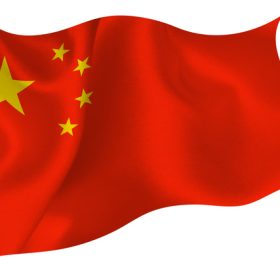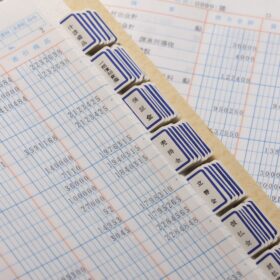Last Updated on 2025年9月15日 by 渋田貴正
会社を立ち上げて間もない経営者の方にとって、最初に直面する経費処理の一つが「出張費」です。
取引先への営業、銀行や役所への訪問、地方での打合せなど、創業期は動き回ることが多いものです。そのときに必ず出てくるのが「交通費」「宿泊費」そして「日当」という概念です。
日当は、出張に伴い、通常の勤務では生じない追加的な支出を補うための定額支給です。領収書を一つ一つ提出できない小さな出費をカバーする役割を持っています。
出張日当の支給方法2パターン
出張費を従業員や役員にどう支給するかは、会社の旅費規程で決めます。大きく分けると次の2つの方法があります。
- パターン①:交通費・宿泊費を含めて一括支給
- パターン②:交通費・宿泊費は実費精算し、日当は別途支給
パターン①はシンプルですが、金額が大きすぎると給与とみなされ課税対象になるリスクがあります。
パターン②は実費精算と日当を区分するので透明性が高く、多くの会社が採用している方法です。
| 区分 | 内容 | 支給方法 | 特徴 | 税務上の取扱い |
|---|---|---|---|---|
| パターン①:交通費・宿泊費を含めて一括支給 | 出張にかかる交通費、宿泊費、日常の雑費をまとめて定額で支給 | 「出張1回につき○○円」「1日あたり○○円」など定額 | 精算業務が楽になる | 社会通念上相当額を超えると給与扱い(課税対象) |
| パターン②:交通費・宿泊費は実費精算、日当は別途支給 | 交通費・宿泊費は領収書精算、それ以外の雑費を日当で支給 | 実費+日当(例:宿泊費・交通費は領収書、日当は1日○○円) | 透明性が高く安心感あり | 実費部分は非課税、日当部分も相当額なら非課税 |
さらにこのほかに国内出張日当、国外出張日当という区分や日帰り出張か宿泊かで日当の額を分ける会社もあります。
「日当で節税できる」ということの意味とは?
会社設立直後によく耳にするのが、「日当を設定すれば節税になる」という話です。よく個人事業主との違いでも、「法人は日当を出せるので得」という記述も見られます。しかし、これは本質的にはミスリードです。日当はあくまで「実費弁償」であり、妥当な範囲を超えれば給与と同じ扱いになります。
確かに日当は、税務上「非課税」となる場合があります。しかし、ここだけが一人歩きしてしまい、本来の日当の意味を理解しないまま金額を設定してしまうケースが多いのが実情です。
「日当で節税」というのは、例えば実費合計だと4,000円だったけど、日当は5,000円で設定しているから5,000円を日当として支給して、その結果1,000円多く経費が計上できた、という意味合いです。
日当はあくまで、出張に伴って発生する食費や雑費といった小規模で領収書を取りにくい支出を補うための制度です。つまり「実費弁償」の性格を持っており、給与とは異なる扱いが認められているに過ぎません。実費の補填だから所得税が課税されないということであり、決して「出張お疲れさま代」ではないということです。日当という名目でも実費の裏付けがない「出張お疲れさま代」として支払うのであれば、それは給与です。
例えば、1泊2日の国内出張で1日あたり2,000〜3,000円程度なら一般的に問題ありませんが、これを1日2万円と設定すれば会食費を日当の範囲に含めているなどの事情がない限り「雑費を補う金額」とは考えにくく、課税対象となる可能性が高くなります。
従業員がいる会社で役員だけに日当を出すのは危険
従業員を雇用している会社で注意すべきなのが「役員にだけ日当を支給する」ことです。
従業員がいる会社で役員だけに日当を出すと、その日当は役員給与と同じ扱いになります。さらに、
- 定期同額給与(毎月同じ金額で支給する給与)にも当たらず
- 事前確定届出給与(あらかじめ税務署に届け出た賞与)にも当たらない
ため、法人税の計算上は損金(経費)に認められない可能性が極めて高いのです。
つまり「役員の日当」という名目でも、結果的に会社の経費にならず、税金が重くなるリスクがあるのです。
特にもともと役員1名の時に日当を計上していて、従業員雇用後も役員だけに日当を支払い、従業員は日当を支払わず出張中の雑費は個人負担というケースに要注意です。
日当支払いをする際にに押さえるべき3つのポイント
-
旅費規程を必ず整備する
出張費や日当をどう扱うかは、必ず「旅費規程」に明文化しておきましょう。規程がないまま曖昧に運用してしまうと、後から税務署に説明する際に根拠を示せず、不利な判断を受けるリスクがあります。特に設立直後の会社では、経理体制が整っていないことも多いため、最初の段階でしっかりルールを作っておくことが、安心して経営を続けるための大きなポイントになります。 -
金額設定は「相場」を意識する
日当の金額は、同業他社の水準や国税庁が示す目安を参考にして決めるのが安全です。高額すぎる日当を設定してしまうと、給与とみなされ課税対象になる可能性が高まります。一方で、あまりに低すぎると従業員の実費補填にならず不公平感が出ることもあります。適正なバランスを意識し、「社会通念上相当」とされる範囲に収めることが重要です。 -
日当と実費精算のダブルカウントに注意
日当の範囲に含めている費用について、実際の領収書でも精算してしまうと「二重計上」となり、不適切な経費処理とみなされます。たとえば、日当の中に「軽微な交通費」や「ちょっとした飲食費」を含めているのに、同じ費用を領収書で経費精算してしまえば、同一の出費を二度計上していることになります。これは税務調査でも問題視されやすいポイントです。したがって、旅費規程の中で「日当でカバーする範囲」と「実費精算する範囲」をしっかり線引きし、従業員にも分かりやすく伝えておくことが大切です。 -
役員への支給は慎重に
従業員がいる会社で役員だけに日当を支給すると、税務上は給与と同じ扱いを受け、法人税の計算上、損金算入が認められない可能性が極めて高くなります。さらに、定期同額給与や事前確定届出給与にも当たらないため、結果として「経費にできない支給」となり、会社の税負担が重くなる危険性があります。会社設立直後は役員だけで動く場面も多いですが、その場合でも「日当」という名目で安易に支給せず、給与との区分を明確にしながら慎重に制度を設計することが重要です。
安心して会社運営を進めるためには、旅費規程をきちんと整え、社会通念上妥当な範囲で日当を設定することが欠かせません。当事務所では、会社設立直後から必要な旅費規程の整備や、役員給与・日当の扱いについてのご相談に対応しています。ぜひお気軽にご相談ください。

司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。合わせて、複数の資格を活かして会社設立や税理士サービスなどで多方面からクライアント様に寄り添うサポートを行っている。