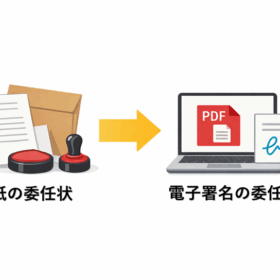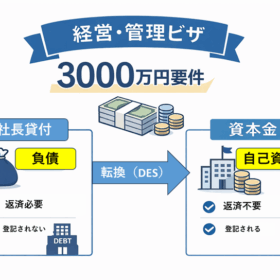Last Updated on 2025年10月29日 by 渋田貴正
現物出資と登記・登録の関係
会社設立時や増資の際に「現物出資」を行う場合、対象となる資産には不動産や在庫、自動車、株式、知的財産権などさまざまなものがあります。
このうち登記や登録が必要な資産については、会社の登記事項証明書がなければ手続きが進められません。したがって、会社設立前に登記や登録を済ませることは実務上不可能です。
この点について、会社法第34条では次のように定められています。
| 会社法 (出資の履行)
|
つまり、登記・登録は会社成立後でも構わず、発起人全員の同意があれば成立後に行うことが認められています。実務的にも、登記事項証明書を添付できない段階では登録ができないため、会社成立後に手続きを行うことが一般的です。
登記・登録が必要な主な現物出資資産
現物出資で登記・登録などが必要となる代表的な資産は以下のとおりです。
| 資産の種類 | 必要な手続き |
| 土地・建物 | 不動産登記による所有権移転 |
| 自動車 | 車検証の所有者変更(運輸支局で手続き) |
| 上場株式などの有価証券 | 証券会社口座の名義変更・移管 |
| 売掛金などの債権 | 債権譲渡登記または通知による対抗要件具備 |
| 特許権・商標権など | 特許庁への名義変更登録 |
中でも実務上よく見られるのが、自家用車を社用車として現物出資するケースです。次に、この自動車の現物出資に関する税務上のポイントを見ていきます。
社用車として現物出資する場合の税務上の取扱い
出資者個人の税務処理
自家用車を会社に現物出資するということは、簡単に言えば「会社に車を売却し、その対価として株式を受け取る」行為にあたります。したがって、個人側では所得税上の譲渡所得の問題が生じます。
ただし、車の使用目的によって課税関係が異なります。
| 使用目的 | 所得税の扱い |
| 主として通勤用 | 生活用動産の譲渡として非課税 |
| 主としてレジャー用 | 譲渡所得として課税対象 |
たとえば、地方で通勤に欠かせない生活用の車を現物出資する場合は非課税ですが、趣味のドライブ用として保有していた車であれば課税対象となります。
| 所得税法 第9条 非課税所得 次に掲げる所得については、所得税を課さない。 (中略) 9 自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゆう器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得 |
譲渡所得は次の式で計算されます。
譲渡所得 = 現物出資額 −(取得費 − 減価償却費)
ここで、減価償却費は購入価格の90%をもとに、法定耐用年数の1.5倍を上限とした期間で按分して計算する「簡便法」が使われます。
また、自家用車など生活用動産の譲渡所得は年間50万円までは非課税(所得税法第9条2項)です。したがって、評価額の設定を慎重に行えば、税金がかからない範囲で現物出資することも可能です。
なお、現物出資額(=評価額)は一般的に中古車販売価格などを参考に合理的に算定する必要があります。税務署が不当に高い評価額と判断した場合には、みなし譲渡所得として課税されるおそれもあるため注意が必要です。
設立する会社側の会計・税務処理
会社側では、現物出資により取得した自動車を中古資産として計上します。
この場合の耐用年数は、所得税法施行令第49条に基づく「中古資産の耐用年数の算定式(簡便法)」で計算します。
耐用年数=(法定耐用年数−経過年数)+経過年数×20%
端数が出た場合は切り捨てです。たとえば法定耐用年数6年の車を3年半使用していた場合は、
6−3.5×80%=3.2年→3年が耐用年数となります。
現物出資額が500万円を超える場合の検査役制度
現物出資額が500万円を超える場合や適正な価値算定に疑義がある場合には、原則として裁判所が選任する検査役による評価が求められます。ただし、弁護士・公認会計士・税理士などの証明を添付した場合は検査役を省略できる制度もあります。
したがって、自動車のように時価が明確な資産であれば、多くのケースで検査役の選任は不要です。
そもそも会社法では「検査役」なるものが規定されていますが、実務上、検査役の選任の事例はほぼ皆無と言ってよいでしょう。
減価償却はこの残存耐用年数に基づいて計算され、取得原価は現物出資額(株式の発行価額相当額)となります。
現物出資は登記・税務の双方に関わるため、個人だけで進めると見落としが生じがちです。特に評価額の算定や検査役省略の可否などは、税理士・司法書士双方の観点から検討することが安全です。
当事務所では、登記と税務をワンストップで対応し、会社設立時の現物出資手続きをスムーズにサポートしています。自家用車の出資をお考えの方は、ぜひご相談ください。

司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。合わせて、複数の資格を活かして会社設立や税理士サービスなどで多方面からクライアント様に寄り添うサポートを行っている。