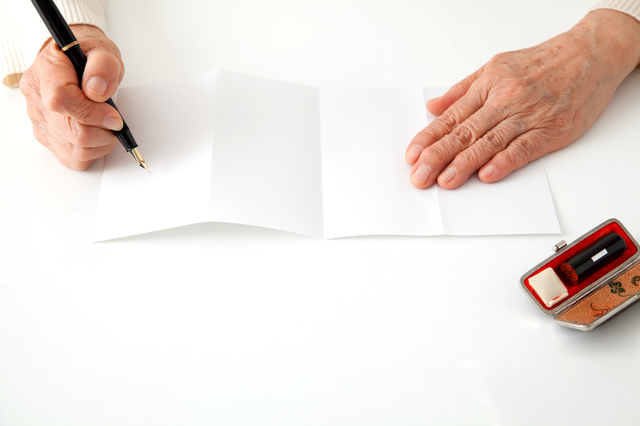Last Updated on 2025年12月2日 by 渋田貴正
死因贈与は、ひと言でいえば「生前に約束しておき、亡くなったときに効力を発揮する贈与」のことです。相続や遺贈と似た仕組みですが、遺言のように一方的に書き残すものではなく、生前に贈与者と受贈者双方の合意が必要となる契約です。
死因贈与は特定の財産を確実に渡したいときには便利な制度ですが、契約である以上、解除が問題になる場面もあります。「死因贈与って一度決めたら後戻りできないの?」というご相談をよくいただきますが、実際はケースによって解除できたり、できなかったりと、法律的にも奥の深い制度です。ここを誤解すると相続人間のトラブルにつながりかねませんので、特に死因贈与をする側(贈与者)にとっては注意が必要です。
書面によらない死因贈与はありえない
口頭で「私が死んだらこの預金あげるよ」といったように、書面を作らずに成立した死因贈与は、かなり軽い扱いになります。履行が終わっていない限り、贈与者はいつでも解除できます。
| 民法 (書面によらない贈与の解除) 第550条 書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。 |
条文上は「贈与」となっていますが、死因贈与も贈与の一形態であり、この条文が適用されます。
しかも裁判例では、死因贈与であれば贈与者が亡くなった後でも贈与者の相続人が解除できると判断されています。つまり、「父が生前に言っていたけど、本当にあげるつもりだったの?」という疑問が残る場合には、相続人がその約束をなかったことにできる可能性があるわけです。
口頭の約束は便利な反面、後々「言った・言わない」で揉める温床にもなりがちです。死因贈与のつもりが、最終的にはただの世間話として扱われてしまうこともありますので、死因贈与については書面で贈与契約書を作成しておくことが必須といえます。
書面による死因贈与の解除の可否
書面を作成した死因贈与は、法律的にワンランク重い契約として扱われます。書面という証拠が存在する以上、「やっぱり気が変わったから解除したい」といった単純な意思だけでは解除できません。このときに基準となるのが、遺言の撤回です。
| 民法 (遺言の撤回) 第1022条 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。 |
判例は、「遺言の方式に従って」という部分を除いてこの1022条の考え方を死因贈与にも準用すべきだとしています。つまり、「遺言と同じように、原則としていつでも撤回(解除)できる」という立場です。ここだけ聞くと、「書面でもいつでも解除できるなら問題ないのでは?」と思うかもしれません。しかし実際はもっと複雑で、判例は個別の事情に応じて解除を制限する方向に進んでいます。
死因贈与は契約と言いながら、遺言のように贈与者の一存で解除できるということを言っているわけですが、契約である以上、贈与者といえども解除に一定の制限がかかります。特に象徴的なのが、贈与者と受贈者が不動産をめぐって訴訟中に裁判上の和解で死因贈与が合意されたケースです。この事案では、最高裁が「この死因贈与は、贈与者が自由に取り消せるものではない」と判断しました。裁判上の和解は、法律的には最も重いレベルの約束とも言えるため、そこから生まれた死因贈与については、遺言による撤回のように軽々しく扱うことができないという発想です。
つまり、「遺言のように撤回できる」と言っておきながら、「でも重い事情があるなら撤回できない」とも言っているわけで、判例はバランスを取りながら細かく線引きをしているのです。
また、「死因贈与後に作った遺言では消せない」と判断した裁判例も存在します。普通は「最後の遺言が最も強い」と思われがちですが、死因贈与は契約であるため、一方的な遺言で上書きできないということです。つまり、贈与契約のほうが遺言より強く働くという、法律の世界ならではの逆転現象が起こり得るのです。その意味で、受贈者にとっては死因贈与のほうが遺言よりも安心という側面があります。
| 種類 | 解除の可否 | ポイント |
|---|---|---|
| 書面によらない死因贈与 | いつでも解除可 | 死亡後の相続人による解除も可能。実務上はありえない。 |
| 書面による死因贈与 | 原則解除可 | 民法1022条準用。ただしケースにより制限される。 |
| 負担付死因贈与 | 解除が厳しく制限 | 負担の履行があると原則解除不可。 |
負担付死因贈与の解除が制限される理由
負担付死因贈与は、「贈与を受ける代わりに何かをする」という条件付きの死因贈与です。よくあるのは、「生前に介護する」「生活費を支給する」「死後に配偶者を扶養する」などのパターンです。
この場合、受贈者が実際に負担を履行していれば、急に契約を解除するのは公平ではありません。たとえば、受贈者が数年間にわたり介護を続けてきたのに、「やっぱりやめた」と言われたらたまったものではないでしょう。判例でも、負担が十分に履行されている場合には解除が認められないケースがほとんどです。
逆に、負担がまったく履行されていなかったり、形式的な履行しかなされていない場合には解除が認められています。つまり、「どれだけ負担が実行されていたか」という、非常に現実的なポイントが裁判で判断されるわけです。
死因贈与は遺言とも贈与とも微妙に違い、その“中間のような存在”であることから、法律判断が非常に難しい制度です。特に不動産が関係すると、解除の可否により登記や税務の影響が大きく変わります。一般の方がご自身で判断すると、後から取り返しがつかない事態になることも珍しくありません。
当事務所では、死因贈与契約の作成、見直し、解除判断、不動産登記、贈与税の検討までワンストップで対応しています。税理士と司法書士の両方の視点から最適なルートをご提案しますので、気軽にご相談ください。いつでもお待ちしております。

司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。合わせて、複数の資格を活かして会社設立や税理士サービスなどで多方面からクライアント様に寄り添うサポートを行っている。