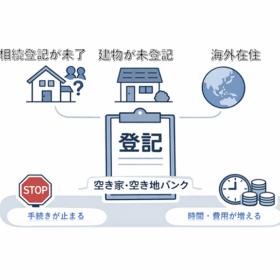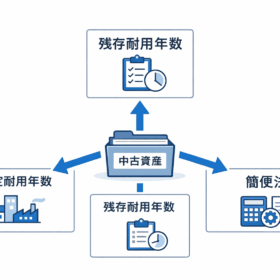Last Updated on 2025年10月21日 by 渋田貴正
会社を新しく設立すると、通常は設立初年度の消費税が免除されます。
これは「事業を始めたばかりの人の資金負担を減らす」という創業支援の目的で設けられた制度です。
しかし、すべての新設法人が免税の対象になるわけではありません。
一定の条件に該当すると、設立1期目から消費税を納める必要があり、これを「特定新規設立法人」と呼びます。
ただし、この制度は多くの中小企業が想像するような「個人事業を法人化した場合」に適用されるものではありません。
実際には、売上規模が5億円を超えるような大企業グループが対象です。
特定新規設立法人とは
特定新規設立法人とは、設立の日前2年以内に「関係者(個人または法人)」が事業を行っていた場合で、その関係者が新設法人の出資金または議決権の50%超を直接または間接に保有しているときに該当します。
ここでいう「関係者」とは、単に親しい人物や同業者といった日常的な意味ではなく、消費税法で定められた法律上の概念です。
新設法人と資本・人事・取引関係などを通じて密接な関係を持つ者が含まれ、主に次のような範囲が想定されています。
-
新設法人の設立者、発起人、株主、役員
-
それらの者の親族(配偶者、同居の親、子など生計を一にする家族)
-
新設法人の株式や出資の50%超を保有する法人
-
その法人に支配されている関連会社や子会社
つまり、「資本的に支配しているか」「経営を実質的に動かしているか」が判断の軸となります。
たとえば、親会社が子会社の過半数株式を持つ場合や、役員構成がほぼ同一の関連会社などは典型的な該当例です。
一方で、取引先や協力会社のように、一定の契約関係があっても経営支配が及ばない場合は関係者には当たりません。
このように、関係者の範囲は「形式的な人間関係」ではなく、「実質的な支配関係」に基づいて判断される点が重要です。
なぜ特定新規設立法人という制度があるのか
この制度の背景には、過去に見られた「免税制度の悪用」があります。
たとえば、
「大企業の親会社が、新たに100%子会社を設立して事業を分散し、形式上は新設法人であるとして消費税の免税を繰り返す」
といったケースが以前は多く見られました。
このように、法人化を繰り返すことで消費税の納税を回避する行為が問題視され、その防止策として「特定新規設立法人」の制度が導入されました。
具体的には、国内売上5億円超または日本以外も含めたグループ全体収益50億円超が要件となります。
この金額は、中小企業の一般的な事業規模からはかなりかけ離れています。
そのため、個人事業主が年商数千万円〜1億円程度で法人化する場合は、特定新規設立法人に該当する可能性はなく、一般的な法人成りで気にすることもないでしょう。
実際の想定対象は、親会社が5億円以上の売上を持ち、その子会社として新法人を設立するようなケースです。
一般的な中小企業では心配無用ですが、大企業グループや関連会社が多い企業では、次のような場合に注意が必要です。
- 親会社の売上が5億円を超えている
- 海外売上を含めてグループ全体の収益が50億円を超える
- 親会社が新設法人の株式の50%超を保有している
このような場合は、設立初年度から課税事業者となる可能性があります。
一方で、個人事業主の法人成りや、家族経営の小規模会社は、これらの基準を大きく下回るため、免税制度の対象外となることはまずありません。
中小企業者が注意すべきは「特定期間」
中小企業にとって、実務的に注意すべきなのは「特定新規設立法人」ではなく、「特定期間」と呼ばれる別の制度です。
これは、資本金や給与支払額などの条件で判断されます。
| 区分 | 特定新規設立法人 | 特定期間 |
| 主な対象 | 大企業グループ | 中小企業全般 |
| 基準 | 売上5億円・収益50億円超 | 資本金1,000万円以上、給与支払1,000万円超 |
| 趣旨 | 免税悪用防止(大企業対策) | 実質的に課税規模の法人の捕捉 |
このように、特定新規設立法人は中小企業にはほとんど無関係ですが、似た名前の制度との混同から誤解されやすいテーマです。
会社設立の際には、資本金や給与額などを正確に把握し、どの制度に該当するかを事前に確認しておくことが重要です。
当事務所では、税理士・司法書士が一体となり、会社設立から消費税の判定、登記・税務届出までを一括サポートしています。
創業初年度の税負担を最小限にしたい方は、ぜひお気軽にご相談ください。

司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。合わせて、複数の資格を活かして会社設立や税理士サービスなどで多方面からクライアント様に寄り添うサポートを行っている。