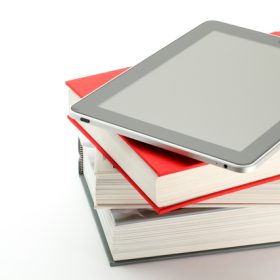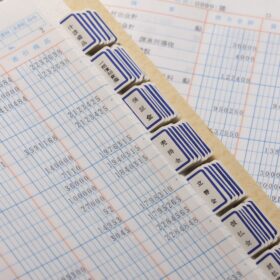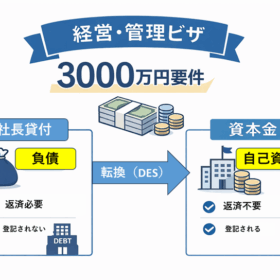Last Updated on 2025年9月10日 by 渋田貴正
贈与契約の基本
贈与とは、当事者の一方が財産を無償で相手に与える意思を表示し、相手が受諾することで成立する契約です。つまり「贈与します」という申込みと「贈与を受けます」という承諾が合致して、初めて効力が生じます。
ここで重要なのが、書面の有無による違いです。民法は次のように定めています。
| (贈与) 第549条 贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。 (書面によらない贈与の解除) 第550条 書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。 |
つまり、口頭やメールだけで行った贈与契約は、贈与者・受贈者どちらからでも自由に解除できてしまいます。これでは法的安定性に欠けるため、後日の争いやトラブルにつながるおそれがあります。
一方で、書面による贈与契約は原則として解除できません。書面にしておけば、当事者双方に拘束力が生じ、確実に効力が維持されるのです。したがって、贈与を行う際には、特に受け取る側(受贈者)としては、書面を作成しておくことが望ましいです。
| 書面による贈与 | 口頭による贈与 | |
|---|---|---|
| 契約の成立 | 書面により申込みと承諾を明確に記録 | 口頭で「贈与する」「受ける」と合意 |
| 法的効力 | 原則として解除できない(民法550条) | 双方から解除可能(履行済部分は除く) |
| 証拠力 | 契約書等が残るため強い | 後日「言った・言わない」の争いになりやすい |
| 安全性 | 安定性が高く、トラブル防止になる | 不安定で、贈与者・受贈者どちらも撤回しやすい |
贈与契約における「書面」の形式は2パターン
贈与の意思表示を文書化する方法には、大きく分けて2種類があります。
それぞれの特徴を表で整理します。
| 項目 | 贈与契約書(1通方式) | 贈与証書+贈与承諾書(2通方式) |
| 書面の数 | 1通 | 2通(贈与証書と贈与承諾書) |
| 内容 | 申込みと承諾を同一書面に記載 | 申込みと承諾を別々に記載 |
| 証拠力 | 双方が署名押印するため強い | セットで保管すれば有効だが、片方だけだと弱い |
| 実務上の利便性 | 同じ日に受贈者と贈与者がいる場合に便利 | 書類を別々にやり取りしたい場合に便利 |
| 推奨度 | 実務ではこちらが主流 | 特殊な事情がある場合に利用可 |
実質的に書面による贈与と扱われるパターン
上記のような贈与契約書や贈与証書+承諾書方式以外にも以下のようなケースで書面による贈与と扱われます。
-
金銭や有価証券の引渡しを証する受取書がある場合
「〇年〇月〇日、甲から金100万円を受領した」と記載された受領証や領収証が交付されている場合、そこから無償譲渡の意思が明らかに認められれば、書面による贈与と扱われます。 -
登記や名義変更に必要な書面が交付された場合
-
内容証明郵便による贈与意思表示
いただいた例のように、贈与者が「私は〇〇に対し、この土地を贈与するので、前所有者から直接移転登記を行ってほしい」と内容証明郵便で表明した場合、その書面は「書面による贈与」と評価されます。
贈与の書面の方式と登記との関係
不動産や株式など、登記や名義変更を伴う財産の贈与では、書面の形式が特に重要です。
土地を贈与する場合を例にすると、法務局で所有権移転登記を申請します。その際、登記原因証明情報として「贈与契約書」または「贈与証書+承諾書」どちらも提出できます。
ただし、実際には別途「登記原因証明情報」を作成するので、贈与契約書や承諾書などを登記申請時にそのまま法務局に提出することは少ないでしょう。
贈与は単に「あげる・もらう」のやり取りではなく、税務と登記に直結する重要な法律行為です。書面の形式を誤ると、後から税務署や法務局で思わぬ指摘を受ける可能性もあります。
当事務所では、贈与契約書や承諾書の作成、不動産登記、贈与税の申告までワンストップで対応しています。安心して贈与を進めたい方は、ぜひ一度ご相談ください。

司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。合わせて、複数の資格を活かして会社設立や税理士サービスなどで多方面からクライアント様に寄り添うサポートを行っている。