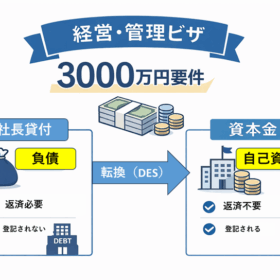Last Updated on 2025年8月4日 by 渋田貴正
小規模企業共済は、個人事業主や会社役員のための退職金制度であり、掛金が全額所得控除の対象となることから、節税手段として非常に人気があります。とくに会社を設立して間もない方にとっては、将来の備えとしても、今すぐの所得税の節税策としても魅力的な制度です。
しかし、この制度には明確な「加入資格」があり、誰でも加入できるわけではありません。誤って資格がない状態で加入してしまった場合、契約が無効とされ、過去の掛金はすべて返還されるものの、節税メリットも消失してしまいます。
そこで今回は、「小規模企業共済に加入できない典型的なケース」を事例付きでご紹介し、これから制度を活用しようと考えている方にとっての注意点をわかりやすくまとめました。
小規模企業共済への加入資格がない典型例一覧
小規模企業共済は、個人事業主や会社の役員など、自らリスクを取って事業を営む方々が、廃業や退職後の生活に備えて積立を行う制度です。とくに会社を設立して間もない方にとっては、将来の備えとしても、節税策としても有効な制度ですが、「誰でも加入できるわけではない」という点に注意が必要です。
小規模企業共済の加入資格がないケースの典型例を以下にまとめました。
| ケース | 具体例 | 加入できない理由 |
| ① 給与所得者 | Aさん:サラリーマンとして平日フルタイム勤務し、副業でECサイトを運営 | 主たる収入が会社の給与であり、自身の事業が本業ではないため |
| ② 非営利法人の役員 | Bさん:医療法人の理事長として病院を運営 | 医療法人などの非営利法人の役員は加入対象外のため |
| ③ 主たる事業が対象外 | Cさん:中規模で小規模企業共済の対象外の不動産会社の役員で、副業で小さなカフェを経営 | 中規模企業の役員が本業であり、小規模カフェは副業のため |
| ④ 保険会社の被雇用者 | Dさん:大手保険会社の営業職として勤務(正社員) | 雇用契約による業務であり、独立した事業とは認められないため |
| ⑤ 学生が本業 | Eさん:全日制高校に通いながら休日だけネットショップを運営 | 本業が「学業」であり、事業は副次的と判断されるため |
| ⑥ 役員未登記 | Fさん:設立したばかりの合同会社で自分が代表だが登記していなかった | 商業登記簿上に役員として記載がないと、共済では資格が認められないため |
| ⑦ 事業専従者 | Gさん:個人事業主の夫の事業を手伝っている妻(従業員ではない) | 夫の事業に専属で従事しているだけでは「事業主」とはみなされないため |
| ⑧ 他の退職金共済制度加入者 | Hさん:建設業退職金共済に加入中の建設会社社員 | 従業員として他の退職金制度に加入しているため対象外 |
| ⑨ 従業員数が多い | Iさん:常勤従業員を25人雇っている製造業経営者 | 小規模企業共済では製造業は「20人以下」の条件があり、超過のため加入不可 |
小規模企業共済への加入可否を分けるポイントとは?
加入できるかどうかは、「現在の肩書き」や「副業の有無」だけでなく、登記状況や従業員数など実態に基づいて総合判断されます。以下に、加入資格の可否に関する代表的な注意点を補足しておきます。
- 給与所得者(サラリーマン)は原則として加入不可。ただしパートやアルバイトであれば可能な場合あり。
- 医療法人、学校法人、NPO法人などの役員は加入対象外。
- 中規模以上の法人の役員と、小規模事業の経営を兼ねる場合は、主たる事業が小規模事業でなければ加入できません。
- 保険会社の雇われ営業マンや学生は加入できません。事業が主であることが必要です。
- 役員として登記されていない状態での加入は、審査ではじかれます。
- 事業専従者や配偶者による事業手伝いは、独立した事業主とはみなされません。
- 他の退職金制度との重複加入は、時期によって不適格になる場合があります。
- 常時雇用する従業員の数が上限を超えると小規模企業とみなされず、加入不可となります。
とくに、会社をこれから設立しようとしている方は、登記内容や役員構成、従業員数の設定を誤ることで、小規模企業共済に加入できなくなるリスクがあります。
たとえば、設立当初から家族以外の正社員を10人以上雇うようなケースでは、そもそも小規模企業の定義から外れてしまう可能性があるのです。節税制度を活かすには、最初の段階から税務・登記の観点をセットで検討することが極めて重要です。
小規模企業共済を活用するには、制度に適合する事業形態や登記構成を事前に整える必要があります。
当事務所では、会社設立サポートだけでなく、共済制度や節税制度の適用可否を踏まえた「実務的な設計」を得意としています。会社設立から節税設計、小規模企業共済の加入までワンストップで対応しておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。合わせて、複数の資格を活かして会社設立や税理士サービスなどで多方面からクライアント様に寄り添うサポートを行っている。