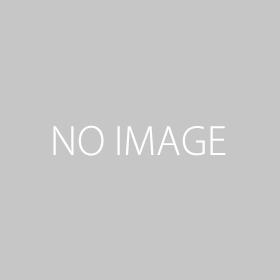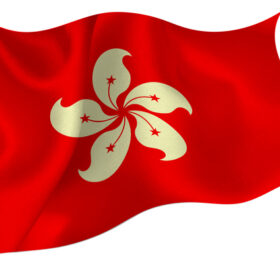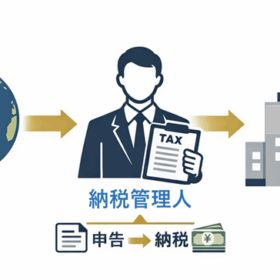Last Updated on 2026年1月7日 by 渋田貴正
株式会社や合同会社の解散事由の中に、「定款で定めた存続期間の満了」や「定款で定めた解散事由の発生」というものがあります。しかし、実際に会社を経営している中でこのような解散まで見据えて定款を作成している事例は多くありません。実務でも、実際にこれらの定めを置いた結果として解散に至るケースは決して多くなく、多くの解散は株主総会の決議(合同会社であれば総社員の同意)に依るケースがほとんどです。
ただし、「使われていない=不要」というわけではなく、将来の相続や資産承継を見据えた設計として、あえて定款に落とし込むという考え方は十分に使い道があります。存続期間や解散事由には「こういう使い方が考えられる」という視点で整理していきます。
存続期間と解散事由の基本的な違い
まず整理しておきたいのは、存続期間と解散事由は似て非なるものだという点です。存続期間は「いつまで会社を存続させるか」を時間軸で定めるものです。一方、解散事由は「どのような出来事が起きたら会社を解散させるか」を条件として定めるものです。いずれも株式会社・合同会社ともに定款で定めることができ、法的な効力を持ちます。
この段階で「そこまで決めると縛りが強すぎるのでは」と感じる方もいますが、実務上は決めていなかったために判断がつかず、例えば会社を残された相続人全員が困るという場面も目につきます。定款は今の自分のためではなく、将来の関係者のためにある、という視点が重要です。
存続期間や解散事由を定める具体的な事例
存続期間を定める事例
ケーススタディ: 期間限定プロジェクト会社
不動産開発や再生可能エネルギー事業など、期間が明確なプロジェクトでは、存続期間を定めた会社設立がよく検討されます。たとえば「太陽光発電設備を設置し、20年間運営する」ことが前提の事業であれば、存続期間を20年と定めることで、事業終了後の出口が明確になります。解散時期が明確であれば、清算や残余財産の分配も計画的に進められます。税務上も、いつまで事業所得が発生するのかが見通しやすくなり、投資家や金融機関への説明がしやすくなる点は大きなメリットです。
ケーススタディ: 資産管理会社を一定期間で役割終了させる設計
たとえば、親が保有する複数の不動産を管理するために設立する資産管理会社を想定します。この会社は、相続対策や管理の効率化を目的として設立されますが、次世代まで永久に存続させる必要があるとは限りません。
このような場合、「設立から30年間を存続期間とする」といった定めを置くことで、次の世代が「この会社をどうするか」で悩む可能性を減らすことができます。実際に30年後に必ず解散するかどうかは別として、出口が一度言語化されているだけで、相続時の意思決定は格段にしやすくなります。これは実際に解散を狙うというより、「考える基準点を定款に置く」という使い方です。
ケーススタディ:相続を見据えた一時的な器としての会社
相続税申告や遺産整理の過程で、一時的に法人を使って資産を管理するケースもあります。この場合、「相続開始から○年以内」という形で存続期間を設定し、役割が終わったら自然に整理するという発想も考えられます。
実務上は、申告後も会社を存続させるケースが大半ですが、「いつまで使う会社なのか」を設立時点で意識しているかどうかは大きな違いです。結果として存続させるにしても、定款に存続期間があることで、税務・登記の見直しを行うタイミングを作ることができます。
解散事由を定める具体的な事例
ケーススタディ: 特定の人を中心とした会社
代表者の専門性や人脈に強く依存する会社では、「この人がいなくなったら会社として意味をなさない」というケースがあります。そのような場合、「代表取締役が退任したとき」や「特定の社員が退社したとき」を解散事由として定めることが検討されます。感情的には少しドライに聞こえるかもしれませんが、後継者問題を先送りにしないという意味では非常に現実的な選択です。相続や事業承継の場面で「会社をどうするか分からない」という状態を避けられる点は、登記実務・税務実務の両面で評価できます。
ケーススタディ: 被相続人の生存を前提とした会社
オーナー個人の判断や関与が不可欠な資産管理会社では、「代表者が亡くなった後も同じ形で続けるのが適切か」が問題になります。そこで、「代表取締役が死亡したとき」を解散事由として定めるという設計が考えられます。
この定めがあるからといって、必ずその時点で会社を解散しなければならないわけではありません。実務では、相続人が改めて定款変更をして会社を存続させるという選択肢も残ります。重要なのは、「何も決めていない状態」ではなく、「一度は立ち止まる設計」になっている点です。これは相続開始直後の混乱期において、極めて実務的な意味を持ちます。
ケーススタディ: 相続人間の合意形成を前提とした合同会社
相続人複数名が社員となる合同会社では、全員の協力関係が前提になります。そのため、「社員間で一定期間、全員の合意が得られない状態が続いた場合」を解散事由として定めることも理論上は可能です。また、特定の相続人が、第三者の影響下で会社を実質的に支配しようとするなど、社員間の信頼関係を根本から損なう行為を行った場合を解散事由として定めるという設計も、理論上は考えられます。これは特定の私生活上の行為を制限する趣旨ではなく、あくまで会社の私物化を防ぐための安全弁として位置づけられるものです。
実際にこの条項が発動して解散に至るケースは多くありませんが、「最終的には解散という選択肢もある」ということが定款上明示されているだけで、無用な膠着状態を避けやすくなります。これは解散を目的とした条文ではなく、交渉を促すための条文といえます。
結局どんな会社が存続期間や解散事由を定めるのに適しているか
存続期間満了や解散事由の発生により会社が解散した場合、解散登記が必要となり、その後は清算手続に移行します。税務上も、解散事業年度の法人税申告や、清算所得の申告が問題になります。これらは「想定していなかった解散」で起きると、実務負担が一気に増えます。
逆にいえば、あらかじめ定款で存続期間や解散事由を定めている会社は、「そのとき何が起きるか」を事前に把握しやすく、税務・登記の段取りを組みやすい会社でもあります。
| 向いている会社のタイプ | 特徴 | 理由 |
|---|---|---|
| 役割が明確な会社 | 不動産管理、資産保有、特定事業の運営など、目的が限定されている | 会社の役割が終わるタイミングを想定しやすく、出口を定款で示すことで将来の整理が容易になります |
| 相続が避けられない会社 | 資産管理会社やファミリー会社など、将来必ず相続人が関与する | 相続開始後に「会社をどうするか」で迷わないための判断基準を、定款に残すことができます |
| 特定の人に依存している会社 | 代表者や特定社員の判断力・信用・人脈に強く依存している | その人物が関与できなくなった後に、一度整理する選択肢を制度的に用意できます |
| 社員間の協力関係が前提の会社 | 相続人複数名が社員となる合同会社など | 関係性が破綻した場合の最終的な出口を用意することで、無用な膠着状態を避けやすくなります |
存続期間や解散事由を定款で定めることは、会社を早く終わらせるための制度ではありません。むしろ、相続や資産承継という不確実性の高い局面で、関係者が迷わないための設計図を残す行為です。株式会社や合同会社の定款は、設立時よりも「その会社が役割を終えるとき」に真価を発揮します。設立段階で少しでも違和感があれば、登記と税務の両面から整理できる専門家に一度相談しておくことをおすすめします。当事務所では、形式論ではなく「将来困らないか」という一点に絞って、定款設計のご相談をお受けしています。

司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。合わせて、複数の資格を活かして会社設立や税理士サービスなどで多方面からクライアント様に寄り添うサポートを行っている。