Last Updated on 2025年12月31日 by 渋田貴正
合同会社では、業務執行社員や代表社員を定めることで、会社の意思決定や対外的な行為を整理することができます。しかし、これらの制度は言葉のイメージで理解されがちであり、実務では「誰がどこまでやってよいのか」を巡って業務執行社員と業務執行社員以外の社員の間でトラブルになることが少なくありません。
特に多いのが、「業務執行社員がいるのだから、社員は何もしてはいけない」「代表社員がいるのだから、他の業務執行社員は口を出せない」といった理解です。実際には、それぞれのポジションにおける業務の区分はもっと厳密に定められています。合同会社運営において、こうしたもめごとを無くすためにも、それぞれの立場における違いをあらかじめ明確にしておく必要があります。
業務執行社員がいる場合の業務執行社員以外の社員の仕事の範囲とは?
業務執行社員が定められている合同会社では、業務執行社員でない社員が自ら行える行為は、原則として実務・補助行為に限られます。
業務執行社員がいる場合、それ以外の社員は、会社を代表して契約を締結したり、会社の名で対外的な意思決定を行ったりすることはできません。これらは「業務」または「常務」に該当し、業務執行社員の権限だからです。
もっとも、社員が何もできないわけではありません。営業活動、現場作業、経理入力、資産管理の実務、資料作成、業務執行社員への助言や提案などは、いずれも実務として行うことができます。これらは会社を法的に拘束する行為ではなく、業務執行権限を必要としません。
また、業務執行社員でない社員であっても、業務執行および財産の状況について調査する権利は、会社法条により明確に保障されています。業務を行う権限と、会社の状況を知る権利は別の次元の話であり、社員は自らの持分の価値を守るための情報取得を排除されることはありません。業務執行社員以外の社員は、業務執行には関与しないものの、経営陣として業務や財産の状況を調査できる立場にあります。この点は、業務執行を行わずに監督機能を担う株式会社の社外取締役の役割に、考え方としては近いといえるかもしれません。
業務執行社員がいる場合の業務執行社員の仕事の範囲とは?
業務執行社員は、会社の業務を執行する権限を有しており、業務・常務・実務のいずれについても行うことができます。
重要な業務の決定はもちろん、定型的・軽微な対外行為である常務についても、業務執行社員は単独で行うことができます。また、実務については、自ら行っても、社員や従業員に任せても構いません。
ただし、業務執行社員が複数いる場合には、業務の決定は原則としてその過半数による決定が必要になります。業務執行社員だからといって、すべてを一人で決められるわけではありません。
業務執行するかどうか分からない社員を業務執行社員にすることは可能?
実際に日常の業務執行を行うかどうか分からない社員であっても、業務執行社員にすることは可能です。むしろ、単に可能というだけでなく、合同会社の制度設計として合理的なケースも少なくありません。
実際に日常の業務執行を行うかどうか分からない社員であっても、業務執行社員にする最大の理由は、重要な業務の意思決定に、制度として関与できる立場を確保できる点にあります。業務執行社員が複数いる場合、業務の決定は、原則として業務執行社員の過半数によって行われます。業務執行社員に含まれていなければ、たとえ社員であっても、この決定プロセスには参加できません。
つまり、実務をしているかどうかにかかわらず、資産運用方針や重要な契約、経営の方向性といった場面で、「最終的な判断に加われる地位」を確保するという意味で、業務執行社員にしておく実益があります。
また、業務執行社員に含まれていない場合、「知らないうちに重要なことが決まっていた」「結果だけ後から知らされた」という状況が生じやすくなります。調査権はあっても、業務の決定権限そのものは別だからです。あらかじめ業務執行社員として位置づけておくことで、経営判断から制度的に排除される状態を防ぐことができます。
さらに、合同会社では、設立時点と将来とで社員の関与度が変わることも珍しくありません。現在は遠隔地にいる、あるいは実務を担当していない社員であっても、将来的に業務執行に関与する可能性がある場合には、最初から業務執行社員にしておく方が実務上は柔軟です。後から業務執行社員に加える場合には、定款変更や登記手続が必要になるためです。
このように、業務執行社員にするかどうかは、「今、実際に業務をしているか」ではなく、「重要な意思決定に制度として関与させるか」という視点で判断すべき問題だといえます。むしろ、業務とは単に手を動かす作業を指すものではなく、会社としてどのような行為を行うかを決める意思決定も、その重要な業務の一部と考えると、業務執行社員に入れるべき社員の幅も広くなるでしょう。
代表社員がいる場合の代表社員以外の業務執行社員の仕事の範囲とは?
代表社員が定められている場合、この点は単なる運用の問題ではなく、法的効果として重要な違いが生じます。
会社法では、業務執行社員は持分会社を代表すると定められていますが、他に持分会社を代表する社員を定めた場合には、その限りではないとされています。つまり、代表社員が定められている場合、代表社員以外の業務執行社員は、原則として代表権を有しないことになります。
| 会社法 (持分会社の代表) 第599条 1.業務を執行する社員は、持分会社を代表する。ただし、他に持分会社を代表する社員その他持分会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。 |
このため、代表社員がいる合同会社では、他の業務執行社員は業務執行権限自体は有していても、会社を代表して契約を締結するなどの対外的行為を当然に行えるわけではありません。代表権は、代表社員に集中するのが原則です。
実務上、代表社員の関与を前提とした契約運用がなされることが多いのは、単なる慣行ではなく、この代表権の所在を踏まえた法的整理に基づくものといえます。
| 業務執行社員 | 代表社員 | |
|---|---|---|
| 代表社員がいない場合 | ・業務執行権あり ・代表権あり(各自代表が原則) ・業務、常務、実務を行うことができる |
ー |
| 代表社員がいる場合 | ・業務執行権あり ・代表権なし(原則) ・業務、常務、実務は行えるが、会社を代表する対外行為は不可 |
・業務執行権あり ・代表権あり ・業務に関する一切の裁判上・裁判外行為が可能 |
合同会社は柔軟な制度である反面、業務執行社員や代表社員の権限を感覚的に理解してしまうと、「勝手に契約していた」「知らない間に会社が拘束されていた」といった深刻なトラブルにつながりやすくなります。
誰が業務を決定し、誰が会社を代表し、誰が実務を行うのか。この整理は、定款の文言と会社法の構造を踏まえて行う必要があります。
合同会社の業務執行体制や代表社員の設計は、登記だけ、税務だけで完結する話ではありません。当事務所では、会社法の解釈、登記実務、税務上の扱いを踏まえ、実際の運用まで見据えた権限設計をサポートしています。業務執行社員や代表社員の権限について少しでも違和感がある場合は、早めに専門家へご相談ください。

司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。合わせて、複数の資格を活かして会社設立や税理士サービスなどで多方面からクライアント様に寄り添うサポートを行っている。


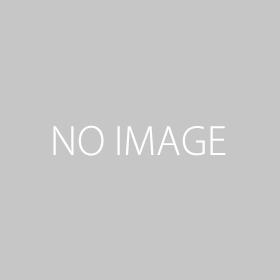
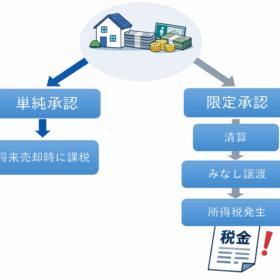
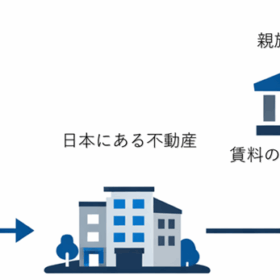
時課税-280x280.png)

