Last Updated on 2025年12月21日 by 渋田貴正
被相続人が賃貸アパートやマンションに住んでいた場合、相続放棄を考え始めた相続人が、真っ先に直面しやすいのが不動産会社や大家さんからの連絡です。
「このままだと家賃が発生しますので、早めに解約手続きをお願いします」「相続放棄をされるとしても、解約だけはしてもらえませんか」このように言われると、「放っておく方が迷惑なのでは」「解約くらいならしても問題ないのでは」と感じる方も多いと思います。相手の言い分ももっともに聞こえるため、対応に迷うのは無理もありません。
しかし、相続放棄を前提に動いている場面では、「相手にとって自然なお願い」と「相続放棄との関係で許される行為」は、必ずしも一致しません。このズレを見極めるための重要な判断軸が、その行為が「保存行為」に当たるのか、それとも「処分行為」に当たるのか、という考え方です。
相続放棄中に許される保存行為とは
相続放棄を予定している相続人が行っても問題にならないのは、相続財産の現状を維持し、価値の減少を防ぐための行為、いわゆる保存行為です。保存行為は、「相続人として積極的に権利を行使した」と評価されにくく、相続放棄との両立が認められています。ポイントは、ざっくりいうと「新しい法律関係を作らない」「既存の関係を終わらせない」という点にあります。
では、不動産の賃貸借契約があるケースで、どのような行為が保存行為に該当するのでしょうか。実務上、比較的安全と考えられているものを整理すると、次のようになります。
| 行為の内容 | 保存行為に該当するか | 理由 |
|---|---|---|
| 室内の施錠・鍵の保管 | 該当する | 第三者の侵入や損壊を防ぐための現状維持行為 |
| 換気・通水など最低限の管理 | 該当する | 建物の劣化や事故を防止する目的に限られる |
| 郵便物の受領・保管 | 該当する | 権利義務を変動させず、管理目的にとどまる |
| 室内に残された動産を移動させて一時保管 | 該当する | 処分せず、現状を維持する限度であれば許容される |
| 賃貸借契約の解約 | 該当しない | 既存の契約を終了させることは保存行為を超えた処分行為に該当しうる |
| 室内に残された動産を売却、廃棄 | 該当しない | モノの処分行為そのもの |
保存行為はいずれも、「契約関係そのものには手を付けない」「あくまで傷まないように守る」行為です。いわば、法律的には「触らず、壊さず、増やさず」というスタンスが保存行為の核心と言えます。
なぜ賃貸借契約の解除は保存行為に当たらないのか
ここで、本題である賃貸借契約の解除との比較をしてみましょう。賃貸借契約の解除は、被相続人が生前に締結していた契約関係を終了させる行為です。これは、単なる管理や維持ではなく、権利義務そのものを消滅させる法律行為に当たります。
家賃の発生を止めたい、大家さんや不動産管理会社から「早めに解約手続きをしてください」と言われている、このまま何もしないと自分が責任を負わされるのではないかと不安になる。相続放棄を考えている相続人の立場からすれば、こうした状況に置かれて戸惑うのはごく自然なことですし、「とりあえず解約だけでもしておいた方がいいのでは」と感じてしまう方が多いのも無理はありません。
しかし、相続放棄との関係では、その動機がどれほど合理的であったとしても、行為の法的評価が変わることはありません。賃貸借契約の解除は、相続財産の現状を維持するための行為ではなく、被相続人が生前に負っていた契約関係そのものを終了させる行為だからです。
保存行為が「今ある状態を壊さないための行為」だとすれば、契約解除は「その状態に区切りをつける行為」といえます。この違いは大きく、相続放棄が認められるかどうかを左右しかねない決定的な差になります。
もっとも、理論上、例外的に整理できる余地が全くないわけではありません。例えば、賃貸借契約書の中に「賃借人が死亡した場合には本契約は当然に終了する」といった条文が明確に定められており、その条文が有効と解される場合には、被相続人の死亡時点ですでに契約関係が終了していると評価される余地があります。
このようなケースでは、相続人が行うのは契約を終了させるための意思表示ではなく、「契約はすでに終了している」という事実関係の確認にとどまります。その限度であれば、新たに権利義務を変動させる行為とはいえず、保存行為に近い性質として整理できる可能性はあります。
ただし、実務上、居住用の賃貸借契約において、死亡を理由に当然終了すると明記されている条文はかなり例外的です。多くの契約では、賃借人の死亡によって当然に契約が終了するわけではなく、相続人が賃借人の地位を承継するのが原則とされています。
また、「死亡時は解約できる」「解約の申し入れができる」といった表現にとどまる場合には、相続人の意思表示が必要となり、その時点で処分行為と評価される可能性が高くなります。この点は、「すでに法律上終了している契約なのか」「終了させるための行為が必要なのか」という構造の違いで、評価が決定的に分かれます。
相続放棄の実務では、少しでも相続人の判断や意思表示が介在する余地がある場合には、安全側に倒して処分行為と考えるのが基本です。
賃貸借契約の解除が保存行為に当たると評価できる場面は、理論上は想定できても、現実には極めて限定的であるという点を押さえておく必要があります。
保存行為と処分行為の違いを、賃貸借契約の文脈で整理すると次のとおりです。
| 区分 | 保存行為 | 賃貸借契約の解除 |
|---|---|---|
| 目的 | 現状維持・劣化防止 | 契約関係の終了 |
| 権利義務への影響 | 影響なし | 権利義務が消滅する |
| 相続放棄への影響 | 原則なし | 処分行為と評価される可能性が高い |
この比較を見ると、賃貸借契約の解除が保存行為に含まれない理由は、かなり明確です。
ここでよく出てくるのが、「相続人ではなく、弁護士や司法書士が解約すれば処分行為に該当しないのでは?」という疑問です。
しかし、この点についても結論は変わりません。弁護士や司法書士が行う解約手続きは、相続人の代理として行われるものです。代理人が行った法律行為は、本人が行ったのと同一の効果を持ちます。保存行為か処分行為かの判断は、「誰がやったか」ではなく、「何をやったか」で判断されます。
ここは、管理会社側と認識がズレやすいポイントでもあります。
相続放棄、相続財産の管理、賃貸借契約との関係整理でお悩みの方は、登記と相続実務を熟知した当事務所へぜひご相談ください。状況に応じて「何をするか」だけでなく、「何をしないか」まで含めた、安全な判断をご提案いたします。

司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。合わせて、複数の資格を活かして会社設立や税理士サービスなどで多方面からクライアント様に寄り添うサポートを行っている。




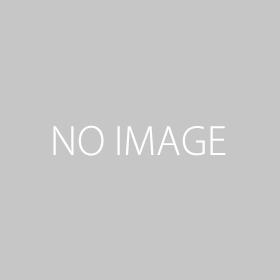


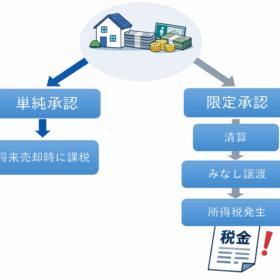
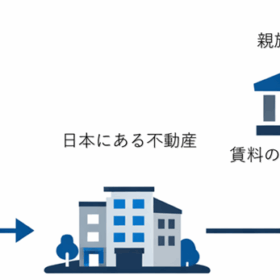
時課税-280x280.png)

