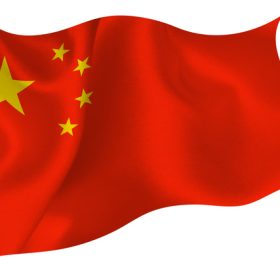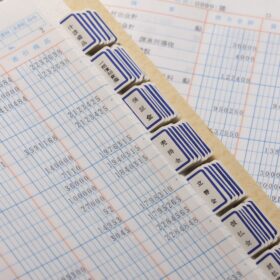Last Updated on 2025年9月13日 by 渋田貴正
当事務所には、次のようなご相談をいただくことがありました。
「父が海外旅行中に亡くなりました。亡くなった場所が外国なので、日本の裁判所で相続放棄はできないのではないでしょうか?」
こうしたご心配をされる方は少なくありません。ですが、実際にはそのように心配する必要はありません。相続放棄の手続きを日本の家庭裁判所で行えるかどうかは、「亡くなった場所」ではなく「被相続人の住所(最後に住んでいたところ)」で判断されるのです。
つまり、亡くなられた場所が日本国内か海外かという点は大きな問題ではありません。大切なのは、亡くなる直前にどこに住所を置いていたかで管轄が決まる、という点です。
相続放棄の管轄は「住所」で決まる
家庭裁判所に相続放棄を申述できるかどうかは、家事事件手続法第3条の11で定められています。
その条文を簡単に整理すると、以下のとおりです。
| 被相続人の状況 | 日本の裁判所に管轄権 | 備考 |
| 相続開始時に日本国内に住所がある | あり | 最も明確なケース |
| 住所はないが居所が日本国内にある | あり | 海外長期滞在中でも可 |
| 住所・居所不明だが、過去に日本に住所があった | あり | 最後の住所が日本であれば対象 |
| 日本に住んでいたが、その後外国に住所を有した | なし | 法律で除外される |
| 相続開始時に外国に住所のみ | なし | 原則、日本での相続放棄は不可 |
このように、管轄の判断基準はあくまで「住所」であり、「死亡場所」そのものは考慮されません。
例えば、被相続人が東京都に住んでいた方であれば、たとえハワイ旅行中に亡くなったとしても、管轄は「東京家庭裁判所」となります。逆に、数年前に日本から海外へ完全に移住し、現地に住所を移していた方の場合は、死亡場所が日本国内であっても日本の裁判所では相続放棄ができないのです。
- ケース1:日本在住者が海外旅行中に死亡
→ 最後の住所は日本なので、日本の家庭裁判所に相続放棄を申述可能。 - ケース2:日本在住だったが、数年前に海外に移住して現地住所を取得。その後一時帰国中に死亡
→ 最後の住所が外国なので、日本の裁判所では相続放棄不可。 - ケース3:住所移転直後で、住民票は残っていなかったが実質的に日本に居住していた
→ 「居所が日本」と評価されるため、日本の裁判所で相続放棄可能。 - このように、住所と死亡地を区別して考えることが重要です。
「死亡した場所」で相続放棄の管轄権が決まると勘違いする理由の一つは、死亡届や火葬許可など、戸籍・行政上の手続きでは「死亡地」が必ず記録されるためです。これにより、相続放棄でも死亡地が基準になると誤解しやすいのです。
しかし、相続放棄は裁判所への法的申述であり、管轄は法律に基づいて厳密に「住所」で決まります。つまり、行政上の死亡届と、家庭裁判所での相続放棄はまったく別の仕組みで動いているのです。
相続放棄の実務上の流れ
「住所」が基準になることを理解したうえで、相続放棄の流れを確認しておきましょう。
| 手続きの段階 | 内容 |
| 管轄の確認 | 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所を確認 |
| 申述書の提出 | 相続放棄申述書を作成し、戸籍一式とともに提出 |
| 提出方法 | 郵送または代理人を通じて提出可能 |
| 期限 | 相続を知った日から3か月以内(民法915条) |
| 裁判所からの通知 | 「相続放棄申述受理通知書」が申述人宛に送付される |
このとき、被相続人の最後の住所が日本国内にあれば、死亡地が海外であっても問題なく手続きできます。
相続放棄は「死亡場所」ではなく「住所」が基準になるという点を理解していただくことがとても大切です。しかし実際のケースでは、戸籍や住民票の確認、海外からの書類送付、翻訳など、手続きは煩雑になりがちです。
当事務所では、税理士・司法書士として相続放棄に必要な戸籍収集から申述書作成、家庭裁判所への提出、さらに登記や税務に関するご相談までワンストップでサポートしています。海外在住の方や、国際的な事情を含む相続でお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。

司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。合わせて、複数の資格を活かして会社設立や税理士サービスなどで多方面からクライアント様に寄り添うサポートを行っている。