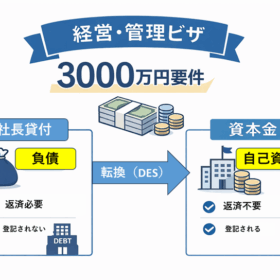Last Updated on 2025年10月28日 by 渋田貴正
不動産を所有して家賃収入を得ている方、あるいは今後得たいと考えている方にとって、「どのくらいの家賃収入があれば法人で保有したほうがよいのか」という疑問はよくあるテーマです。
私は税理士・司法書士として多くのオーナー様のご相談を受けていますが、単に「家賃収入の多寡」だけで判断することはできません。家賃収入はあくまで「売上」の一側面にすぎず、得た家賃=売上をどのように役員報酬を配分し、どのような形で法人を維持していくかが大きな判断材料となります。
不動産の個人所有と法人所有の違い
まず、個人で不動産を持つ場合と法人で持つ場合の税務上の違いを整理しましょう。
個人所有の場合
個人が賃貸不動産から得る家賃収入は「不動産所得」として所得税と住民税の対象になります。
個人の場合、所得が増えるほど税率も上がる「累進課税制度」が適用され、最高税率は55%(所得税45%+住民税10%)にも達します。
また、給与所得など他の所得と合算して課税されるため、一定以上の所得がある人は税負担が重くなりがちです。
個人では、家族に給与を支払う仕組みが青色事業専従者給与など限られるため、所得を分散しづらい点もデメリットです。
法人所有の場合
法人の場合は、法人税・法人住民税・事業税などを合わせた実効税率が概ね30%前後です。
また、役員報酬として支払った金額を損金(経費)にできるため、法人の利益を減らして税金を抑えることが可能になります。
ただし、法人を維持するには毎年の決算申告費用や法人住民税の均等割(最低でも年間約7万円)などの固定コストがかかります。
| 区分 | 個人所有 | 法人所有 |
|---|---|---|
| 税率 | 累進課税(所得が増えると税率上昇) | 一定の法人税率(中小企業は約30%前後) |
| 節税方法 | 経費にできる範囲が限られる | 役員報酬・家族給与などで分散可能 |
| 手続き | 確定申告のみで完結 | 決算・法人申告・登記などが必要 |
| 維持コスト | ほぼなし | 法人住民税・会計費用など固定コストあり |
| 相続対策 | 個人資産として直接相続 | 株式として承継しやすい(分割もしやすい) |
どのくらいの家賃収入が法人にすべき目安か
一般的には、「年間の課税所得(収入-経費)が800万円〜900万円を超えるあたりから法人化のメリットが出やすい」と言われています。この水準を超えると、個人の所得税率が33%前後になり、法人化によって税率差の恩恵が出やすくなるためです。
例えば、家賃収入が1,200万円あり、経費や減価償却を引いた課税所得が900万円の場合、個人所有のままだと所得税・住民税を合わせて300万円超の税負担となるケースもあります。
一方で、法人化して役員報酬を設定すれば、法人と個人に税負担を分けることができ、合計の税金が抑えられることがあります。
しかし、実際にはこうした数字に明確な数学的な根拠があるわけではありません。実際にはExcelなどに落とし込んで個々のケースをシミュレーションすることで数値の形で表すことで法人化の目安を判断すべきです。
収入だけでなく、役員報酬や配分の視点も
とはいえ、家賃収入の多寡だけで法人化を判断するのは危険です。
不動産保有会社(いわゆる資産管理法人)は、一般的な事業会社と異なり「資産運用」の性格が強く、役員報酬を「生活費のために決める」というよりも、「税務上どの形が個人と法人を合わせて最適か」という観点から決めるケースが多いのが実情です。
したがって、法人化の検討にあたっては「家賃収入をいくら得ているか」ではなく、「そのうちどの程度を役員報酬として支払い、どの程度を法人に残したいか」を明確にすることが重要です。
役員報酬を高く設定すれば個人の所得が増えて税率が上がりますが、法人の利益は減り法人税が軽くなります。逆に報酬を低くすれば個人税率は下がるものの、法人の利益が増えて法人税が増える——このバランスを総合的に見極める必要があります。
また、家族を役員にして役員報酬を分散することで、合計税負担を下げることも可能です。ただし、実際に業務をしていない家族に報酬を支払うと税務上否認されるおそれがあるため注意が必要です。
法人化のためのコストを含めた検討も必要
法人化には次のようなコストや手続きが発生します。
- 法人設立登記の登録免許税(最低15万円前後)
- 定款認証費用(株式会社の場合)
- 不動産を個人から法人に移す場合の登録免許税・不動産取得税
- 毎年の決算・法人税申告・顧問税理士費用
これらの初期費用・維持費を合計し、節税効果と比較して「元が取れるか」を判断することが重要です。
特に、法人に不動産を移す際は、売買や出資の形に応じて譲渡所得税や消費税の課税が発生する場合もあります。司法書士や税理士に相談しながら、登記と税務の両面を調整して進めるのが安全です。
収入規模別の目安
| ケース | 年間家賃収入 | 経費差引後の所得 | 検討ポイント | 判断の目安 |
| A:ワンルーム1棟 | 約500万円 | 約300万円 | 所得税率は低く、維持コストが重い | 個人所有で十分 |
| B:複数棟・1,200万円 | 約900万円 | 所得税率が高くなりやすい | 法人保有を検討 | |
| C:大規模・2,000万円超 | 約1,500万円〜 | 節税・承継の観点が重要 | 法人化を積極的に検討 |
上記はあくまで目安であり、実際にはローン残高、減価償却、共有名義の有無などにより最適な形は変わります。
法人化する際には、次の点にも留意が必要です。
法人化によって節税のチャンスが広がる一方で、登記や税務の取扱いを誤ると、思わぬ税負担や将来のトラブルにつながることもあります。
以下の点は、法人化を検討する際に特に注意すべきポイントです。
役員報酬の妥当性
法人の利益を減らして税金を抑える目的で、過度に高い役員報酬を設定すると「損金不算入」と判断されるおそれがあります。
税務上、役員報酬として認められるのは「定期同額給与」や「事前確定届出給与」など、形式・金額・支払時期が適正に定められている場合に限られます。
たとえば、年度途中で自由に金額を上下させると、その増額部分が経費として認められず、法人税が増えてしまうことがあります。
また、不動産保有会社の場合、役員報酬は生活費のためではなく、「税負担をどう分散させるか」という設計上の意味が強くなります。
どの程度を法人に残し、どの程度を役員報酬として個人に移すかを、長期的な視点でシミュレーションすることが大切です。
所有権移転登記の扱い
個人が持つ不動産を法人に移す際は、「売買」または「現物出資」のいずれかの方法を選びます。
それぞれ登記原因や税務処理が異なり、どちらを選ぶかで税金の負担や評価額の扱いが変わります。
売買による移転の場合
- 法人は個人から不動産を購入した形となり、登録免許税(固定資産税評価額の2%)と不動産取得税(3%)が発生します。
- 個人側には「譲渡所得税」が課税され、購入時の取得費や売却費用を差し引いた差額が課税対象になります。
現物出資による移転の場合
- 個人が不動産を出資として法人に提供し、代わりに株式を受け取る形です。
- 出資時点の評価額によっては、譲渡があったものとみなされ課税される場合があります。
- 現物出資では、評価・登記・会計処理の整合性を確保することが重要です。
どちらの方法でも、登記簿上の名義変更が必要です。
また、金融機関からの融資を受けている物件の場合、所有者変更の際には銀行の承諾が必要となるケースもあるため注意が必要です。
将来の相続・承継
法人化は、将来の相続・事業承継にも影響を与えます。
不動産を個人名義で所有している場合、その物件自体が相続財産として評価されます。
一方、法人化すると不動産は法人の資産となり、相続の対象は「法人の株式」となります。
一般的に、不動産を直接相続するよりも、法人株式として承継した方が分割が容易で、共有状態を避けやすいというメリットがあります。
ただし注意点として、法人に利益や含み資産が多い場合、株式の評価額が高くなり、結果的に相続税が増えることもあります。
相続を見据えた法人設計では、
- 株主構成をどのようにするか
- 役員を誰にするか
- 利益をどの程度法人に残すか
といった点を早い段階から設計しておくことが重要です。
法人化が長期的な資産承継の安定につながる一方で、短期的な節税目的のみで行うと、将来の税負担が逆に増えることもあるため、慎重な判断が求められます。
不動産の法人化は、「家賃収入がいくらか」という単純な判断ではなく、役員報酬の配分・節税バランス・登記コスト・将来の承継までを見据えた総合設計が必要です。
特に不動産保有法人は、事業というより「資産管理」の性格が強いため、生活費ベースではなく税務効率を軸に役員報酬を設計するのが一般的です。
当事務所では、不動産賃貸経営の法人化について、税務と登記の両面からワンストップでご相談を承っております。
現在の家賃収入や将来の計画に応じて、最も有利で安全な形をご提案いたします。ぜひお気軽にお問い合わせください。

司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。合わせて、複数の資格を活かして会社設立や税理士サービスなどで多方面からクライアント様に寄り添うサポートを行っている。