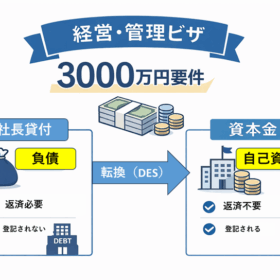Last Updated on 2025年10月25日 by 渋田貴正
「時効」とは、一定の期間が経過すると法律上の権利が消滅したり、逆に新たな権利を取得できる制度のことです。長期間権利を主張しない人よりも、現実に社会で権利を行使している人を保護するという考え方に基づいています。民法上の時効は大きく分けて2種類あります。
| 種類 | 内容 | 例 |
| 消滅時効 | 一定期間が過ぎると権利が消える | 借金の返済請求、家賃の支払い請求など |
| 取得時効 | 一定期間占有すると権利を得る | 他人の土地を長年使用して自分の所有にする場合など |
つまり、「権利を失う時効」と「権利を得る時効」があるのです。
2020年の民法改正で変わった消滅時効制度
以前は「商人は5年」「医師は3年」「弁護士は2年」といったように、職業や債権の種類ごとに異なる消滅時効期間が細かく規定されていました。そのため、一般の方にはどの取引が何年で時効で消滅するのか非常に分かりにくい制度でした。そこで、2020年4月の民法改正では、消滅時効制度の考え方が大きく見直され、非常にシンプルな形に変更されました。
| 民法 (債権等の消滅時効)
|
消滅時効の改正の背景と趣旨
- 生活・経済の変化への対応
取引が多様化し、誰もが商取引を行う時代になったため、職業ごとの区別が時代に合わなくなりました。 - 権利者の保護と法的安定の両立
権利を行使する人が保護される一方、いつまでも請求されるリスクを減らし、取引の安定を図るためです。 - シンプルで一貫したルールへ
「いつから」「何年で」時効が完成するのかを明確にするため、一般債権の時効期間を統一しました。
消滅時効の改正前後の比較表
| 項目 | 改正前(旧民法) | 改正後(2020年4月~) |
| 一般債権の時効期間 | 原則10年、職業別短期時効あり(例:商人5年、医師3年など) | 権利を行使できると知った時から5年、または行使できる時から10年のいずれか早い方 |
| 起算点 | 「権利を行使できる時」 | 「権利を行使できると知った時」を新設 |
| 短期時効 | 職業ごとに異なる特例多数 | 原則廃止、統一 |
| 時効中断 | 「中断」という表現 | 「更新」へ変更し、手続き明確化 |
| 用語整理 | 援用・停止など曖昧な規定 | 「完成猶予」「更新」として明確化 |
以前は「知ってから何年」という考え方がなかったため、たとえば被害に気づかないまま10年経っていた場合には、請求する前に時効が完成してしまうこともありました。改正後は「権利を行使できると知った時から5年」というルールが導入され、柔軟で実態に即した判断が可能になりました。また、時効期間の統一により、個人間の貸付でも会社間の取引でも基本的には5年または10年というシンプルな判断ができるようになっています。この変更により、契約書や請求の管理が格段に行いやすくなりました。
消滅時効の具体例と期間
消滅時効は、お金の請求や債権管理の現場で最も重要な制度です。次のように整理できます。
| 債権の種類 | 時効期間 | 起算点 |
| 通常の債権 | 権利を行使できると知った時から5年、または行使できる時から10年 | 借金の返済期日など |
| 例外:不法行為による損害賠償 | 被害と加害者を知った時から3年(または行為時から20年) | 交通事故など |
たとえば、貸したお金の返済日から5年経過した後、債務者が「もう時効だから払わない」と主張すれば、裁判でも支払いを求めることはできません。このように「時効の援用(主張)」があって初めて効果が生じます。
不動産登記と取得時効
もう一つの時効である「取得時効」は、不動産登記の現場で非常に重要です。他人名義の土地でも、20年間所有の意思をもって平穏・公然と占有した場合には、その土地の所有権を取得できると民法162条で定められています。たとえば、境界が不明確な土地を自分の敷地と誤信して20年以上使い続けた場合、裁判手続きを経て「取得時効を原因とする所有権移転登記」を申請できるケースがあります。ただし、単なる「借りていた」「知らずに使っていた」では成立しません。実際に所有の意思をもって管理・維持していたことが求められます。
時効の更新と中断の仕組み
時効は、ただ時間が経てば自動的に完成するわけではありません。進行中に一定の行為があれば「リセット」されることがあります。改正前は「時効の中断」と呼ばれていましたが、現在は「時効の更新」として整理されています。
時効を止める・リセットする主な方法
| 方法 | 内容 | 効果 |
| 裁判上の請求 | 裁判を起こすことで進行が止まる | 判決確定後に再び新しい期間が進行 |
| 内容証明郵便による請求 | 債務者に請求意思を明確に伝える | 通常6か月間、時効の完成を猶予できる |
| 債務の承認 | 相手が一部でも支払ったり、債務を認める発言をする | その時点で時効がリセット(更新) |
たとえば、相手が1万円だけ返済した場合でも「借金の存在を認めた」と見なされ、その時点から新しい5年(または10年)がスタートします。また、内容証明郵便を送ることで一時的に時効の進行を止めることができますが、その後6か月以内に裁判などの正式な手続きを取らなければ、再び進行を始めてしまいます。
改正後の新ルール「完成猶予」と「更新」
改正民法では、時効に関する用語も整理されました。「完成猶予」は時効完成を一時的に止めること、「更新」は時効をリセットし、ゼロから再カウントすることを意味します。この区別により、「止まるのか」「やり直しになるのか」が明確になり、実務でも時効管理がしやすくなりました。とくに相続や会社取引の場面では、時効期間の管理ミスが損失につながることが多く、定期的な確認と記録の保存が重要です。
時効をめぐる相続上のトラブル事例
事例①:名義放置した不動産が他人のものに?
被相続人名義のまま20年以上放置した土地に他人が住み続けていた場合、その人が「取得時効」を主張すると、相続人は取り戻せなくなるおそれがあります。→ 相続登記義務化(2024年4月施行)により、3年以内の登記申請が義務となっています。
事例②:相続した預金の請求を忘れていた
銀行預金は10年で休眠扱いとなり、時効で引き出せなくなることがあります。また、亡くなった親が誰かにお金を貸していた場合も、5年で時効消滅します。→ 相続後は速やかに金融機関や債務者に請求しましょう。
事例③:合同会社の持分払戻しを請求し忘れた
相続人が合同会社の社員を承継せず退社した場合、会社に対して持分払戻請求が可能ですが、退社の日から5年で時効消滅します(会社法606条)。請求が遅れると払戻しを受けられず、税務上も「損金不算入」などの問題が発生します。
時効は「権利を守る制度」でありながら、「放置すると権利を失う制度」でもあります。登記を怠ったり請求を後回しにしたりすることで、思わぬ損失につながることもあります。当事務所では、司法書士として登記実務を、税理士として税務上の時効処理を一体的に確認し、相続財産の保全から合同会社の持分整理まで、総合的にサポートしています。時効が迫っている、またはすでに過ぎているかもしれないという場合でも、まずはお気軽にご相談ください。

司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。合わせて、複数の資格を活かして会社設立や税理士サービスなどで多方面からクライアント様に寄り添うサポートを行っている。