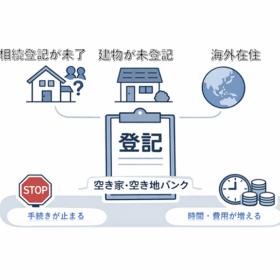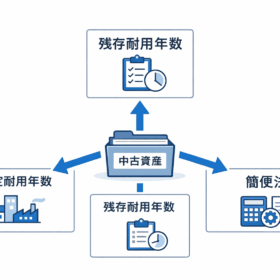Last Updated on 2025年10月23日 by 渋田貴正
匿名組合契約とは、出資者が営業者の事業に資金を出し、その事業から生じた利益を分配してもらう契約のことです。
商法で定められており、簡単にいえば「出資だけをして経営には関与しない投資契約」です。
| 商法 (匿名組合契約)
|
この契約では、営業者(事業を行う側)が実際に事業を営み、出資者(匿名組合員)はその事業の成果に応じて利益を受け取ります。
たとえば、不動産投資やクラウドファンディングなどの仕組みでよく利用されています。
匿名組合の出資者は、営業者の対外的な契約関係には一切登場せず、営業者名義で事業が行われます。
つまり、出資者の名前が登記や契約書に出てこない、まさに「匿名」な構造となっています。
出資者と営業者の立場
匿名組合契約における2者の関係を整理すると、次のとおりです。
| 立場 | 内容 |
| 営業者 | 出資を受けて事業を行い、利益を生み出して出資者に分配する。事業の責任を負う。 |
| 匿名組合員 | 出資のみを行い、事業運営には関与しない。出資額を限度に損失リスクを負う。 |
出資した資金は営業者の財産に帰属するため、匿名組合員は直接的な経営権や所有権を持ちません。
この点が、他の組合契約や会社組織との大きな違いです。
他の組合契約や合同会社との違い
匿名組合契約は、同じ「出資+利益分配」という構造をもつ任意組合や合同会社と混同されることがあります。
それぞれの仕組みを理解しておくと、目的に合った形を選びやすくなります。
匿名組合と任意組合との違い
任意組合は民法上の組合契約に基づくもので、出資者全員が「組合員」として事業の運営に関与します。
| 民法 (組合契約)
|
たとえば、不動産共同所有や共同開発などに利用され、出資者自身が事業の権利義務を直接負います。
これに対し、匿名組合では営業者が事業の主体となり、出資者は「表に出ない存在」です。
匿名組合と合同会社との違い
合同会社(LLC)は会社法上の法人であり、登記を経て法人格を取得します。
匿名組合はあくまで契約にすぎず、独立した法人格はありません。
また、合同会社では出資者(社員)が業務執行権を持つか否かを定款で決めることができますが、匿名組合員は一切経営に関与しません。
また、合同会社では出資した持分に応じて損益配分が行われますが、その利益は法人課税後に利益の分配として支払われます。(もちろん合同会社内に留保しておいても問題ないです。)
一方、匿名組合の分配金は営業者の所得計算に含めたうえで匿名組合員に分配されるため、所得区分が異なります。
まとめると以下のようになります。
| 比較項目 | 匿名組合 | 任意組合 | 合同会社 |
| 法的根拠 | 商法 | 民法 | 会社法 |
| 法人格 | なし | なし | あり |
| 出資者の地位 | 匿名組合員(非公開) | 組合員(共同事業者) | 社員(出資者) |
| 出資者の経営関与 | なし | あり | あり |
| 不動産の所有権 | 営業者名義 | 組合名義または共有 | 会社名義 |
| 損失の範囲 | 出資額まで | 無限責任 | 出資額まで |
| 利益分配 | 契約による | 契約による | 定款による |
| 税務上の扱い | 原則:出資者は雑所得 | 各組合員の事業所得等に按分 | 法人課税後に利益の分配 |
匿名組合の税務上の取り扱い
ここでは、匿名組合契約の税金面の扱いを整理します。
出資者(匿名組合員)側の税務
匿名組合からの利益分配は、原則として「雑所得」に分類されます。
雑所得は、給与や不動産所得など他の所得と損益通算できないため、たとえ出資損失が生じても相殺はできません。
また、損失を翌年に繰り越すこともできません。
ただし、匿名組合出資を事業として継続的に行っており、事業所得と認められる場合には、例外的に他の所得との損益通算が認められることもあります。しかし、一般的な投資やクラウドファンディング出資では雑所得扱いが原則です。
利益分配金が支払われる際には、営業者が源泉徴収義務者となって所得税(約20.42%)を源泉徴収します。
出資者は確定申告により、総合課税の雑所得として他の所得と合算して税額を確定させます。
営業者側の税務
営業者は、法人・個人に関わらず匿名組合契約に基づく事業の損益を自らの所得として計上します。
匿名組合員に対する利益分配は、費用ではなく「損益分配」として扱われるため、営業者の所得計算上は調整が必要です。
また、匿名組合員が個人である場合は源泉徴収義務が生じます。
匿名組合契約は法人格を持たないため、会社設立のような登記手続きそのものは不要です。
不動産にしても組合名義の登記は存在せず、営業者の名義で行われます。
ただし、不動産特定共同事業など特別な事業形態に用いる場合には、別途行政庁への届出や登録が必要になるケースがあります。
匿名組合を抜けるときの扱い(脱退・契約終了)
匿名組合契約では、原則として契約期間の途中で自由に抜けることはできません。
商法上も、匿名組合員の地位は契約で定めた期間中は拘束されるのが基本です。
脱退できるのは、以下のような場合に限られます。
- 契約期間が満了したとき
- 契約書で定めた「解約事由」(例えば営業者の重大な契約違反や破産など)が生じたとき
- 営業者との合意により中途解約が認められたとき
途中で抜ける場合は、出資金の返還を受けられるかどうかは契約内容により異なります。
多くの場合、「事業終了後に清算して分配する」とされており、途中返金は認められません。
税務上も、脱退時に出資金の一部または全部が戻る場合、その差額が譲渡所得や雑所得として課税対象になることがあります。
たとえば、出資金100万円を拠出して70万円しか戻らなければ、その30万円は損失となりますが、基本的に雑所得となるので損失を他の所得(給与など)と相殺することはできません。逆に120万円戻った場合は、20万円が雑所得として課税される可能性があります。
したがって、匿名組合から脱退する際は、契約上の返還条件と税務上の所得区分を両面から確認することが重要です。
匿名組合契約の活用事例
匿名組合契約は、不動産運用・飲食店の共同出資・スタートアップ支援など、さまざまな形で活用されています。
ここでは代表的な3つの事例を紹介します。
事例① 不動産クラウドファンディング
不動産を小口化し、複数の出資者から資金を集めて運用するタイプです。
匿名組合員は実際の不動産の所有者にはならず、営業者が取得・運営・売却を行い、利益を分配します。
不動産取得税や登記手続きが不要で、少額から投資できる点が魅力です。
ただし、運用益は雑所得として総合課税されるため、税率が上がるケースもあります。
事例② 飲食店など小規模ビジネスの共同出資
友人や知人が経営する飲食店・カフェなどに対し、匿名組合契約で出資するケースです。
営業許可や店舗名義は営業者側にあり、出資者は経営に口を出さず、売上に応じた分配を受けます。
この方式を取ることで、出資者が経営責任を負わずに支援できるという利点があります。
ただし、途中で抜けにくい契約構造である点には注意が必要です。
事例③ スタートアップ支援・ベンチャー投資
会社設立直後の事業者に対して匿名組合契約で資金を提供するケースです。
株式を取得せずに「事業の一部収益への参加」という形で関与できるため、株主として登記されるリスクを避けられます。
近年は、VC(ベンチャーキャピタル)のスキームにも匿名組合が利用されています。
匿名組合契約は、出資・税務・契約のいずれも複雑な仕組みを含みます。
当事務所では、税理士と司法書士の両方の資格を有する専門家が、
「契約書のチェック」「登記・印紙税の確認」「利益分配時の税務処理」まで一貫してサポートします。
匿名組合契約を検討している方や、既に出資していて内容に不安がある方は、
ぜひ一度ご相談ください。複数の専門分野を横断して、最適なアドバイスをご提供いたします。

司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。合わせて、複数の資格を活かして会社設立や税理士サービスなどで多方面からクライアント様に寄り添うサポートを行っている。