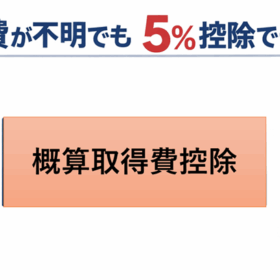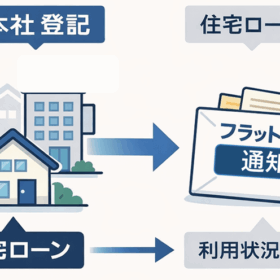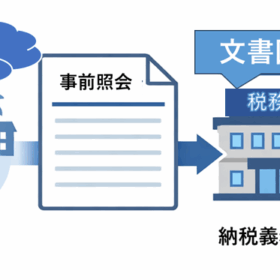Last Updated on 2025年10月5日 by 渋田貴正
会社が増資を行う場合、株主や出資者から新たな資金を受け入れます。この資金は会社の資本金となり、登記を経て初めて対外的に効力を持ちます。
そのため、払込みの方法を誤ると登記が却下されるだけでなく、税務上の解釈でも問題が生じる可能性があるため、口座の扱いはとても重要です。
増資における払込み口座選択の重要性
会社法では株式会社の増資時の口座について以下のように規定されています。
(出資の履行)
|
このように、条文上は「株式会社が定めた銀行等」とはなっていますが、「会社名義の口座」と限定されていません。「会社が指定した場所」であれば足りると読めます。
しかし、実務では登記申請において「確実に会社財産となったこと」を証明できる必要があり、結果的に会社名義の口座を利用することが必須となります。
会社名義以外の口座への出資金の入金は認められるか
結論から言えば、増資の払込みを会社名義以外の口座だけで完結させることは、実務的にはほぼ認められていません。法律上は「会社が指定した場所」に払込めばよいとされていますが、登記・税務の実務では「会社に資金が確実に帰属したこと」を明確に示すことが求められます。そのため、最終的には会社名義の口座に資金が入っていることが不可欠なのです。
代表取締役の個人口座を使うケースでは、「一時的な預かり」として入金を受けることは形式上可能かもしれません。しかし、その後に会社の口座へ資金を移し、その振替記録や通帳の写しなど、会社が実際に受け取ったことを客観的に示す証拠がなければ、登記は認められません。単に「社長の口座に振り込んだ」だけでは、会社財産になったとは言えないのです。
第三者(仲介人など)の口座を利用するケースは、さらに厳しく扱われます。会社との法律上の関係が明確でない第三者が一旦資金を受け取った場合、その段階では「会社への払込み」とは評価されません。法務局の登記審査でも、「会社の財産として確実に帰属した」と判断できる客観的資料が存在しなければ、申請は却下される可能性が高いです。
この点は、上場会社の増資手続きを見るとよく理解できます。上場会社では、株主や投資家が直接会社の口座に振り込むわけではなく、証券会社が払込取扱機関となり、投資家から資金を集めて一括で会社に払い込みます。つまり最初の段階では会社以外の機関が資金を受け取っているのです。しかし、重要なのはその後です。最終的に証券会社から会社の口座へ資金がまとめて振り込まれ、その入金が確認されて初めて増資が成立します。
非上場会社の場合も考え方はまったく同じです。代表取締役や第三者が一時的に資金を預かっていたとしても、最終的に会社名義の口座に入金された事実が確認できなければ、増資は有効に成立しません。この「二段階の流れ(第三者預かり → 会社口座入金)」があって初めて、会社に対して払込みがなされたといえるのです。
また、これは登記手続の前提というだけでなく、資金の性質から考えても当然のことです。増資で払い込まれた資金は、会社の資本金として会社の財産になるべきものです。したがって、会社の口座に入金されていない状態では、そもそも増資が完了したとは言えません。
このため、会社名義の口座を開設できていない株式会社では、形式的にも実体的にも増資を行うことはできません。会社口座の存在が、増資手続の前提条件になると考えてください。
なお、合同会社の場合は、会社法上、金融機関への払込みを必ずしも必要としていないため、口座がなくても増資は可能です。株式会社と合同会社とで、資金の扱いや登記上の要件が異なる点にも注意が必要です。
会社設立時については発起人ではなく代表取締役の口座でも認められる
会社設立時の払込みについては、会社名義の口座がまだ存在しないという特殊な事情があります。会社は登記によって初めて成立するため、設立前には会社名義の銀行口座を開設することができません。そこで、実務上は発起人(会社を設立する人)の個人口座に出資金を払い込み、その通帳の写しを添付することで登記が認められてきました。
さらに、法務省の通達では、発起人ではなく「設立時代表取締役」の個人口座を払込先とすることも一定の条件のもとで認められています。たとえば、発起人が複数いる場合や、発起人ではない人物が代表取締役に就任するケースなどです。この場合には、設立時代表取締役が発起人から出資金を受領する権限を有していることを証する書面を添付する必要があります。ただし、代表取締役以外の人(単なる取締役や全くの第三者)が会社設立時の出資金の受領代理人となることは認められていません。
つまり、設立時に限っては「会社名義以外の口座」が例外的に認められる仕組みが整えられているのです。ただし、これは会社設立という一度限りの手続きに限定された特例であり、増資のように会社成立後の払込みには適用されません。登記審査でもこの点は厳格に区別されていますので、設立時と増資時の違いを正確に理解しておくことが重要です。
増資の払込みは、登記・税務の両面から非常に重要な手続きです。
形式を誤れば、登記が通らないだけでなく税務リスクにもつながります。
当事務所では、司法書士と税理士の双方の知識を活かして、確実に安全な増資手続きをサポートしています。
「会社の成長を支えるために増資をしたいが、手続きが不安…」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。

司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。合わせて、複数の資格を活かして会社設立や税理士サービスなどで多方面からクライアント様に寄り添うサポートを行っている。