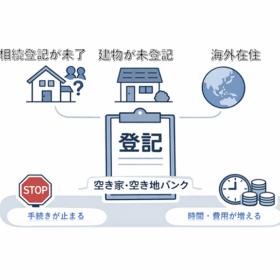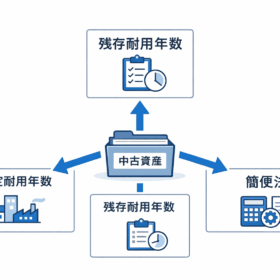Last Updated on 2025年10月6日 by 渋田貴正
役員報酬を多くとるか、会社にお金を残すか――。このテーマは、特に一人会社や家族経営などの小規模な会社でよく議論になります。代表者自身が主要な役員・株主であり、実質的に「会社のお金=自分のお金」という感覚を持つ経営者も少なくありません。そのため、役員報酬を多めに設定して個人で資金を保有しておくべきか、あるいは法人に資金を残しておくべきかは、税金・資金繰り・将来計画に直結する重要な経営判断になります。
どちらを選ぶかによって、税金や社会保険の負担額だけでなく、将来の資金繰りや事業の安定性に大きな差が生じます。ここでは、税務と経営の両面から、それぞれの考え方と注意点をわかりやすく解説します。
役員報酬と会社利益の基本的な関係
まず、役員報酬とは、会社の役員(代表取締役・取締役など)が会社から受け取る給与のことです。役員報酬を増やせば、会社の利益は減少し、法人税は少なくなりますが、役員個人の所得税や住民税は増えます。逆に、役員報酬を少なくすれば、会社の利益は増えるため法人税は増えますが、個人の税負担は減少します。
つまり、役員報酬と会社利益は「シーソー」のような関係にあります。どちらかを増やすと、もう一方は減る仕組みです。
役員報酬を多くとるメリット・デメリット
役員報酬を多くとる場合の特徴を、以下の表にまとめました。
| メリット | デメリット |
| ・法人税を減らせる(経費になるため) ・生活資金を確保しやすい ・役員個人の社会保障(年金・健康保険)を厚くできる |
・所得税・住民税・社会保険料の負担が増える ・会社に資金が残りにくくなる ・金融機関から見た自己資本が減る可能性 |
例えば、会社の利益が1,000万円ある場合、役員報酬を600万円とすると、法人税は利益400万円に対して課税されます。一方で、個人側は600万円に対する所得税・住民税・社会保険料を負担します。法人税率よりも所得税率が高い場合、全体として税負担が増えるケースもあります。
会社にお金を残すメリット・デメリット
次に、役員報酬を抑えて会社に利益を残す場合です。特に中小企業では、資金繰りの安定性という面でも大きな意味があります。
| メリット | デメリット |
| ・会社の内部留保が増える ・将来の設備投資や融資の信用力が高まる ・社会保険料の負担を抑えられる ・急な支出や売上減少時に備えられる |
・法人税の負担が増える ・役員個人の手取りが少なくなる ・内部留保に偏ると資金の使い道に困ることもある |
中には、「役員報酬を多めにとっておいて、資金が必要になったら役員から会社に貸し付ければよい」という考え方もあります。確かに、役員からの貸付金は登記や手続きが不要で、必要なときにすぐ資金を戻せる柔軟な方法です。ただし、現実にはこの方法にはいくつかの注意点があります。
第一に、いったん役員個人の所得になってしまうため、所得税や社会保険料は確定的に発生します。会社に戻すときに税金が戻るわけではありません。第二に、個人の資金を会社に戻すには一度自分の生活資金から支出することになるため、資金繰りの面で必ずしもスムーズとは限りません。特に大きな金額になると、個人の預金残高や融資の可否にも左右されます。
一方、最初から会社に資金を残しておけば、法人の資金として継続的に管理できます。法人名義の預金を厚くしておくことで、突発的な支出や売上減少への備えにもなりますし、金融機関の融資審査でも有利です。将来の投資や不測の事態に備える「会社の貯金」と考えると、資金を法人内に残しておくメリットは非常に大きいといえます。
事例:役員報酬を多くとる場合と会社に残す場合の比較
【前提条件】
・会社の利益(役員報酬控除前)1,000万円
・法人税率20%
・個人の所得税+住民税率30%
・社会保険料概算15%
① 役員報酬を800万円に設定した場合
・法人利益:200万円 → 法人税 40万円
・役員報酬:800万円 → 所得税等 240万円+社会保険120万円
→ 合計税・社保負担 400万円
② 役員報酬を400万円に設定した場合
・法人利益:600万円 → 法人税 120万円
・役員報酬:400万円 → 所得税等 120万円+社会保険60万円
→ 合計税・社保負担 300万円
さらに、②のように会社に600万円の利益を残しておけば、翌期に設備投資や資金繰りで柔軟に活用できます。一方、①の方法では個人で多く受け取った分から会社に貸し戻す必要があり、所得税等はすでに支払っているため、実質的な再投入コストが高くなる点に注意が必要です。
相続時の違いと注意点
役員報酬を多くとるか、会社にお金を残すかという問題は、相続の場面でも非常に重要な影響を及ぼします。
代表者が亡くなったとき、会社に残っている資金は「株式」の評価に反映され、個人の現金とは扱いが異なります。
例えば、
- 個人で現金100万円を保有していた場合 → 相続財産として100万円がそのまま課税対象
- 100%株主の会社に純資産100万円がある場合 → その会社株式の評価額として課税
小規模オーナー会社の株式評価は、原則として「純資産価額方式」で行われます。したがって、会社の純資産100万円は、株式評価としてほぼ同額が課税対象となり、評価額という点では大きな差はありません。
しかし、納税資金の観点では大きな違いがあります。
現金であれば、そのまま相続税の納税に充てられますが、会社の資金は法人のものなので、相続人が自由に使えるわけではありません。
株式を相続したあと、会社から資金を引き出すには、次のいずれかの手続きが必要になります。
- 役員報酬として支給(所得税・社会保険負担が発生)
- 配当として支給(配当課税あり)
- 会社からの貸付(将来の返済義務が発生)
つまり、会社にお金を残しておいた場合、相続発生後に資金を取り出すには追加の課税や手続きが必要になる可能性があります。納税資金を用意する上では、個人で現金を持っている方がシンプルです。
また、分割のしやすさにも差があります。現金は法定相続分などに応じて分けることができますが、株式は分割が難しく、遺産分割や経営権の問題が絡みやすいです。特に複数の相続人がいる場合、株式の帰属を巡ってトラブルになるケースもあります。
以下に違いを整理します。
| 項目 | 個人の現金100万円 | 会社の純資産100万円(100%株主) |
| 相続税評価額 | 100万円 | 100万円(純資産価額方式) |
| 納税資金 | すぐに使える | 会社からの配当・報酬・貸付が必要 |
| 分割のしやすさ | 容易 | 株式は分割困難、承継設計が必要 |
| 追加課税の可能性 | なし | 配当・役員報酬に伴う二重課税リスク |
「会社にお金を残しておけば相続税が減るのでは?」という誤解もよくありますが、100%株主の場合、会社の純資産がそのまま株式評価に反映されるため、単純な節税効果はありません。
むしろ、納税資金が不足して株式を担保に融資を受けたり、資金を出す際に二重課税が発生したりと、問題が複雑になるケースが多いのです。
もっとも、会社と個人の財布をきちんと分けて考えられるタイプの経営者であれば、会社に資金を残し、生活に必要最低限の役員報酬だけを受け取ることで、長期的に見て最終的なキャッシュを増やせるケースもあります。
余剰資金を個人に移してしまうと、所得税や社会保険料が確定的に発生し、その後の運用も個人単位になります。これに対し、法人に資金を残すことで法人税率を活かしつつ、計画的に将来の投資や承継資金として蓄えることができます。
つまり、税制上はどちらが有利というよりも、経営者の資金管理の姿勢によって結果が大きく変わる可能性もあります。
いずれにしても、役員報酬と内部留保のバランスを考える際には、事業計画や税金だけでなく、将来の相続・事業承継まで見据えた設計が非常に重要です。
社会保険・金融機関・将来の出口戦略にも影響
役員報酬額は、税金だけでなく社会保険や資金調達にも影響します。役員報酬を高く設定すると、厚生年金の加入金額も増えるため、将来の年金受取額が増えるメリットがあります。一方で、毎月の社会保険料の会社負担・個人負担も増えるため、キャッシュフローに影響します。
また、会社にお金を残すと、自己資本比率が高まり、金融機関から融資を受けやすくなることがあります。特に新規事業や不動産購入を予定している会社では、内部留保を積み上げておく戦略が有効です。
さらに、将来的に会社を売却する「事業承継」や「M&A」の場面でも、会社に資金が残っている方が評価が高くなる場合があります。一方で、個人の退職金戦略と合わせて役員報酬をコントロールすることも可能です。
役員報酬と会社利益の最適バランスを考える
結論として、「役員報酬を多くとるのがよいか」「会社にお金を残すのがよいか」は一概には言えません。
会社の利益水準、今後の投資計画、融資の必要性、役員の生活費や退職金戦略などを総合的に考える必要があります。税率だけで判断すると、かえって損をするケースもあります。
特に、役員報酬は一度決定すると原則として期中に変更できません(定期同額給与の原則)。安易に高額報酬を設定してしまうと、後から柔軟に調整することが難しくなります。慎重なシミュレーションと計画が重要です。
当事務所では、税理士・司法書士として、会社の将来を見据えた役員報酬の設計、内部留保のバランス、登記・税務申告まで一括でサポートしています。税金だけでなく資金繰りや将来計画を踏まえた最適な報酬設計をお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。

司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。合わせて、複数の資格を活かして会社設立や税理士サービスなどで多方面からクライアント様に寄り添うサポートを行っている。