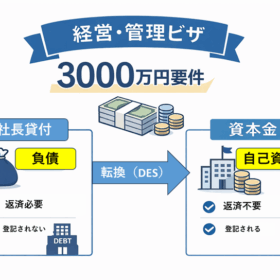Last Updated on 2025年9月24日 by 渋田貴正
会社を設立して経営していると、合併や解散、組織変更など、会社法で定められた「公告(こうこく)」を行わなければならない手続きに直面することがあります。これまで、こうした公告を官報(国が発行する新聞のような公的な刊行物)に掲載した場合、その掲載紙が後日郵送されて手元に届くのが一般的でした。
しかし、2025年4月1日の「官報の発行に関する法律」の施行により、この仕組みが大きく変わり、官報公告の掲載確認がオンラインで可能になっています。官報という国家の重要な公報をオンライン化することで、日本のデジタル行政の進展の象徴とし、国民への情報公開を促進するというのが狙いの一つです。
官報公告とは?
まず「官報公告」とは何かを整理しておきましょう。
官報は、内閣府が発行する国の機関紙で、法律・政令・告示のほか、会社法や民法に基づいて公告すべき内容も掲載されます。「広告」ではなく「公告」ですので注意しましょう。
会社に関係する代表的な官報公告の例
会社法などの規定により、一定の事項については「公告(官報への掲載)」が義務付けられています。主な例を以下の表にまとめました。
| 公告の種類 | 公告が必要となる主なケース | 内容の概要 |
| 決算公告 | 株式会社が事業年度ごとに計算書類を作成した後 | 貸借対照表の要旨などを官報に掲載し、会社の財務状況を外部に知らせる |
| 合併公告 | 会社が合併をする場合 | 合併の方式・効力発生日・債権者保護手続きに関する事項を公告 |
| 会社分割公告 | 会社分割を行う場合 | 分割の内容・効力発生日・債権者保護に関する事項を公告 |
| 減資公告 | 資本金を減少させる場合 | 減資の方法や効力発生日、債権者保護手続に関する事項を公告 |
| 解散・清算公告(債権者保護手続) | 会社が解散し清算に入る場合 | 債権者に対し、一定期間内に債権を申し出るよう公告 |
このように、官報公告は「会社が大きな組織変更や財務に関する重要な決定を行ったこと」を広く周知するための仕組みです。公告には債権者保護手続の一部を担うなどの重要な役割があります。
「官報の発行に関する法律」施行前の官報公告の確認方法
従来、官報に公告を掲載した場合、掲載された紙の官報が後日、官報販売所(東京都や各都道府県に設置)を通じて郵送されていました。
例えば、東京都内の会社が解散公告を行った場合、公告掲載日から数日後に、東京官書普及株式会社などの取次所から、掲載された紙の官報が送られてきます。
この紙面を社内で保管し、金融機関や取引先に提示することで「きちんと公告をした」という証拠として利用できました。
しかし、紙ベースでのやり取りには次のような課題がありました。
- 郵送に時間がかかるため、すぐに確認できない
- 郵便事故や紛失のリスクがある
- 保管場所を確保する必要がある
- 複数の関係者に共有する際に不便
こうした背景から、近年はデジタル化の流れに合わせて、官報の電子化・オンラインでの確認体制が整えられてきました。
「官報の発行に関する法律」施行によるオンラインでの確認
現在は、官報の紙面が自動的に郵送されることはなく、内閣府の「官報情報検索サービス」や「インターネット版官報」からPDFをダウンロードして確認する方法に変更されています。
内閣府 官報発行サイトの利用方法
- 内閣府の官報サイト(https://www.kanpo.go.jp)にアクセスします。
- 公告を掲載した日付を入力し、対象の「本紙」または「号外」を開きます。
- 掲載箇所(ページ番号)を探す際には、公告を依頼した際に付与された「受付番号」を利用します。
※東京都の場合、公告依頼をすると「受付番号」が記載された控えが送られてきます。掲載日以降に「東京官書普及株式会社」のホームページ(https://www.tokyo-kansho.co.jp/koukoku/page-search)からこの番号を入力することで、正確な掲載ページを確認できます。
他の都道府県でも、官報の取次所を通じて同様の案内が行われており、現在は全国的にオンラインでの確認が基本となっています。
官報公告確認方法のビフォーアフター
| 項目 | 従来(紙ベース) | 現在(オンライン化後) |
|---|---|---|
| 確認方法 | 官報販売所や取次所から紙の官報が郵送されるのを待つ | 内閣府の官報サイトからPDFを即日ダウンロード |
| 掲載確認のタイミング | 掲載から数日~1週間後に郵送物到着後に確認可能 | 掲載日当日から確認可能 |
| 証拠資料の利用 | 紙の官報をそのまま保管・提出 | 電子署名付きPDFを印刷・またはデータで利用可能 |
| 検索方法 | 紙のページをめくって探す | 掲載日や号数、受付番号を入力して検索 |
| リスク | 郵便事故や紛失、保管場所の確保が必要 | インターネット環境が必要、番号を誤入力すると探しにくい |
| 共有のしやすさ | コピーや郵送が必要 | PDFをメール添付やクラウド共有で容易に対応可能 |
| コスト面 | 紙の購読費用・郵送費用が発生 | 基本的に無料でダウンロード可能(検索サービス利用時は有料の場合あり) |
官報のオンライン化に伴う実務への影響
オンライン化は便利になった一方で、いくつか注意点もあります。
- 検索機能の制限
内閣府の公式サイトでは、官報の「本紙」「号外」を日付や号数で探すことはできますが、自由検索機能はありません。受付番号や正確な掲載日がわからないと探すのに手間取る可能性があります。 - PDFの真正性
官報のPDFは「電子署名付き」で発行されます。これは、国が発行した正規のものであることを証明する仕組みです。印刷した場合でも証拠書類として使用できますが、電子申請で提出する場合には電子署名の検証が必要となる場合があります。 - 関係者への共有方法
紙の官報が届かなくなったため、金融機関や取引先に提出する際は、自社でダウンロード・印刷して準備する必要があります。これを忘れると、口座解約や清算手続きがスムーズに進まない可能性があります。
会社の公告は、登記や税務の場面で大切な役割を果たします。オンライン化によって利便性は高まりましたが、正しい方法で確認・保管しておくことが重要です。
もし「公告の内容をどう確認すればよいのか」「登記や税務にどのように添付すればよいのか」といった不安がある方は、ぜひ当事務所にご相談ください。司法書士・税理士の立場から、公告の確認方法から登記・税務申告まで、安心してお任せいただけるようサポートいたします。

司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。合わせて、複数の資格を活かして会社設立や税理士サービスなどで多方面からクライアント様に寄り添うサポートを行っている。