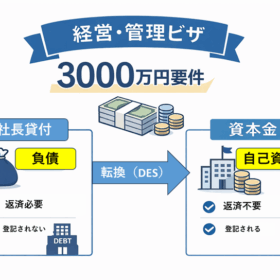Last Updated on 2025年9月6日 by 渋田貴正
労働者の定義見直しが始まった背景
2025年5月2日、厚生労働省は「労働基準法における労働者の範囲」を検討する有識者研究会を立ち上げました。労働者保護を目的とする労基法の「労働者」定義は、1985年の基準以来大きく改正されておらず、フリーランスやギグワークといった新しい働き方に対応しきれない状況が続いています。
ただし注意すべきは、この見直しは現段階では、あくまで労基法上の「労働者」定義の議論であり、健康保険法・厚生年金保険法・所得税法・消費税法といった他の法律に自動的に波及するわけではない、という点です。
法律ごとの「労働者」「被保険者」の定義
他の法律に波及するかどうかは、それぞれの法律で「労働者」がどのように扱われているかによります。そこで以下に、主な関連法令での定義を比較してみましょう。今回の改正によってこの定義にも影響するならば、その他の法律への波及もあり得るかもしれません。
| 法律 | 条文抜粋 | 趣旨・対象範囲 |
| 労働基準法 | 「労働者とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用され、賃金を支払われる者をいう」 | 使用者の指揮命令下で労務を提供し、賃金を得る人を広く含む |
| 健康保険法 | 「この法律において被保険者とは、適用事業所に使用される者をいう」 | 雇用契約を前提にした被用者を対象 |
| 厚生年金保険法 | 「この法律において被保険者とは、適用事業所に使用される者をいう」 | 健康保険とほぼ同様の定義 |
| 雇用保険法 | 「労働者とは、職業の種類を問わず、事業に使用され賃金を支払われる者をいう」 | 実態は労基法に近いが、保険給付が前提 |
| 所得税法 | 「給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費、賞与その他これらに類する性質を有する給与に係る所得をいう」 | 法文上「労働者」の定義はなく、実態判断で給与か事業かを区分 |
| 消費税法 | 「課税仕入れとは、事業として対価を得て行う資産の譲渡等に係るものをいう。ただし給与等は含まない」 | 事業者への支払いは課税、給与は非課税 |
この比較から分かるように、労基法の定義見直し=他法令の自動改正ではありません。ただし、実務上は労基法で労働者性が広く認定されれば、それが社会保険・税務の判断にも影響を与える可能性があります。
社会保険への影響──加入義務は拡大する?
健康保険法や厚生年金保険法は「適用事業所に使用される者」を被保険者と定義しています。ここでの「使用される者」が、労基法の労働者性判断を参考にされるケースが多いため、労基法の定義が広がれば、実質的に社会保険の加入対象者が増える可能性があります。
事例
- 「業務委託」として契約しているが、勤務時間や業務内容が会社の指揮命令下にあるデザイナー。
→ 労基法改正後に労働者とみなされれば、「適用事業所に使用される者」として、健康保険・厚生年金加入が必要とされる可能性
税務への影響
税務への影響としては、主に所得税と消費税が考えられます。
所得税への影響ー事業所得か給与所得か
所得税法では「給与所得」という定義があるものの、「労働者」という概念を直接は規定していません。実務では、報酬が給与所得か事業所得かは、契約関係・指揮命令の有無・業務の独立性などで判断されています。
労基法で労働者と判断される事例が増えると、税務当局もその判断を参考にし、事業所得ではなく給与所得と認定する傾向が強まる可能性があります。
- 給与所得となれば、会社が源泉徴収義務を負い、年末調整を行います。
- 業務委託報酬として支払ってきたものについて、源泉徴収漏れを指摘されるケースも出てきます。
消費税への影響ー課税か非課税か
消費税法は「給与」を非課税としています。したがって、労基法で労働者と判断される人が増えると、その報酬が給与扱いとなり、消費税がかからなくなる可能性があります。
具体例(50万円の報酬)
- 業務委託の場合:55万円(消費税10%含む)請求。会社は仕入税額控除で5万円を相殺可能。
- 労働者扱いの場合:50万円の給与。消費税なし。会社は仕入税額控除が使えず、実質負担が増える可能性。
つまり、同じ金額の支払いでも「業務委託」と「給与」では会社の消費税負担に大きな差が生まれます。
今回の研究会での議論は労基法の範囲にとどまりますが、今後の実務運用によっては社会保険・税務・消費税・登記に影響が及ぶ可能性が高いといえます。
- 社会保険の加入義務をどう判断すべきか
- 源泉徴収漏れのリスクを避けるにはどうするか
- 消費税の処理にどのような影響が出るか
こうした不安を感じたときは、ぜひ当事務所へご相談ください。税務と登記の両面から、安心できる対応をご提案いたします。

司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。合わせて、複数の資格を活かして会社設立や税理士サービスなどで多方面からクライアント様に寄り添うサポートを行っている。