Last Updated on 2025年8月11日 by 渋田貴正
海外在住の方が日本で会社設立を行う場合、日本在住の共同代表(株式会社なら代表取締役、合同会社なら代表社員)を置く形がよく選ばれます。理由はシンプルです。銀行の法人口座開設や契約締結、郵送物の受領など、国内の実務を日本在住の代表が円滑に担えるからです。
本来、代表取締役や代表社員といった代表者は会社を対外的に代表する立場ですが、口座開設や本人確認などを円滑に進める実務上の配慮として、日本在住の方を共同代表に迎えることがあります。これは名目上の形だけではなく、現地での最終署名や各種手続を確実に進めるための実務的な体制整備という位置づけです。
登記面でも、株式会社・合同会社ともに「代表者の氏名・住所」は登記事項です。この点を踏まえ、国内住所の代表者を掲げると、取引先や金融機関とのやり取りがスムーズになりやすい事情があります。
もっとも、この方式には生体認証(顔認証・指紋認証)を前提とする銀行アプリの運用という、新しいハードルが生じているのが現状です。
生体認証がもたらす「良い点」と「落とし穴」
生体認証の良い点:不正防止と迅速承認
スマホの生体認証は、パスワードより強い本人確認となり、不正ログインの抑止に役立ちます。承認操作も素早く、誤入力のリスクを下げられます。
生体認証の注意すべき点:登録者の端末に依存しがち
法人口座開設時に日本在住の代表がアプリの初期設定と生体認証を登録すると、その端末に承認フローが紐づく銀行が少なくありません。すると、海外在住の代表が自分のスマホにアプリを入れても、承認やログインに国内代表の生体認証が必要となり、遠隔地からの資金移動や承認が止まることがあります。
背景には銀行に課される厳格な本人確認義務(KYC;Know Your Customer”)があります。金融機関は口座開設・一定の取引時に本人確認を行い、記録を保存する義務があります。非対面確認は、犯収法施行規則に定める方式(ICチップ読み取りと容貌照合、公的個人認証の活用など)に従って実施されます。
海外在住の代表者が共同代表制で口座開設する場合のポイント
登記の観点
株式会社の設立登記の登記事項には「代表取締役の住所」等が含まれ、合同会社の設立登記でも「代表社員の氏名・住所」等が登記事項です。共同代表として日本在住の代表を置くこと自体は法的に整合しています。
会社法上の観点
株式会社の代表取締役は、会社の業務に関する一切の裁判上・裁判外の行為をする権限を有します。承認フローや送金権限はこの包括的代表権を踏まえた社内統制の設計だと考えると整理しやすいです。
いずれも法的に正当な行為ではありますが、口座開設や、社内での振込業務の連携という実務上の観点で支障が生じうるということです。
遠隔地に住む代表者が「自分のスマホ」で使えるようにする実務対応
ここでは銀行名や個別仕様には踏み込まず、どの銀行でも応用しやすい考え方と手順を示します。ポイントは、
- 生体認証に人(誰)と端末(どれ)を正しく紐づける、
- 生体認証が難しい場面の代替手段を用意する、
- 社内の権限設計で“止まらない”体制を作る、の3点です。
ステップ1:開設前に「運用設計」を決める
- 誰がどの端末で振り込みに関する日常承認を行うか(国内代表/海外代表/両方)を決めます。
- 権限分掌(作成者/承認者/最終承認者)や二要素認証(生体+OTP)を前提に、止まらない運用を設計します。
ステップ2:海外在住代表の「初期登録」をどう行うか
方法1 アプリ登録時に海外在住の代表者が立ち会う
-
担当者がスマホを持って代表者に会いに来る or 郵送でスマホを一時的に送ってもらう
-
代表者が実際にそのスマホで顔認証をして登録
-
登録後はそのスマホを担当者が通常どおり使用可能(顔認証は最初の1回のみ)
方法2 日本在住の代表者のスマホにアプリを入れて認証後に海外在住代表者のスマホに再設定
-
代表者のスマホでアプリをダウンロードして顔認証を完了
-
その後、代表者が設定を解除
-
担当者のスマホで再登録(再び顔認証が必要)
- 代表権の所在を明確に
株式会社の代表取締役は包括的代表権を持ちます。誰が最終承認者かを取締役会や社員総会の方針と整合させると安心です。 - 登記の正確性
代表者の氏名・住所等の登記と、銀行に届け出る実際の承認権限者の情報が齟齬を起こさないよう整えます。承認者を変更したのに銀行権限を更新し忘れる、という“あるある”を防ぎましょう。 - 税務上の実務
支払・入金の承認や証憑の保管は、取引記録として社内で統制・保存します。税務調査でも、誰がいつ承認し送金したかを説明できる体制が望ましいです。
当事務所は、海外在住代表+日本在住共同代表という体制での会社設立・登記から、法人口座の運用設計、生体認証/eKYC対応など実務に寄り添って並走します。最新の本人確認ルールを踏まえ、遠隔地でも止まらない送金フローをご提案します。まずは状況をお聞かせください。最適な進め方をわかりやすくご案内いたします。

司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。合わせて、複数の資格を活かして会社設立や税理士サービスなどで多方面からクライアント様に寄り添うサポートを行っている。










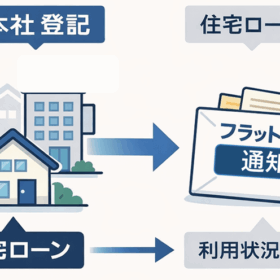

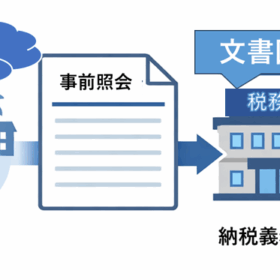

時課税-280x280.png)
