Last Updated on 2025年8月10日 by 渋田貴正
合同会社では、社員の死亡は法定退社事由です。
(法定退社)
|
社員が一人だけなら、死亡と同時に社員が誰もいない状態になります。そして社員が1人もいない状態になると、合同会社は解散します。
(解散の事由)
|
-
- ただし、もし定款において、社員の持分について相続権が規定されていれば、相続人が社員となり、合同会社が存続する可能性はあります。こうしたケースを除いて、合同会社の唯一の社員が死亡=解散となります。
株式会社は「株主が死亡しても株式が相続される」ので基本的には株主不在になりません。ここが合同会社との最大の違いです。合同会社では、株式会社の自己株式のような状態(いわゆる自己持分)の状態は認められませんので、社員が0名=会社の所有者がいない=そのまま解散ということになります。
合同会社の唯一の社員が死亡した場合の清算人は誰がなる?
合同会社の唯一の社員が死亡すれば、解散の手続きのために清算人の選任が必要です。
合同会社の唯一の社員が死亡すると、会社法により会社は解散します。解散後は、財産の処分や債務の弁済などを行う「清算人」を選任しなければなりません。清算人は、以下の通りに定まります。(法定清算人)
1)定款に定めがあればその者が就任
2)定款に定めがなければ社員の過半数で定める者が就任
3)1)、2)の者がいなければ業務執行社員が就任
しかし唯一の社員が死亡している場合は社員の過半数で定めることもできず、業務執行社員も存在しないため、この規定は適用できません。
このように法定清算人がいない場合、利害関係人や相続人などの申立てにより裁判所が清算人を選任します。清算人は会社の財産を管理・換価し、債権債務の精算を行い、残余財産を分配する重要な役割を担うため、誰でも自動的になれるものではありません。特に、相続人であっても当然に清算人になるわけではなく、就任には選任手続が必要です。
したがって、唯一の社員が死亡した合同会社では、まず清算人の人選と選任申立てを早急に行うことが、円滑な清算と期限内の税務申告に不可欠です。
しかし、もし定款に持分の相続に関する規定があればこうした面倒な事態は防ぐことができます。解散させる場合でも、いったん相続による社員の加入をして、その社員がそのまま清算人になればよいからです。(合同会社の債権債務の状態にもよりますが。特に債務超過の場合は清算人を選任してもらった方がよいケースもあります。)
合同会社の社員が0人になり、解散したらその日に事業年度が終了
法人税法は、内国法人が解散した場合、解散日がその事業年度の終了日になると定めます。つまり、死亡日=解散日=決算日の扱いです。
| (事業年度の特例) 法人税法 第14条 次の各号に掲げる事実が生じた場合には、その事実が生じた法人の事業年度は、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に終了し、これに続く事業年度は、第二号又は第五号に掲げる事実が生じた場合を除き、同日の翌日から開始するものとする。 一 内国法人が事業年度の中途において解散(合併による解散を除く。)をしたこと その解散の日 |
地方税(法人住民税)にも、清算中・清算確定で別期限があるため、市区町村の案内を確認しましょう(多くは「清算中2か月」「清算確定1か月」などの独自期限がある場合があります)。
ここで気になるのが解散決算において法人税の申告書に記名する人です。原則、解散後の会社を代表するのは清算人です。清算人が決まっていれば、その清算人が申告書に記名すれば問題ありません。
しかし、唯一の社員が死亡すると法人税の申告期限までに清算人の選任が間に合わないことがあります。
その場合の現実的な選択肢は次のとおりです。
| 清算人の選任申立てを急ぐ。 | 会社法では、清算人となる者がいないときは裁判所が選任できると定めます。 |
| 申告期限の延長を申請する。 | やむを得ない事情があるときは、法人税法75条の2による提出期限の延長が可能です(別途手続が必要)。 |
| 相続人代表が代表者として申告する。 | 申告書の提出は行政手続であり、契約のような私法上の法律行為とは異なります。 通則法124条は「税務書類の提出者の氏名等の記載」を求めており、提出者欄に相続人代表を記載し、税理士が代理送信(電子委任)する運用が実務上みられます。念のため、管轄税務署に確認しておきましょう。 |
合同会社を存続させたい場合はどうする?
取引先が多い、収益性自体は高く経営を続けたほうが望ましいといったような場合に、せっかくある合同会社を解散清算するのがもったいないというケースがあります。
死亡=退社=解散が原則ですが、相続人が新たに社員として加入すれば、事業を継続できる場合があります。
- 相続人全員で方針決定(誰が社員になるか、複数加入も可)
- 定款で持分を相続して社員として加入できる規定があるかどうかを確認
- 変更の登記を2週間以内に申請(会社法915条1項)
- 通常どおり法人税の確定申告(決算期ベース)へ移行
※登記の2週間は変更が生じた日からカウントします。
相続税の注意(会社の持分は相続財産)
亡くなった社員が持っていた持分(経済的価値)は、相続税の対象です。一般に純資産価額方式などで評価します。申告期限は死亡から10か月が原則です。
※評価や必要書類は、事業の実態・借入金・在庫などにより大きく変わります。専門家の試算が安心です。
具体例(ケーススタディ)
例:父が唯一の社員。急逝。事業は黒字、主要取引先との契約継続が必要。
- 相続人会議で「長男が社員に加入」方針を決定。
- 定款に持分の相続に関する規定があることを確認
- 変更登記を2週間以内に申請
- 死亡日を解散日とする解散確定申告は不要
唯一の社員が死亡した合同会社は、登記・法人税・相続税が同時進行になります。
当事務所は税理士×司法書士のワンストップ体制です。
清算人選任の段取り、期限管理、申告書作成、相続税評価までまとめて伴走いたします。
「今すぐ何をすべきか」から一緒に整理しますので、まずは無料の初回相談で状況をお聞かせください。

司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。合わせて、複数の資格を活かして会社設立や税理士サービスなどで多方面からクライアント様に寄り添うサポートを行っている。






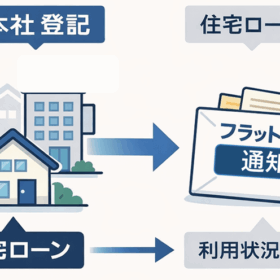

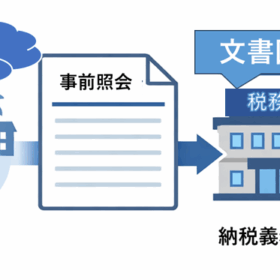

時課税-280x280.png)
