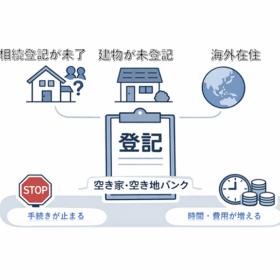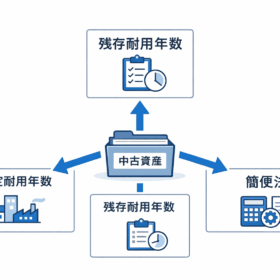Last Updated on 2025年7月20日 by 渋田貴正
会社を設立したばかりの方や、役員報酬の設計を進めている経営者にとって、「事前確定届出給与」は役員にもボーナスを出すための重要な制度です。役員に対するボーナス(賞与)を法人税上の損金にできる唯一の手段といっても過言ではありません。
しかし、この制度は非常に厳格なルールに基づいており、届出通りの金額や時期で支給が行われなければ、全額が損金不算入となる可能性があります。
特に注意したいのが、年に複数回支給する形式を採った場合に、その一部だけが届出と異なった場合です。本記事では、このようなケースについて、実際の年度を用いた具体例とともに、税務上の扱いを分かりやすく解説します。
事前確定届出給与の基本ルール
まずは制度の基礎を確認しましょう。事前確定届出給与とは、役員に対して賞与などの支給額と支給時期をあらかじめ決めて、税務署に届出を行うことで、その支給額を法人税上の損金に算入できるという制度です。
事前確定届出給与については、以下の3つの要件すべてを満たす必要があります。
| 要件 | 内容 |
| ① 決議要件 | 株主総会等で金額・支給日を明記した決議を行うこと |
| ② 届出要件 | 決議から1か月以内に税務署に届出書を提出すること |
| ③ 実行要件 | 決議・届出どおりの金額・時期で実際に支給すること |
【例1】複数回支給のうち一部が届出と異なると全額が損金不算入に
■ 事例
3月決算の法人が、2024年6月26日の定時株主総会において、役員に対して以下のような支給を決定し、事前確定届出を行いました。
- 2024年7月25日:300万円
- 2024年12月25日:300万円
ところが、実際にはこうなりました。
| 支給日 | 実際の支給額 | 会計年度 | 結果 |
| 2024年7月25日 | 300万円 | 2025年3月期 | 支給済み |
| 2024年12月25日 | 50万円(減額支給) | 2025年3月期 | 減額支給 |
この場合、職務執行期間(2024年6月26日〜2025年6月25日)内の支給が定めどおりに行われなかったため、原則通りに考えれば合計600万円のすべてが損金不算入となります。
なぜなら事前確定届出給与は、役員の職務執行期間、つまり定時株主総会から次の定時株主総会まで全体を一単位として、定め通りに支給されたかどうかを判断します。よって、その期間内の支給が一部でも届出と異なれば、全体が要件不充足=全額損金不算入とされてしまうのです。
【例2】前期分は定めどおり支給し、翌期分だけが届出と異なる場合
では、次のようなケースはどうでしょうか。
■ 事例
3月決算の法人が、2024年6月26日の定時株主総会において、役員に対して以下のような支給を決定し、事前確定届出を行いました。
- 2024年7月25日:300万円(2024年3月期)
- 2025年6月25日:300万円(2025年3月期)
実際の支給は以下のとおりです。
| 支給日 | 実際の支給額 | 会計年度 | 税務上の扱い |
| 2024年7月25日 | 300万円 | 2025年3月期 | ○ 損金算入可 |
| 2025年6月25日 | 50万円(減額支給) | 2026年3月期 | ✕ 損金不算入 |
このように、前期(2025年3月期)分は定めどおりに支給されたため損金算入が認められ、翌期(2026年3月期)分のみが不算入とされる取り扱いも、実務上は認められています。これは、役員ボーナスは支給日に損金に算入するため、翌期の分が減額、または不支給でも当期の課税所得に影響を与えないことから特別に認められている扱いです。
支給内容を変更したいときは「変更届」が必要
上記のように年度をまたいだ場合の支給については事業年度ごとに判断してよいといった特別の扱いはありますが、通常は業績の悪化や資金繰りの都合で、やむを得ず支給内容を変更したい場合は、「臨時改定事由」や「業績悪化改定事由」に該当すれば、変更届を提出することで対応が可能です。
ただし、変更届も「原則1か月以内」に提出する必要があるため、対応は計画的に行う必要があります。
| 内容 | 必要書類 | 提出期限 |
| 支給額・支給時期の変更 | 変更届出書 | 原則1か月以内 |
「とりあえず支払ってしまおう」「変更届はあとで……」という対応では、税務調査で全額否認されるリスクがあるため、慎重な対応が求められます。
【まとめ表】複数回支給の事前確定届出給与(役員ボーナス)における損金算入可否
| ケース | 損金算入 |
| すべて届出通り支給 | ○ 可 |
| 事業年度内の一部が届出と異なる | ✕ 全額不算入 |
| 前期分のみ届出通り、翌期分が異なる | ○ 前期のみ可 |
| 支給内容を変更し、変更届も提出 | △ 条件付きで可 |
| 支給内容変更済だが変更届未提出 | ✕ 不算入リスク高 |
制度を活かすも殺すも設計次第。当事務所が全力でサポートします
事前確定届出給与は、正しく使えば会社にとって強力な節税ツールになりますが、一歩間違えると「全額否認」という手痛い結果につながります。
当事務所では、会社設立時の役員報酬設計・株主総会議事録の作成・税務署への届出・実行支援まで一貫して対応しております。
ミスのない制度運用をしたい方は、ぜひお気軽にご相談ください。

司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。合わせて、複数の資格を活かして会社設立や税理士サービスなどで多方面からクライアント様に寄り添うサポートを行っている。